人生は舵取り次第です。舵取りを適切に行えば、躍進が可能になる。逆も真です。→熟年になって明暗がくっきりした同級生・同期生。同じことが日本モデルが成功要因から失敗要因に転じてしまった日本経済にも当てはまります。→マネジメントの仕組みは成功要因から失敗要因に転じてしまう 今の日本経済は泥舟状態です。枠内思考に留まっている限りこのような状態から決して脱出できないでしょう。なぜなら、国際競争が厳しさを増す一方であるので、力づくでは相手を圧倒しにくい。先行きがどんどん不透明になるので、過去の延長線上を歩んでいると激変環境に呑みこまれてしまうからです。 こういう時に出番となるのが「日本の魅力を発見するのではなく創出する ⇒ 縮み思考に陥っている民間の活力を引き出す ⇒ 持続的経済成長を実現させる ⇒ 財政を再建する」といいう図式の実現を可能にする戦略発想です。 アベノミクスはこの戦略発想に基いて練り上げ、実行すべきでしょう。「数値計画に基く工程表を」という言葉がすぐに発せられますが、この要求は無視すべきでしょう。この理由を説明します。 池田内閣の所得倍増計画が国民の支持を容易に得られたのは、「欧米先進国がキャッチアップ目標になれた ⇒ 頂上を目指す尾根登りのようなことができた。いいかえれば、不確実性がないに等しかった ⇒ 目的達成のための手段(政策)を体系化できた。いいかえれば、計画経済が実質的に可能であった」のです。 アベノミクスを取り巻く環境は池田内閣の所得倍増計画時とは真逆です。こういう時は金言「企業経営で最重要なのは定性化困難事象を定性化することである」に忠実になり、多くの人が「魅力的だ。実現できそうだ。自分自身のこともイメージできる」と思えるような問題解決のシナリオを描くことです。 (関連記事 ⇒ 『解決すべき問題の体系的な理解が挑戦を可能にする / 経営計画は「立案手順の知悉」よりも「創造力」の方を遙かに必要とするようになった /斬新な枠外思考入手なくして各セクターの明日はない』)
日本を代表する経済学者による「1997年消費税引き上げ論評」が日本経済が陥っている実態を如実に物語っています。 「消費税の引き上げは財政再建のために必要不可欠。消費税引き上げ後は駆け込み需要の反動で消費が落ち込んだが、しばらくして元に戻った。これは消費税引き上げ時期とデフレ脱却は別々に考えなければならないことを意味する。デフレ脱却は金融政策によらなければならない」。しかしながら ─────
鋭い直観回路に基く果敢な行動力は一朝一夕では身につきません。安倍政権は2020年に基礎的財政収支の赤字をゼロにする目標を掲げていますが、高めの成長率が続いても10兆円ほどの赤字が残るそうです。したがって、過去の延長線上を歩む限り日本全体が夕張市のようになってしまいます。 どうすべきでしょうか? 「必需性の高い商品の市場が未成熟な開発途上国の市場を開拓する」「規制が開花を邪魔している国内需要を開拓する」ことです。しかしながら、これだけでは息切れしてしまいます。企業経営幹部が鋭い直観回路に基く果敢な行動力を身につけるための自助努力を促進しなければなりません。新創業研究所も微力を尽くします。→日本再生に結びつく新しいビジネスモデル開発を目指します 上記したことに関連して認識すべき大事なことがあります。「いわゆる専門家を安易に飛びついてはならない」がそうです。→いわゆる専門家を含む権威筋は様変わりした環境に適応できていない&著名エコノミスト達の誤判断「経済が成熟しているのに成長戦略は馬鹿げている」は陳腐化した枠内思考の所産である&有名だが視野狭小の医師達に振り回された少女の悲劇現象
日本は「(縦型社会の源である日本モデルが根づいている ⇒ 自由自在な人的交流がままならない ⇒ 国民は老害発生の仕組みに陥りやすい) + 成長力が豊かで労働コストが安い開発途上国が存在している ⇒ 市場成熟化と円高の直撃を受けて産業の空洞化が進んだ ⇒ 社会全体の雇用力が衰えるに至った」という図式の中に置かれています。 ここに、「国がセーフティネットを張る ⇒ 社長を含む雇用流動化促進に結びつく規制見直しを行う + TPP参加を初めとする自由貿易協定に国益を意識しつつ参加する ⇒ 競争が促進されてナアナアや癒着が許されなくなる ⇒ 国民を老害発生の仕組みから守ることに結びつくオープンリソース経営が進む ⇒ 実質的社会主義体制の悪影響からの脱却が進む」という図式の必要性があります。 (関連記事 ⇒ 『生き抜くために新しいライフスタイルが必要になる / 日本は人材ミスマッチ大国である /適切な断章取義(ジグソーパズル思考)力が永遠の成長を可能にする / 民間経済は中枢機能の麻痺が目立っている』)
日本人の税負担は相対的に低い。ところが、「政府には貧困の人を助ける責任がない」と考える日本人が38%いて、世界の中でトップ…といった具合に重税感が強い。税制の抜本的改革以前に検討すべきは、内需拡大並びに政治と行政に対する監視機能強化にも結びつく国民のぶら下がり体質是正です。(関連記事 ⇒ 『個人のパワー欠如は内需低迷にも結びついている』) 実質的社会主義体制が生み出したぶら下がり体質の是正は「自立と創造力の強化 ⇒ 人生の舵取り力強化 ⇒ 新市場創造に結びつく新事業開発の命である開発目標力強化」となることが期待できます。ぶら下がり体質が最終場面を想定した行動を採る習慣形成を困難にして、会社ごっこの如き開発行為を横行させることに結びついていることを忘れてはならないのです。→適切な開発目標設定が超難問の創造的解決を可能にした
単純な法人税引き下げは「世界経済の右肩上がりの困難化 ⇒ 国家主導の雇用力強化 ⇒ 法人税引き下げ合戦」の渦中に入るようなもの。しかも、法人税率と経済成長は相関しないという歴史的事実もあるとのこと。法人税引き下げの前に検討すべきは、地方自治体と企業の連携強化&成長の限界打破に結びつく社会横断的人的交流に結びつく地域主権の地方分権推進です。 (関連記事 ⇒ 『地域主権のうねりをフォローの風にしよう! / 適切な断章取義(ジグソーパズル思考)力が永遠の成長を可能にする / 全員参加型社会は紆余曲折が仮にあっても必ず実現に向かう』)
企業の投資促進策は必要だが、供給力過剰下での単純な投資減税はデフレを増幅するのみ。そこで、減価償却は企業が臨機応変に行えるようにする。と同時に新市場創造に結びつく新事業開発の場合のみに借金返済を先延ばしできるようにする。(関連記事 ⇒ 『世界金融危機の真相』) 企業経営幹部の鋭い直観回路に基く果敢な行動力が欠如したままでは法人税減税や設備投資減税は空回りすることを忘れてはならないのです。→複雑な問題を量的効率で対処しようとしたことが悲劇を招いた&深く潜在している豊かな新成長機会発掘に結びつく知恵入手を可能にする質問のポイント
消費税増税に伴う低所得者対策は、膨大な行政コストがかかる軽減税率採用などを止めて、仕事創りや脳力進化支援を行うようにする。(関連記事 ⇒ 『性格に振り回されていることが自分の潜在能力の殆どを未活用にしている)
国民を老害発生の仕組みから守ることに結びつくオープンリソース経営が進むにつれて人材の優勝劣敗が明確になり、仕事を「追う」のではなく「追われる」状態の人はストレスが溜まり続けて、人生を台無しにする“その場しのぎのなれの果て症候群”になります。 こうならないためには努力継続力入手を可能にする「適切で好きな道」を歩むようにしなければなりません。→適切で好きな道を歩むことが、増える一方の心因性うつ病の最善の予防・治療策である 製品・サービスのエンドレスなハイエンド化に結びつく脳力のエンドレスなハイエンド化を可能にする、企業人の努力継続力入手は、脱・旧習が困難な社長を含む雇用流動化と相まって賃金上昇に結びつく可能性が大です。「新成長機会は顕在化している ⇒ 労働力はコスト要因であった」から「新成長機会は深く潜在するようになった ⇒ 労働力は収益要因になった」からです。→鋭い直観回路が新成長機会ゲットの要諦だ&日本人の生き方の変遷と背景
深く潜在している豊富な新成長機会の発掘の成功は経済の高めの成長実現に結びつく。しかしながら、「基礎的財政収支ですら2020年に10兆円ほどの赤字が残る」という問題が解決しない限り世界に例のない累積赤字は膨らむばかりです。 一方、日本には由々しき実態「(日本的集団主義が根付いている ⇒ 日本人は理念で糾合しにくいので、ばらばらになりやすい ⇒ 縦型社会の源である日本モデルが根づいた ⇒ 個々人の自立と創造力を鍛えることが困難になった。鍛えることができても適切な枠外思考ができない) + 小さな物語の時代になった ⇒ 頼みの組織が硬直化して超然とした存在になっている」があります。 ここに、個々人の自立と創造力を鍛える原動力となる「適切で好きな道」を歩むことを誘導しつつ年金支出の大幅削減に結びつく、生涯現役社会を実現させる必要性があるのではないでしょうか。→絶好調を維持しながらの生涯現役の人生が可能である&80歳代に脳力のピークを迎える人生が送りやすくなった
▲トップ
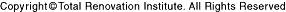 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)