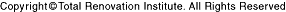![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
過去の歩みを生かす再出発を可能にする新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒311-1203 茨城県ひたちなか市平磯414-7 来客用駐車場があります ☎ 029-229-0225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(節子) 「戦後レジームからの脱却」の詳細な肉付けに基づいた緊急課題への対応が甘かった…という前回の貴方の発言にある緊急課題の中で一番大切な格差の拡大問題だけど、民主党は財源を具体的に示すことなくばら撒き政策のマニフェストを提起した。これは欺瞞であることについて国民は気づき始めている。政府が採るべき創造的対策としてどんなことが考えられるかしら? (高哉) 「
(節子) この状態を放置したままであると、共同体があったから生きることができた人々は経済成長の果実を手に入れることは永遠にできない。国民の生命と安全を守らなければならない政府は財界の言うことだけを聞いていては駄目ということね。だからと言って、再び大きな政府を志向すると、財政破綻が一気に進んでしまう。どうしたらいいのかしら? (高哉) 大都市と過疎化が進む地方社会の両方で有効な新・公共事業が考えられる。大都会の緊急を要する解決すべき問題はネットカフェ難民。地方から大都会に出てきた。しかし、仕事が見つからなかったり、住まいがないためにネットカフェ難民になってしまった人々にとって一番必要なのは住民登録して再起の準備を安心してできる住まい。そうでないと、「住所不定」ということで正規社員への道を閉ざされてしまう。 過疎化が進む地方社会の緊急を要する解決すべき問題は農業の後継者難。民主党がマニフェストで謳っている所得補償制度は隔靴掻痒の感がある。安定した収入が得られないために生活不安に悩まされている人々が農業従事者になるように誘導することを考えるべきだと思う。 大都会にも過疎化が進む地方社会にも廃校になった公立の学校がある。その上、過疎化が進む地方社会には空き家が沢山ある。こういう建物を有効利用して公共の住宅を超格安で提供できるんじゃないかなぁ。
(節子) 戦後レジームからの脱却のことで前回貴方が言ったことは日本が現在陥っている状態と日本が目指すべき状態の両方を踏まえて採るべき政策を明らかにすることよね。すると、日本が現在陥っている状態をまず明らかにしなければならない。リストアップするだけでは駄目よね。 (高哉) 「問題は山積するけど、根っこはたったひとつしかない」という考え方が何より必要だね。山積している問題を一体化した図解がなぜ必要か?で説明してあるように…。 (節子) 政治評論家の屋山さんが言っているように犯罪者や怠け者の巣窟化した社会保険庁、人口増を前提にした年金制度、もたれあいの構造そのものであるマンション耐震偽装事件、隠蔽体質の典型であった原子力発電所問題…等は日本的集団主義の悪影響の結果であるとして説明ができる。 したがって、 たったひとつの根っこは日本的集団主義よね。安倍さんはどうしてこんなことに気づかなかったのかしら? (高哉) 安倍さんだけを批判するのは酷だよ。デフレの本当の原因にあるようなマンネリ現象は日本の伝統的な組織にほぼ全面的に共通する現象なんだ。 (節子) マンネリ現象はどうして生まれるのかしら? これもやはり日本的集団主義に起因するのかしら? 日本的集団主義にどっぷり浸かった人生を送ると、メリハリのある思考をしなくなるからね。 (高哉) 出来事を自分に都合よく解釈したり、無視したりする習性が人間には元々ある。いいかえれば、人間は性格に振り回されれやすい。これがゼロベース発想を妨げることに結びつく。こういうことに起因していると思う。
(節子) 安倍首相が様変わりした環境に日本を適応させるために短期間で日本の基盤を強化してきた実績は高く評価できる。しかし、具体的問題と結びつけた戦後レジームからの脱却の説明がなかった。その結果が大きな原因となって7・29参院選惨敗に結びついてしまった。どうしてこうなってしまったのかしら? (高哉) 小泉改革の継承者として総裁・総理になった。しかし、改革の翳の部分に気づいているし、自身は共同体尊重者。そこで、 「犠牲を少なくしつつ改革を推進するためには長期展望に立った対策を講じるしかない」となり、戦後レジームからの脱却を打ち出し、憲法改正・教育改革・行政改革…に熱心になったんだと思う。 (節子) 安倍首相路線は創造的であることは認める。しかし、具体的問題と結びつけた戦後レジームからの脱却の説明が欠落してしまったのは事実。どうしてこうなってしまったのかしら? 「望遠鏡を覗いて政治をしているようだ」とまで言われてしまったのよ。「お友達内閣だ」「人の意見に耳を貸さない」と言われていることに原因があるんじゃないかしら? (高哉) その通りだけど、選挙民の情報の質・量が不足していたことの方がより根源的なんじゃないかな。この背景には次の三つの図式が示していることがあると思う。
(節子) 「犠牲を少なくしつつ改革を推進するためには長期展望に立った対策を講じるしかない」となり、戦後レジームからの脱却を打ち出した。しかし、具体的問題と結びつけた理論武装がなければ、経済諮問会議が中途半端に終わったのは当たり前よね。 話は変わるけど、安倍首相の性格がなんとなく分かったような気がする。安倍さんは「和と共存の実現を目標に他人の支配を受けずにしっかりやろう!」という人のようね。判断情報が少なすぎるのであくまでも仮説で直感でしかないけど…。 (高哉) 僕も判断情報が少ないので断定はできないけど、同感だ。自他が融合できるような人間関係を大事にする。これを付け加える必要があるかもしれない。 和と共存を大事にする人は痛みを伴う改革は断行しにくい。しかし、改革をしないと日本は破産してしまい、和と共存は不可能となってしまう。だから、安倍さんは痛みの少ない改革を実現させるために、戦後レジームからの脱却の財源にすることをも狙って経済の成長戦略を打ち出したんだと思う。 しかし、社長力の抜本的強化や個人のパワーアップが遅れたままグローバリゼーションが進展したために共同体が崩壊してしまった。となれば、経済成長を一般の人や過疎化に悩む地方社会が実感できるようにはなりにくい。こういうジレンマがあったので、地球環境問題に取り組んだのかもしれない。というのは、次の図式の実現が期待できるからね。 地球再生の努力をする ⇒ 日本が世界に誇るクリーン・テクノロジーを世界中に売ることができる ⇒ 開発途上国の経済開発が進めやすくなる ⇒ 日本の持続的な経済成長がしやすくなる ⇒ 痛みの少ない改革を進めやすくなる。 (節子) 貴方が提唱し、実践している創造的統合戦略がジレンマを解決するのに最も有効な手段なのにどうして気が付かないのかしら? (高哉) 創造的統合戦略とは無縁になっているのは何も安倍さんだけではない。その場しのぎの体質が染み付いている日本人全般に言えることだよ。この背景には日本的集団主義が生み出したその場しのぎ体質がある。 (節子) 安倍首相が陥ってしまっている状態を「人の意見に耳を貸さない」という評判の原因分析をも意識して図式化すると、次のようになりそう。 改革は必要不可欠。しかし、犠牲者は出したくない。様々な意見を持った人がいる自民党内のとりまとめは経験不足者にとっては容易ではない ⇒ 「和と共存を実現しなければ」と気が焦る ⇒ 「他人の支配を受けずにしっかりやろう!」に基づく行動が円滑さを欠いてしまい、時には強引に、時には問題先送りとなってしまう ⇒ 自他が融合できるような人間関係ができずストレスがたまる ⇒ ストレスを解消したり、ストレスがたまらないようにするために心地よい人との付き合いについつい偏ってしまう。 このように述べた自分が言うのは変だけど、最初からお仲間志向に走ってしまったのはどうしてなのかしら? (高哉) 和と共存を大事にする。自他が融合できるような人間関係を大事にする。この二つが重なれば、最初からお仲間志向に走るのは当然のことじゃないかな。 安倍さんは自分の性格をきちっと認識してないことが他の悪しき現象をも生み出している。いいかえれば、性格に振り回された結果が諸々の失敗に結びついてしまったと言えるんじゃないかな。 (節子) 自殺した松永元農林水産大臣は性格に振り回された安倍首相の犠牲になったのかしら? 世間では「安倍首相の決断がなかったために、松永元農林水産大臣は追い込まれて自殺してしまったのだ」という評価は正しいのかしら? (高哉) 松永さんが緑資源機構関連の汚職に関わっていなければ、世間の評価通りだと思う。関わっているのであれば、世間の評価は間違っていると思う。 松永さんは他人の支配を絶対に受けたくない。心理的にも…。したがって、他人の支配を受けざるを得ない状態になりそうだったら、そうなる前にそうならないように自ら決着をつける人だと思う。離婚になりそうだったら、自分の方から離婚を申し出るといった具合に…。 この誤解は日本の社会全体に警鐘を鳴らしていると受け止める必要がある。というのは、「日本は気が遠くなるほど長い間個性を抑圧してきた ⇒ 個性的な人はほとんどいない。いると排除される ⇒ 人間を十羽一絡げに扱ってきた」という図式に陥っていることを猛反省しなければならない。さもないと、とんでもない誤解を生み、この誤解が社会全体を不幸に陥れることになってしまうからだ。
(節子) 参院選大敗北後の人事で麻生幹事長と与謝野官房長官を登用したことに対して「安倍さんは党内運営は麻生さんに、内閣の運営は与謝野さんに丸投げ。これでは安倍色は出しくい。なんのための続投なのかさっぱり分からない」と超有名な政治評論から酷評されている。これをどう受け止めたらいいのかしら? (高哉) その酷評は間違っている。麻生幹事長と与謝野官房長官の登用は安倍さんの持ち味発揮に結びつく可能性が大きい気がする。というのは、次の図式が実現するかもしれないからだ。 麻生幹事長が党内を与謝野官房長官を内閣を取り仕切る。いいかえれば、二人に大幅の権限を委譲する ⇒ 安倍首相は戦後レジーム脱却策の練り上げ・実行に費やせる時間とエネルギーが大幅に増える ⇒ 安倍首相の持ち味であると思われるレフリー機能が強化される ⇒ 安倍首相の国政全般の掌握力が強化される。 (節子) この二人の登用は安倍首相のトップダウン力の強化ではなく持ち味を発揮しやすくすることが狙いなのね。そうだとすると、首相補佐官を大幅に縮小したことに納得できる。でも、「与謝野官房長官が内閣を取り仕切る ⇒ 竹中路線から撤退する ⇒ 小泉構造改革が中断され、国政のあり方が逆戻りする」という図式のことが盛んに言われるようになっているけど、これをどう受け止めたらいいのかしら? (高哉) 竹中元総務大臣や有名な評論家達が盛んにそういうことを言っているけど、斬新な着眼の欠落が生み出した間違いだ。竹中元総務大臣の政策を次のように評価できる。 癒着は新しい伸びる力を封じ込めることに結びつく。したがって、癒着を排除する市場原理の追求は正しい。しかしながら、アメリカ型の市場原理の追及は現状においては好ましくない。主な理由は二つある。 (理由1) 日本人を改革に誘導するためには内生変数を重視しなければならない場合が多い。そうでないと、「笛吹けど踊らず」という組織の宿命に遭いがちとなる。(詳しくは ⇒『米国の宿命的な体質である“外生変数重視主義”とは何なのか? どうしてこのような体質になったのか?』) (理由2) 日本経済活性化のためには「工業化が限界に達しているために収穫逓減の法則が働く蛸壺型の社会構造」から「永遠の経済成長を可能にする秘訣にあるように収穫逓増の法則が働きやすい、人々の相互依存の輪が広がるネットワーク型の社会構造」に転換しなければならない。人々の相互依存の輪が広がるためには、日本社会に伝統的に根づいていた思いやりの心が必要である。 (節子) 思いやりの心を人々の相互依存の輪の拡大に確実に結びつけるためには、次の図式を実現させなければならないわね。 お互いに「好きこそ物の上手なれ」の世界に入る ⇒ 棲み分けが円滑に行われるようになる ⇒ お互いに「好きこそ物の上手なれ」の世界が円滑に広がる ⇒ 生涯現役が可能になる ⇒ 製品・サービスのハイエンド化が数学者の例が暗示しているように限りなく進む ⇒ 財政再建が進む。 このように整理して頭の中がすっきりした。癒着打破のためには改革は必要不可欠。しかし、アメリカ式ではなく日本式のやり方が必要不可欠なのよね。 (高哉) 全くその通り。だから、 お互いに「好きこそ物の上手なれ」の世界に入ることを確実にする、個性的才能を引き出す性格診断が必要不可欠になるというわけだ。
(節子) 安倍首相の性格の影響を展望するとどういうことが言えるのかしら? お亡くなりになったミヤコ蝶々さんと似ているところがありそうなので、追い込まれて立場が自由になると、俄然パワーフルになる可能性があると思うんだけど…。 (高哉) それって当たっているかもしれない。というのは、次の図式実現が考えられなくもないからだ。 民主党が対決路線を歩み、国政調査権を使ったりする ⇒ 自民党が絶体絶命のピンチに陥る + 自民党内の反改革派が力を失う ⇒ 和と共存を実現しやすくなる ⇒ 「他人の支配を受けずにしっかりやろう!」に基づく行動が円滑になる ⇒ 自他が融合できるような人間関係を大事にする想いが実現しやすくなる。 但し、仲良しクラブは適切な判断を下すことを妨げることに結びついたことを反省して、大事を決断・決行する前に徹底的な議論をするために、「思考の三原則」(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える)を適用できる人物を幅広く探索・抜擢すべきだろうね。但し、常時オーラを発することができるようにビジョン効果を入手しなければならない。 (節子) その徹底的な議論のポイントはなんなのかしら? それをしっかり示さないと、「今更言われなくてもやってますよ。私の周りには優秀な人材が揃っているし…」ということになってしまうわよ。 (高哉) 安倍さんが和と共存を実現させようとする際の盲点を少なくすることがポイントになる。例えば、さっき指摘したことだけど、グローバリゼーションによって崩壊した共同体を放置したままの状態では「地球再生のための努力をする ⇒ 持続的な経済成長が可能になる ⇒ 痛みの少ない改革が可能になる」という図式は成立しないことを認識させる…とかが考えられる。 安倍さんの政策はシステマティックだけど、詰めが甘い。実にもったいない。こういう詰めは周りの者がしなければならないのだが、党内にも個人的な人脈にもそういうことができる人材がいないんじゃないかな。 これもさっき言ったことだけど、デフレの本当の原因にあるようなマンネリ現象は日本の伝統的な組織にほぼ全面的に共通する現象について真剣に考える必要があると思う。 (節子) 若い安倍首相が目指すべき指導者像は何かしら? 勿論性格を考慮してだけど…。 (高哉) 和と共存を大事にする。自他が融合できるような人間関係を大事にする。この二つを大前提に他人の支配を受けずにしっかりやりたい。── こういう性格の持ち主であるとすれば、御祖父の故・岸元首相ではなく、アメリカの故・レーガン元大統領ではないかという気がしてならない。だから、「持ち味はレフリー役」とさっき言ったんだけど…。故・レーガン元大統領のような人物像を確立できれば、政界再編成を乗り越えて長期政権を実現する可能性ですらあるんじゃないかな。
(節子) 成長戦略は良かったんだけど、共同体が崩壊したままだと経済成長の果実を国民に幅広く行き渡せることができない。こういう盲点を極力少なくするために優れた参謀が必要である。この主張は説得力があるけど、分からないことがあるの。小泉前首相も外交上のの失敗とか盲点が結構あったと思う。にもかかわらず、5年以上の長期政権になったのはどうしてかしら? (高哉) 小泉さんが政権を担っていた時は不良債権問題の解決とか郵政民営化といったようなことに乾坤一擲の努力を払うことができた。ところが、安倍さんの場合はそうはいかなかった。改革を一層進めなければならない。しかし、格差が広がっているので改革は進めにくい。前にも行ったようにこういうジレンマに悩まされていたんだ。 (節子) 典型的な立ち往生状態ね。創造的統合戦略の出番だったけど、貴方がさっき言ったように日本的集団主義が災いしてこういうことに気づきにくかった。これは理解できるけど、安倍首相はどうしてもっとどっしり構えていることができなかったのかしら? アメリカを襲った9・11同時多発テロ事件の時、日本の政治家の中で一番泰然自若としていたというじゃないの。 (高哉) さっき言ったジレンマの円滑な解決策が思い浮かばなかったことが次の図式を実現させてしまったからではないかと思う。 和と共存を求めようという想いが強迫観念になってしまった ⇒ 「しっかりやろう!」とい思ってもなかなかうまくいかない ⇒ ストレスが溜まってしまった ⇒ ストレスを解決するために強引な行動を採ることになってしまった。 (節子) だから国会運営が乱暴になってしまったのね。でも、強引になってしまった人が一方において問題を引き起こした閣僚の責任追及が甘かったじゃないの。どうしてなのかしら? (高哉) 安倍さんのような性格の持ち主は人事において次の図式に嵌りやすい。だからだと思う。 (人間関係において融合志向が強い ⇒ 相手を理想化しやすい ⇒ 相手が何かをしでかしてもついつい楽観的に考えてしまう) + (他人から支配されることを極度に嫌う ⇒ 問題閣僚の解任要求をはねつけたがる) ⇒ 問題を先送りしてしまう。 (節子) 国民を糾合できる創造的統合戦略を提起する ⇒ 政策面でのジレンマ解決が可能になる + (求心力が生まれる ⇒ 融合強迫観念がなくなる ⇒ 人事における冷静な判断ができるようになる──、という図式の実現が根本的な解決策となるわけね。 (高哉) その通りだけど、日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた人に今言った図式の実現を迫るのは酷。安倍さんと言えども例外ではない。だから、適切な参謀の登用を主張したわけだよ。そうすれば、どんな状況になっても安倍さんは泰然自若とした態度を採り続けることができるようになるだろうね。
(節子) 「安倍首相は適切な参謀を登用すべし」という勧告は当たっているわね。遠藤前農水大臣が就任早々に政治と金の問題で辞任に追い込まれてしまった。それだけではなく、政治資金問題を抱えている閣僚や党三役がいることが新たに分かった。このことは泰然自若とした態度はまだ身についていいないことを意味するんだから。でも、本当にだらしがない。「マネジメント能力に問題がある」という批判は当たっているわね。 (高哉) ある評論家が言っていた「大臣に就任したら政治と金の問題で辞任に追い込まれてしまう人が沢山いることは与党、野党を問わない」は日本の政治家の体質をずばり突いているんじゃないかな。どうしてかと言うと、中央官庁と国民の間に立つ、特定の団体に利益を誘導するブローカー業が政治家の実態であることが実に長いこと続いてきた。政策立案能力をバックに国家・国民のためには働いている人は例外的存在なんだ。 (節子) 「多少ダーティーな面はあるけど、ずば抜け能力の持ち主。したがって、国民にとってプラスの方が遥かに大きい。こういう政治家は今のようなヒステリックな国民感情だと出てこないんじゃないか」という一部国民の意見をどう受け止めたらいいのかしら? (高哉) そういう意見は普通の時だったら通用する。しかし、今は通用しにくい。というのは、国全体が夕張市のような財政状態になっているので、増税の前に税金の無駄遣いを一切排除しなければならない。さもなくば、国民の負担増を要求できないからだ。 (節子) しかし、遠藤前大臣の問題について「蚊に刺されたようなもんだ」という有力国会議員の発言が示すように事態の深刻さに対する認識が十分ではないのは、マンネリ現象そのもの。どうしてこうなってしまっているのかしら? (高哉) 中央官庁と国民の間に立つブローカーが多くの政治家の実態であったので、ブローカーとしての報酬として賄賂を受けるのが常識であった。こういうことが超長期に亘って続いてきたので、一定のリズムに乗って行動するという文明人の傾向に拍車がかかってしまったからだと思う。 (節子) 習慣病ね。しかし、染み付いた習慣から脱出するのは容易ではない。となると、次の図式の道に入るしかないわね。 自分の性格と由来をきちっと認識する ⇒ 刺激に対して自動的に反応しそうになると、「性格に振り回されそうになっているな」と気づく ⇒ 「良くなりたい」という本能が働き、刺激に対して自動的に反応するのを止めて現実をしっかり直視する。 (高哉) そうそう。その図式の実現を支援するのがヒステリックな国民感情だとも言える。政治と金の問題での過剰反応は、細かい所に神経が行き過ぎて大局観、ひいては斬新な着眼を失いがちな日本人らしい対応だと思う。でも、次の図式が実現しやすくなるというメリットもあるからね。 政治家が賄賂を受け取らなくなる ⇒ 国民は賄賂を使って利益誘導を図ることをしなくなる ⇒ 政策立案能力をバックに国家・国民のために働く能力のない候補者は当選しなくなる ⇒ 政治屋から政治家への転換が実現する。 (節子) となると、国民もぼやぼやしていられなくなるわね。自分の利益実現のためには実力をつけなくてはならなくなるんだから。 (高哉) 実力とは臨機応変力。したがって、「自分の性格と由来をきちっと認識する ⇒ 性格に振り回されないようになるする ⇒ 現実直視力の強化が進む ⇒ 創造的問題解決能力の強化が進む」という図式実現の必要性に迫られることになることを忘れてはならない。
上記の文章における安倍元首相の性格診断には若干甘いところがあります。そこで、『 ポジショニング手法の適用を怠った→新しい立場の覚悟が不十分になった→臨機応変力を再構築しなかった→政権を投げ出すに至った…となった安倍元首相』を用意することになりました。内容がごく一部重複しますが、必ず役に立つはずです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||