【斬新な着眼】(1) あのイラク再生は成功する(難問題解決の糸口探索編)
ある集団に致命的な攻撃が行われたとしましょう。この攻撃を行った集団が特定できれば、人望のあるリーダー同士が話し合いをすることにより事態の収拾は可能です。ところが、この攻撃を行った集団を特定できなければ、「お互いに疑心暗鬼となる ⇒ お互いに攻撃しあう ⇒ 社会あるいは組織全体が大混乱に陥って事態の収拾が困難になる」という図式になりかねません。 上記図式の状態に陥りかけている。いいかえれば、内戦状態に突入しかけているのがイラクです。このように判断する根拠は大きく分けて三つあります。 (根拠1) 内戦の因子が元々存在している。 イラクは紛争の当事者になっている勢力が多数あり、勢力同士の友好・敵対関係が変わりやすい。 (根拠2) 内戦の因子がとうとう顕在化した。 昨年8月に中部の聖地ナジャフでイスラム教シーア派指導者ら80人以上がテロで殺害。今年1月31日にイラク北部のクルド人地区の主要都市アルビルで自爆テロが起きて、二つのクルド人政党事務所がほぼ同時に爆破され、60人以上が死亡した。このイラク人同士の殺戮は、 「自分たちの防衛を優先させなければならない」ということでイラクの各軍閥の分派性を強めている + 国連を怖気づけさせている ⇒ イラク統合は遠のき、内戦の火種がくすぶる──、という図式に結びつくこととなった。 (根拠3) テロ攻撃の抑制は不可能に近い。 上記のクルド人攻撃を受けて、クルド人指導者たちは、アルカイダやイラク国内のイスラム過激派組織による犯行の可能性を示唆しているが、いずれにせよ、イラクが内戦状態の気配を見せ始めたことは攻撃側の思うつぼかもしれません。なぜなら、 「攻撃する側は、財政的にも政治的にも米英が占領を続けらなくなるまで、地道なゲリラ活動を続ける覚悟のようだ」「イラク国内には資金と武器が大量に隠されている」という専門家の指摘もあるからです。しかも、 「市民の足」であるために止めようがない。ドライバーが命令を記憶できる。 ── この二つの特徴を持っているタクシーを用いて資金や武器の運搬を行っているとのことです。 アルカイダやイラク国内のイスラム過激派組織が関与しているとすれば、彼らのデスマッチ的な闘いの激しさは増すことでしょう。なぜなら、バグダッドの米軍キャンプの数は60から26に減り、いずれ8になることが予想されているからです。例えて言えば、遥か遠くを走っていたマラソンのトップランナーの背中がどんどん近づいてきたようなものなのです。 したがって、「治安が極度に悪い + サボタージュがある ⇒ 電力施設・原油生産設備等の復興工事が順調に進まない ⇒ 電力不足・ガソリン不足・通信困難の事態に陥ったままである ⇒ 電力施設・原油生産設備等の復興工事が順調に進まない・・・・・」という悪循環が収まらず、緊急課題である雇用拡大を困難にしたままのようです。
優秀な兄弟が長期に亘って社長と副社長を勤めていた企業がいつの間にか倒産の危機を迎えました。どうしてでしょうか? 失敗の潜在要因があるところに失敗の顕在要因が発生したからです。 (失敗の潜在要因) この兄弟経営者は毎晩酒を飲み交わしながら意見交換をしますので、経営体制は磐石でした。したがって、他の経営幹部以下の社員は“指示待ち族”になるしかありませんでした。いいかえれば、後継者が育たない企業になりました。 (失敗の顕在要因) この兄弟経営者は経営に関する異論を耳目することがなくなったので、成功方程式の固定化が進みました。ところが、この固定化された成功方程式が通用しない経営環境が到来。市場が成熟化し、競争が激化したのです。したがって、ヒット商品が生まれなくなってしまいました。 以上の例からお分り頂けましたように、異常現象の背景には「潜在要因」と「顕在要因」があるのです。「気管支が生来弱い(潜在要因) + 過労が続いた(顕在要因) ⇒ 風邪をこじらせて肺炎になった(異常現象)」という図式も同じことです。 イラクの異常現象(内戦の気配を呈し始めたために、失業問題は深刻さを増している)の背景にも「潜在要因」と「顕在要因」があることは間違いありません。
元々根づいている反米感情、宗教的な狂信主義への走りやすさ、米国の宿命的な体質である“外生変数重視主義” ── この三つが潜在要因になっていると言えそうです。
文明的に相容れないものがある上に、イラク国民は米国に裏切られたことがあります。前ブッシュ大統領時代の湾岸戦争時にフセイン大統領打倒の軍事行動が起きたにもかかわらず、米国はこれを支持しなかったために、反乱軍は悲惨な目に遭ったのです。しかも、イラク人の多くは「イラク戦争には大義がない」と思い込んでいるからなのです。 (文明についての理解は人様々なところがありますので、筆者の考えを紹介します。個人的な工夫や習慣を見て、「いいなあ」と思い、真似しやすいようにしたのが文化。この文化が国や広い地域に広がって根づいたのが文明であると理解しているのです) 英『スペクテーター』誌のイラク人に対して行った世論調査によると、「石油利権のため・・・47%」「イスラエルの安全保障のため・・・41%」「大量破壊兵器を廃棄するため・・・6%」となっているのです。
フセイン元大統領の強権的政治が長期に亘って続いたイラクには議会民主主義は根づきようがありませんでした。したがって、親米派、反米派、自由主義者、イスラーム主義者のいずれも自分の議論を掲げることばかりに忙しく、議論を政治舞台の上で調整・組織化していくことに関心を示そうとしません。 こういう状態であっても、年老いた人が多ければ、穏健な行動が期待できます。ところが、イラクでは、20歳代の若者が多いので、「暴発しやい + 旧秩序が崩壊したままであるので、信じられるのはイスラム教しかない ⇒ イスラム過激派的な行動を採りがちとなる」という図式になってしまうからなのです。
改革対象の内面の変革を先行させるのではなく、置かれる環境を変えることを優先させる。これがここで言うところの“外生変数重視主義”です。したがって、環境が様変わりすると、米国人は環境変化を受け入れてから自らを変革させる…という行動を採りがちなのです。 この“外生変数重視主義”の由来を様変わりした環境への対処の仕方で日本と比較すると、次のようになるのではないかと思われます。 (日本) 自然発生的に国ができあがった ⇒ 既存の人間関係を重視しなければならない ⇒ 個々の人間の感情・情緒を重視しなければならない──、というプロセスを経て、「様変わりした環境を受け入れる前に個々の内面的な変革を優先させなければならない」という習慣ができあがった。 日本の改革が遅々している背景には上記の図式があるのです。いいかえれば、日本は創造と破壊を同時に行うことが困難な社会なのです。 この状態は現段階では遠い昔も今も変わっていません。 『坂本竜馬』を読んで、「日本は今も幕末も同じなのね。駄目な国なのね」と言う人が多いことが何よりの証拠です。 「だから…」と言って諦める必要はまったくありません。“人を見て法を説く”ようなやり方で一人一人のやる気を引き出す“内生変数重視主義”を採用すればよいのです。交渉相手の性格と歴史的立場を見抜き、これを強く刺激する動機づけをすることが行動期待値を引き出す要諦なのです。(関連記事 ⇒ 『性格発衝動脅迫 / ワタナベ式問題解決へのアプローチ』) (米国) 人工的に国ができあがった ⇒ 既存の人間関係重視の必要性はそもそもなかった ⇒ 個々の人間の感情・情緒を重視する必要性はほとんどない──、というプロセスを経て、「様変わりした環境を受け入れてから個々の内面を変革させる」という習慣ができあがった。 米国はスピーディーに改革を進めやすい。いいかえれば、米国は創造と破壊を同時に行いやすい社会なのです。
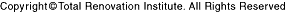 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)