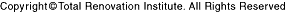![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528 FAX: 03-3773-6082 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人の羽ばたき支援のための日本の国策はどうあるべきか?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト発注者募集の背景 |
唐突な話題で恐縮ですが、日本が第二次世界大戦に突入し敗戦に至ったのはどうしてなのでしょうか? 主な理由は三つあります。
(理由1) 第一次世界大戦後、世界は「列強による世界市場の分割」から「世界市場の統合」に向った。このようにメガトレンドが一変したにもかかわらず、日本は大東亜共和圏構想をぶち上げて、世界市場統合に舵を取りつつあったアメリカ並びにドイツとイタリアを除くヨーロッパ主要国と対立することとなった。いいかえれば、時代認識が甘かった。
(理由2) 日本の軍事力とその背景にある国力はアメリカ等と比べると遥かに劣っており、ドイツとイタリア両国の協力があっても、その差は極めて大きかった。にもかかわらず、真珠湾攻撃を契機に世界大戦に突入した。いいかえれば、自分の力を客観視できなかった。
(理由3) 陸軍と海軍の対立を収めるための創造的コンセンサスを行うことなく、双方の意見を足し合わせてアメリカと旧ソ連を同時に主戦相手とすることになった。いいかえれば、総花的な対策・行動を採ることとなった。
企業等の組織に所属されている皆さんは上記「三つの理由」をお読みになって、「日本の組織運営の実態は昔も今も変わっていないなぁ」と思われたことでしょう。私共流に言うと、日本の社会には昔も今も創造的統合戦略がぽっかりと抜け落ちているのです。どうしてこうなってしまっているのでしょうか? 三つの体質が日本の社会に根づいているからなのです。
(体質1) 世の中の動向を幅広く学問して、ジクソーパズル思考をすることを軽視する。
(体質2) 減点主義の下で生き残った者がリーダーになる。したがって、組織のトップには本当の意味でのリーダーシップが期待できない場合が多い。
(体質3) 皆で渡れば赤信号でも怖くない。この言葉に象徴されるように横並び志向が強い。
上記「三つの体質」はどのようにして根づくことになったのでしょうか? 模倣や「カイゼン」で事足りた時代が古代からごく最近まで…延々と続いてきたことに根本的原因があるのです。なぜなら、このことが
枠外思考抑制を目的とする減点主義が社会全体に根づき、横並び志向がはびこることとなった ⇒ 構想力・独創力を駆使してリスクを背負うのではなく組織内の和を重視する“組織内遊泳術”がパワーゲームにおける成功の鍵となった ⇒ 世の中の動向を幅広く学問して、ジクソーパズル思考をする必要性は生まれようがなかった──、という図式に結びついたからです。
そして、時代が様変わりして、模倣や「カイゼン」が通用しにくくなりました。世の中の動向を幅広く学問して、ジクソーパズル思考をする必要性が生まれたのです。
したがって、日本の社会に真に求められているのは、この必要性に応えられるように社会全体の仕組み・運営の仕方を変革することです。それではどのようにして変革を進めたらよいでしょうか?
日本は自然発生的に生まれた国である ⇒ 既存の人間関係を重視しなければならない ⇒ 個々の人間の感情・情緒を重視しなければならない ⇒ 様変わりした環境を受け入れる前に個々の内面的な変革を優先させなければならない ──、という図式に縛られがちであることを念頭に置かなければなりません。
様変わりした環境を受け入れてから個々の内面を変革させる、アメリカ方式は日本の社会には通用しにくいのです。したがって、日本の社会を様変わりした環境に適応できるように変革させるためには、日本人一人一人が自然に羽ばたけるようにすることを優先させなければなりません。ここに、このページのタイトルである『個人の羽ばたき支援のための日本の国策はどうあるべきか?』の意義があるのです。
| プロジェクト受注者の義務 |
調査研究を行う ⇒ 提案書を作成する ⇒ 提案書に基づく質疑応答会を行う ── この3ステップをプロジェクト受注者の義務にしたい、と考えています。(プロジェクト発注者が別の意向をお持ちの場合は提供するサービスのあり方の変更を検討させて頂きます)
上記「提案書」の目次仮説は下記の通りです。(プロジェクト発注者が別の意向をお持ちの場合は目次仮説の変更を検討させて頂きます) ── リンクがかかっている箇所は完成されたものではありませんが、私共の思想や能力を判断する資料としてお使いください。
第1部 わが国の現状認識
| 政府は超然として漂っている | ||
| 民間経済は優れた要素を生かせていない | ||
| 個人のパワーが大幅に不足している |
表面化している問題をただ単に捉えるだけではなく、深く潜在している根本的問題を鋭く抉り出すことによって、「受注したプロジェクト遂行者の問題意識を適切にする」「後続の成果を適切に判断する評価眼をプロジェクト発注者に養って頂く」 ── の二つを実現させることが目的なのです。(現象のみに振り回されることの怖さ ⇒『有名な医者達に翻弄された少女の悲劇』)
第2部 一点突破改革案の分析
| 「嫌老社会」から「好老社会」へ | ||
| 年俸1500万円、「実力教師」を作れ | ||
| 「はないちもんめ型」官僚統制法 | ||
| 「平成基礎科学財団」の設立を | ||
| 「どこでもコンピューター」革命 | ||
| 2008年に「日本連邦」実現 | ||
| 「相続税100%」で介護充実 | ||
| 対金正日に「国軍」を整備せよ | ||
| 「平成徳政令」150兆円を実施 | ||
| 「子供に我慢力」を植えつけよう |
部分最適と全体最適を整合させた提案書が理想です。しかしながら、最初から全体最適を意識することは妥協精神が働いてしまい、提案内容が鋭角不足になってしまいます。そこで、、「文芸春秋」(2003年8月号)の小論集『日本が変わる 一点突破宣言』の分析を行うこととしました。
鋭い部分最適志向の提言に接すると、全体最適のことを考えなければならない立場の人は「抵抗感を覚える ⇒ 部分最適志向が生み出す鋭い提言を否定してしまう」となりがちです。でも、心配ご無用です。なぜなら、「第1部 わが国の現状認識が予めインプットされている ⇒ 部分最適志向が生み出す鋭い提言を前向きに受け止めることを可能にする大きな器量ができあがっている」という図式が実現されているからです。
第3部 行動のあるべき方向の認識
| アジア経済の一体化が不可避となる |
| 1 | 世界的な地域主義が不可避となる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (理由1) 地球環境の回復に役立つから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (理由2) 文明の衝突回避に役立つから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (理由3) 世界経済の統合を妨げないから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(理由4) 米国の赤字がプラス要因になるから
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (理由5) 持続力ある開発が可能になるから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (理由6) 中国の民主化が加速するから |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 米国とエネルギーがアジアの一体化を迫る |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日本はアジアにとって安心できる存在になる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 念願の環日本海経済圏が大きく開花する |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ASEANの共同市場化は不可避である |
※「(1)あのイラク再生は成功する」のブッシュ政権の新創業可能性分析まで私共の思想や能力を判断する資料提供を予定しています。
| ネットワーク効果が生まれやすくなる |
| 1 | オルガナイザーが政治家の活路になる |
|||||
| 2 | 循環型経済が地域社会の活路になる |
|||||
| 3 | ネットワーク型社会への転換が進む |
|||||
| 4 | 内需が継続的に拡大する条件が整う |
不可逆的に様変わりしつつある環境動向を全方位的に洞察する ⇒ どういう発想・行動の転換がなぜ必要なのかを具体的、かつ理路整然と認識することが目的です。この作業を効果的に行うためには、強烈な問題意識が必要不可欠です。だからこその、「第1部 わが国の現状認識」並びに「第2部 一点突破改革案の分析」があるのです。
第4部 個人の羽ばたき支援のための日本の創造的統合戦略
「日本人一人一人が羽ばたく状態」「その結果が生み出す社会全体の効用」の二つの目標を設定する。設定した二つの目標実現の障害を明らかにする。障害除去のために日本政府に求められる創造的統合戦略を策定する。── この3種類を図解して提起します。
図解の目的は、目標・目標実現の障害・障害除去策のいずれをもばらばらではなく一体的に捉えることにあります。(図解のイメージ ⇒『東京一極集中が消費拡大を困難にしている仕組み』&『大型事業の独創的構想(例)』&『豊田市地域商業近代化ビジョン』の一部である『実施手順と主体者の割り当て』)
| ● | 個人の羽ばたきの必要性・実現策の仮説(現段階) ⇒記念講演「どうしたら羽ばたけるようになるか?」(講演の録音結果を無償で聴取・ダウンロードできます) |
| プロジェクトの進め方並びに費用 |
プロジェクトの発注希望者と私共の話し合いにより決めさせて頂きます。
|
「創造的問題解決策のあり方の本質は個人・企業・地方経済・国家の各セクター共通である」という私共の古くからの考え方に立って、立ち往生している日本経済を題材に大筋に焦点を絞った事例研究を行うという考え方に立って、
2003年9月21日から開始した『ボトムアップとトップダウンを融合させて企業を再生させよう! ── 「一点突破改革案の募集 ⇒ 断章取義 ⇒ 創造的統合戦略の策定」の具体例』の連載は前述の目次にある「(1) あのイラク再生は成功する」の完了をもって打ち切らさせて頂きます。この決断の背景には、
限られた時間を効果的に使うためには、「身近なテーマを臨機応変に選定する ⇒ 新創業を適切に行えるようになるためのヒントを提供する」という行動が必要であるという考えがあります。
タイムリーではないと数多くの読者の興味を引くことが困難になる。テーマがマクロ的であったり、多岐に亘ると読者の理解が困難になる。 ── この二つを私共は連載を通じて学習したのです。連載中止をご了承くださいますようお願いします。
| 〔渡辺高哉が用いる手法の効用〕 | 〔渡辺高哉の特技活用例〕 |
|
|
|
|