![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528 FAX: 03-3773-6082 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【斬新な着眼】
日本の教育界が荒廃しきっているのは、教育の現場は聖域であるので教師間の競争を排除しなければならない…という考え方が支配的であるために、 教員の生活水準を守ることを第一義とする日教組が磐石化してしまった⇒すべての努力は教師任せ。努力しようがしまいが給与格差なし⇒目立たず挑戦をしない人間がいい目を見る⇒教師として必要な、人間性・高度のコミュニケーション能力・元気を生徒に与える心身の健康さがおざなりにされることになってしまった⇒有能な人材は教育界を敬遠しがちとなっている⇒荒廃した教育の建て直しは進みようがない──、という図式が実現しているからである。
荒廃しきっている日本の教育界を立て直すために、教師の優秀劣敗が明確になるようにする。 そのために、「予備校のように子供と親が教師を選択して実力給にする」「親が教師の実力を見極めることができるように授業をオープンにする」「品川区が導入した学校選択制を普及させる」の三つからなるポリシー・ミックスを実施して、
という具合に持っていく。
荒廃した教育の建て直しは進みようがない…という状態になってしまったのはどうしてなのでしょうか? 偏狭な日教組が牙城化してしまったからです。その背景には二つの図式があります。
日本の教育界が荒廃しきったままである背景には深刻なものがあるのです。しかしながら、上記のように原因の原因の解明努力によって、抜本的打開策がイメージできたのではないでしょうか?
目的があって始めて手段の選択が行われる。これが道理です。それでは教育建て直しの目的は何でしょうか?
日本経済再生のために必要不可欠な新産業創出が遅々としています。どうしてなのでしょうか? 「あれをしては駄目、これをしては駄目…と言ったような母親の教育」「答が先にある学校・大学教育」「横並び・実績至上主義の社会生活」の三点セットが新産業創出に必要不可欠な未知への挑戦力を奪い取ってしまっているからです。 そして、この状態を放置すると、「日本経済が没落路線を歩んでいる⇒(大人が自身を失っている⇒子供たちはロールモデルを身近に発見しにくくなっている)+(社会全体が閉塞状態に陥っている⇒心の余裕を失った人が増えている)⇒判断力に乏しい子供たちが孤立化している」という図式の実現が更に進むことでしょう。 以上の説明から明らかなように、「新産業創出に必要不可欠な未知への挑戦力はどうしたら養うことができるか?」を念頭に置いて教育改革の目的を設定したいものです。
“飴と鞭”を使って新産業創出に必要不可欠な未知への挑戦力をつける。こういう方法もあります。でも、この方法では艱難辛苦を乗り越える精神エネルギーを生み出すことはできません。 どうしてもやりたいからやる…ということではないので、“飴と鞭”がなくなったら万事休す…となってしまうからです。粘り強い挑戦を行い続けるようになるためには、 子供たちの内発的動機に基づく自己決定力を強化できるような教育を家庭・学校の両方で行う⇒子供たちは自主的挑戦に成功した喜びを知る⇒幼児が初体験した歩行を繰り返したがるような“繰り返しの快”本能が生き生き働くようになる──、という図式の実現が必要になります。
内面から湧き上がってくるやりたいことを自分で決定する⇒自分で決定したことだから困難を乗り越えてやり遂げる ── こういうことを繰り返せるような子供にするためには、家庭内教育と学校教育の連係プレイが必要不可欠です。
不思議な事象に接すると、疑問をとことん解明しようとする。いいかえれば、柔らかい心を持っている ── これが加齢に応じて思考力が伸びる人に共通していることです。 このような人間になるために、「自主性を極力重んじる」「子供の優れていることは積極的に褒める」「大自然との接触並びに童話や文学小説の読書の機会をできるだけ多くする」といったような子育てをすることが必要でしょう。
「学んだ力」よりも「学ぶ力」の方がこれからは大事です。なぜなら、時代は「学んだ力」が威力を発揮する先進国へのキャッチアップからジグソーパズル思考を必要とする知識経済の時代に大きく転換しつつあるからです。それではどうすれば「学ぶ力」を養うことができるのでしょうか?
── の二つの設問を頭の中に置いてください。そうすれば、自ずと解答が見つかることでしょう。 そうです。なんとしてでも学問したい…と思えるようにする動機付けに勝る教育はないのです。そのためには、「ごく最近発生した事件の因果関係を過去に順次遡る形で歴史を教える」、「各学習科目の出来不出来が日常生活の送り方に大きな差を生むことを納得させることを先行させる」といったような授業を行うことが必要でしょう。 ここに斉藤孝氏の提唱している「教師の優秀劣敗が明確になるようにする⇒年俸1500万円の実力教師を作る」という図式実現の意義があるのです。但し、この趣旨を生かしきるためには、 特定教師の下に数多くの生徒や学生が群がる⇒この特定教師の限界を超える⇒この教師の“眼鏡に適う”その他大勢の教師を組織化する⇒特定教師同様の能力をその他大勢の教師が発揮できるような「ウルトラナレッジマネジメント体制」を確立する──、という図式の実現が必要になることでしょう。
上記の主張に対して、「これまでの日本の良さであった平等主義はどうなるのか?」という疑問が寄せられるかもしれません。そこで、この点についての筆者の考え方を本稿の締めくくりとして述べさせて頂きます。 理念や理論では動かされない。感情で動く。しかも、日本の社会はウチとソトが明確に分かれているので、公共精神は希薄。これが日本人の体質。したがって、日本の社会は強制的に束ねるものがなければ、戦国時代のようにばらばらになりやすい。 このような日本の社会の秩序を保つために様々な工夫が凝らされてきました。この工夫のひとつが「細かい規制等を設ける⇒役割分担社会を実現させる⇒平等主義を実現させる」という図式です。 この図式が有効なのは、ほぼ一直線での成長が可能な時代のみです。このような環境であれば、各人・各組織が与えられた役割をひたすら守り続けてもなんら齟齬をきたさないからです。ところが、時代が様変わりして、「与えられた役割をひたすら守り続ける」のではなく、「断章取義をして活路を切り開く」ことが必要になりました。 仕事や私生活で立ち往生しているとすれば、上記の必要性に応えていないからなのです。
●『斬新な着眼』を無料でお届けする電子メールマガジンを発行しています。ぜひご登録下さい。
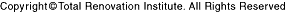 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||