![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所(古河イノベーションセンター)
〒306-0024 古河市幸町4-31(来客用駐車場があります)→道案内
| 直通「東京主要駅〜古河駅」で60分前後です→鉄道路線図 |
E-Mail: info@trijp.com
TEL 0280-23-3934
|
【斬新な着眼】

 |
「はないちもんめ型」官僚統制法(成毛眞)(2003/10/28号) |
 |
この小論の論理的整理並びに補足
|
 |
日本政府の診断 |
政治家が官僚に対しリーダーシップを発揮できない + (人材の裾野が狭い + 退官待機時の受け皿機関が不足している ⇒ 官僚を政権に応じて一斉に取り替えるポリティカルアポイント制度が導入できない) ⇒ 官僚独裁体制が温存されたままである。
上記の官僚独裁体制を会社に例えると、次の通りである。
社長(総理)は地元の商工会議所から数年間派遣されて来る人物で全く人事権はない。時期商工会議所の幹部になる若手を副社長(大臣)として迎えるが権限はない。たたき上げの専務(次官)は常務会を主宰しているが社長は絶対に出席させてもらえない。
社長が専務の意向に反する行為を行うと、専務は部下に命じて商工会議所のメンバー(族議員)に直接交渉させる。そのうち社員を教育するはずの社長は逆に教育されはじめ、専務の代弁者として町で有力な幹部として認められ始める。
たたき上げの専務は部下に命じて定年後に再就職するための子会社を用意させておく。本社の売り上げや利益を子会社に回しておくことも忘れない。子会社をいっぱい作っておけば、愚かな社長の何倍もの収入と名誉が手に入るというものだ。国が滅んでしまう。
 |
日本政府の処方箋 |
新しい政権が発足したら各閣僚は自省の局長以上の20%、課長以上の10%を他省または民間など外部から採用することを義務づける。(使命権の順位は総理が目玉となる政策を考慮に入れて決める)
そして、三つを実現させる。
|
|
|
|
 |
官僚があらかじめ自身のために天下り先を作っておくことを無意味にする。 |
|
|
|
|
 |
物事を多角的に見ることができる人材を育て、「省益」だけを考える縦割り行政の弊害をなくす。 |
|
|
|
|
 |
客観的に正しい政策遂行が困難化しにくくなりがちな中高年官僚の弱体化を実現させる。 |
「勝ってうれしいはないちもんめ、あの子が欲しい。この子が欲しい、じゃんけんぽん」を国政に導入するのだ。
 |
指摘された核心的な問題や対策の概念拡大と論理化 |
 |
政治家が官僚に対しリーダーシップを発揮できない…のはなぜでしょうか?
|
絶対的権力者であった戦前の天皇に官僚は直属していた⇒第二次大戦敗戦後の混乱防止のために官僚独裁体制が保持された⇒超長期政権を担った自民党が官僚に従属する形で政官一体化が実現された⇒官僚と国民の間を取り持つブローカーとしての政治家の役割が確立された──、という図式が実現されたからです。
 |
ポリティカルアポイント制度の導入に必要不可欠な人材の裾野が狭い…のはなぜでしょうか?
|
蛸壺あるいは樽の集合体であり、かつ先進国へのキャッチアップだけを考える…という状態が日本の社会に超長期に亘って続いた。このことが根本的原因となり、
成員間の情緒一体感志向が強い+社会全体の学問の必要性は皆無に近い⇒横並び志向が根づく⇒学際的論理的思考力は鍛えられようがない⇒パッチワーク的な問題解決の習慣が遺伝子のようにほとんど全員の日本人に染みついた⇒国家レベルの政策立案能力のある人材は例外的存在になるしかなかった──、という図式が実現されたからです。
 |
「あるべき総理が誕生する⇒あるべき政治家主導の行政が行われる」という図式はどうしたら実現できるのでしょうか? |
国民の思考力・判断力の水準を大幅に引き上げる。これが何よりも重要です。なぜなら、そうすることにより、二つの実現が可能になるからです。
|
|
|
|
 |
選挙が適切に行われるようになる ⇒ あるべき政治家の数が増加する⇒あるべき総理が実現するようになる。
|
|
|
|
|
 |
ポリティカルアポイント制度導入に必要不可欠な人材の裾野が広がる ⇒ 官僚を政権に応じて一斉に取り替える + 族議員(ブローカー型政治家)の跋扈が影を潜めるようになる⇒「総理─大臣─官僚」という「指揮系統」が機能する。
|
 |
どうしたら国民の思考力・判断力の水準を大幅に引き上げることができるでしょうか? |
立ち往生からの脱出・躍進に結びつく創造的問題解決策を、ワタナベ式問題解決へのアプローチのような手法を適用して専門家と共に創る ⇒ 構想・独創の喜びを認識する
⇒ 人間が本来持っている「繰り返しの快」本能が作動する ⇒ 構想力・独創力が継続的に強化される(判断力が継続的に強化される)──、という図式を実現させることです。
(「思考の三原則」(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える)の適用なくして構想・独創も判断も成功しません。そういう意味で構想力・独創力の強化は判断力の強化にも結びつくのです)
成毛眞氏が提唱する「はないちもんめ型」官僚統制法は上記した根本的対策が軌道に乗るまでのつなぎ的なものとして位置づけるべきでしょう。
●『斬新な着眼』を無料でお届けする電子メールマガジンを発行しています。ぜひご登録下さい。
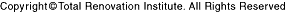
|
|
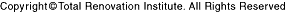
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)