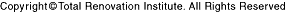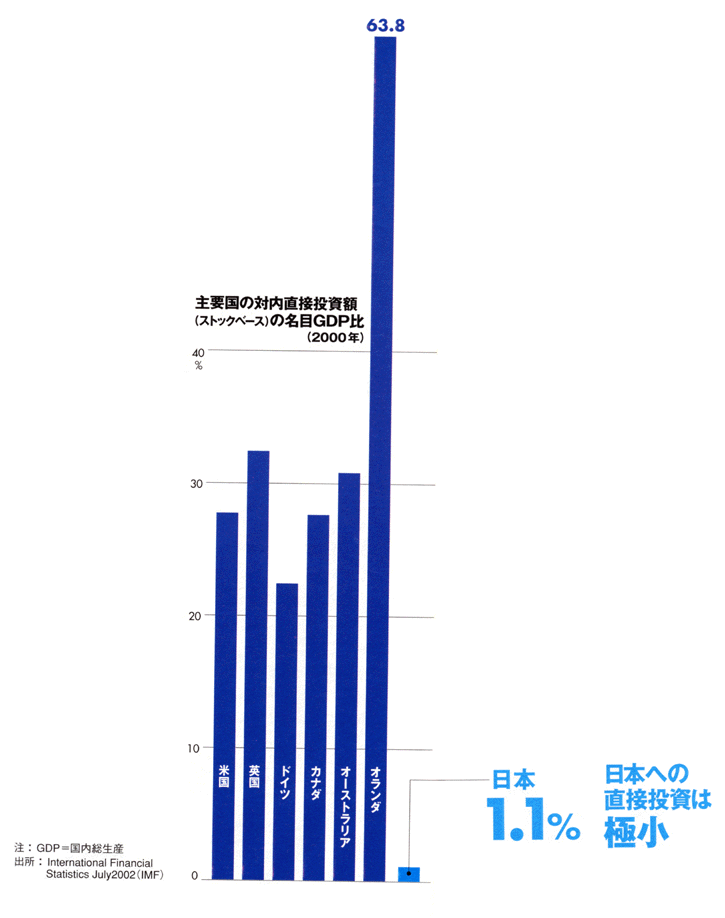![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【渡辺高哉の時代認識Ⅱ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 世界の流れが大きく変わりました。ビジネスに携わる方々が頭の中に是非入れて置かなければならなポイントが三つあります。 (ポイント1) グローバリゼーションのあり方を再構築しさえすれば、世界経済は再び拡大路線に乗る可能性がきわめて大きいです。 イスラム過激派による「9・11米国同時多発アタック事件」はどうして起きたのでしょうか? 主な原因は四つありそうです。 (原因1 貧富の格差拡大が怨嗟を生んでいる) 石油資源に恵まれている中東諸国は石油価格が高かった時は国民所得は高水準で、1980年当時のサウジアラビヤは世界有数の金持ち国だったほどです。ところが、人口が急増する中にあって、湾岸諸国全体の石油収入は激減して、1980年当時の1500億ドルから1900年代の800億ドルになってしまったのです。 20才以下が約60%、30才以下が約70%…と、総人口に占める若者の割合が1980年以来異常に高くなった。ところが、このような人口爆発が国の経済不振の下で発生したために、一人当たりの年間所得は20,000ドルからその半分に激減してしまっている。(『The Economist』March 6th 2004の45頁) 一方において、経済のグローバル化は米国経済を大きく発展させました。したがって、「貧乏なサウジアラビヤ等のアラブ諸国 vs 金持ちの米国等の先進国」の図式が分かりやすく浮かび上がり、情報化の進展とあいまって、貧困にあえぐ人々の怨嗟の気持ちがごく自然に生まれることになりました。 (原因2 宿命的な重荷が絶望感を生んでいる) 伝統的な価値観を変えにくい。職業的能力が劣っている。似た者同士での共同市場の形成もできない。: ── この三つが原因して貧富の格差を是正しようがないために、絶望感が生まれるに至っている人が多くなっています。 イスラム教には定期的な断食と祈り…といったような国際経済競争において不利な風習があります。しかしながら、イスラム教から生まれた風習は生活を支える価値観になっているために、こうした風習を急に改めるわけにはいきません。となると、ハンディキャプを背負ったままの状態で国際競争にさらされ続けなければならないのです。 伝統的な風習が国際競争上不利であっても、国民一人一人の職業的能力が優れていれば、話は変わってきます。ところが、下記の図式になっているのが実態なのです。 (豊富な石油資源がある + 王族の特権維持の必要性がある ⇒ 一般国民を甘やかしてきた) + 職業的能力開発を軽視した教育制度が採用されてきた ⇒ 職業的能力は低い水準に留まったままになっている。 上記のような国際競争上不利な条件があっても、同じハンディキャップを持つ者同士が共同市場を形成できれば、経済活動においてスケール・メリットが追求でき、その分、豊かになれます。ところが、、中近東は欧米先進国が仕組んだ不自然な国境が災いして紛争の火種を抱えているので、この地域共同市場の形成は困難になっているのです。 (原因3 米国がスケープ・ゴートになるしかない) 改革が必要不可欠。しかし、困難を極める。したがって、絶望的になるしかない。そして、この体制を米国が支えている。しかも、米国は世界一の金持ち国である。一方、国内の支配者は畏敬の対象になってしまっている。── このような構造になっているために、米国がごく自然に鬱積した不満のスケープ・ゴートになりやすくなってしまっているのです。 上記の実態をやや詳しく説明すると、次の通りです。 ・国内の支配者は畏敬の対象になってしまっているのはなぜなのか? 超長期にわたる王政の下で極度の家父長制が採られてきた ⇒ 権威に対する盲従の習慣が醸成された。しかも、豊かな石油資源に恵まれている ⇒ 支配体制は“善政”を行うことができた ⇒ 体制に対する“信頼”が醸成された──、という図式の下に国内の支配体制が置かれているからなのです。 ・米国がごく自然に鬱積した不満のスケープ・ゴートになりやすくなってしまっているのはなぜなのか? 国民生活は困窮度を増すばかりである。しかしながら、畏敬の念が染み付いているために支配体制に対する反発は生まれにくい ⇒ 国民は鬱積し続けている不満の捌け口を探し求めるようになる ⇒ ニューエコノミーの恩恵をほぼ独り占めしてきている米国が国民生活を圧迫している真犯人であるように思えてくる──、という図式が成立しているからなのです。 (原因4 鬱積する不満のガス抜きができない) 不満が限界まで鬱積していても、野外スポーツ・映画・飲酒等が自由にできれば、爆発は抑止できる場合が多いものです。ところが、イスラム教の厳しい戒律並びに貧困がこれを困難にしているのです。 ところで、積極的な経済主体者は自由に活躍できる世界の拡大を求めます。そして、考え出された手段はいずれも限界を露呈する歴史を辿ってきました。 (第1段階) 植民地支配 (戦争に結びつかざるをえませんでした) (第2段階) 東西冷戦構造 (米国と旧ソ連の負担が余りにも大きすぎました) (第3段階) グローバリゼーションの推進 (貧富の格差拡大・地球環境の破壊・成長の限界等に見舞われたが、世界唯一の超大国・米国ですら新秩序を形成できないまま今日に至っています) 米国のシアトルで開催された世界貿易会議に対する、想像を絶する大暴動という警告反応があったにもかかわらず、旧来型のグローバリゼーションは蛇行し続けてきました。そうしたところに、イスラム過激派による米国の同時多発アタック事件が発生したのです。マネジメントの達人揃いのアングロ・サクソンのエリートが次のように考えても、何の不思議もありません。 石油価格を引き上げ、自動車エネルギーの水素への転換をも含む、クリーン・エネルギー開発に向かわせる。その上で、先進国の脱工業化を推進しつつ、世界規模での地域主義からなる共同市場の推進を通じて低開発国の経済開発を進め、「輸出拡大 ⇒ 貿易赤字の縮小 ⇒ 次世代産業開発力増強」という図式を実現させて、アメリカ経済を再浮上させる…。 問題はどのようにして石油価格を引き上げるかですが、イラクが第二次湾岸戦争に突入する以前から抱えている約1100億ドルの負債並びに第一次湾岸戦争が生み出した約2000億ドルの賠償金の支払い力創出…という大義名分の下に、イラクの石油資源を完全に支配することにより、下記の図式の下に政治的リスク を冒すことなく実現させる可能性が大です。 石油価格を引き上げる ⇒ イラクが国際社会に対する義務遂行と国土再建が容易になる + 外貨不足で悩む石油大国・ロシアの協力を引き出す + 物価引き上げによる世界経済のデフレを抑制できる ⇒ 米国を始めとする先進国の財政再建が進みやすくなる。
(ポイント2) 米国の同時多発アタック事件のショック効果は日本にも及び、経済のマクロ環境は紆余曲折はあるとしても、大きく好転します。 日本企業のマクロ環境は絶望的です。なぜなら、資産対負債の比率が米国の7倍に達してしまっているからです。したがって、「世界経済の将来は明るいとしても、今の日本はそんな将来のことを考える余裕はまったくない」という声が聞こえてきても不思議はありません。 しかしながら、見方を変えると、あることをきちっとやりさえすれば、楽観的に考えてもよさそうです。なぜなら、米国の同時多発テロ事件がショック効果を発揮して、4ステップを踏んで日本経済再生の足かせとなっている、人材のミスマッチ是正が急ピッチで進むことが期待できるからです。あくまでも期待ですが…。
但し、世界の製造王国の基盤をしっかりと固めつつある中国等の開発途上国の存在を考えますと、「円安 ⇒ 製品輸出の拡大 ⇒ 日本経済の再生」という具合にはいきません。他の先進国同様に脱工業化、つまり新時代に相応しいサービス産業を振興しなければなりません。そして、そのためのマクロ環境は整うものと思われます。あくまでもマクロ環境ですが…。なぜなら、次のシナリオが実現される可能性が大だからです 円安 ⇒ インフレ + 外資の対日直接投資拡大 + 大都市への人口集中促進 ⇒ 土地価格の上昇 ⇒ 資産効果の回復 ⇒ サービス需要の拡大 ○「外資の対日直接投資拡大」という考えの根拠は下記の通りです。 ○「 大都市への人口集中促進」という考えの根拠は下記の図式です。 (財政再建の必要性 + 中国経済等の躍進と工業化の限界が生み出した産業の空洞化 ⇒ 地方社会の自立と自律の必要性) + 地球環境保全風潮の高揚が生み出す広域地域別農産物自給自足度拡大の必要性 ⇒ 超広域行政・経済開発の必要性。(新時代に相応しいサービス産業振興の必要性と方向性の認識を深めたい方 ⇒『「輸入大国への転換が日米緊密化の最善策である』) 後は企業努力次第です。そして、この努力のための資金はたっぷりと用意されるのです。なぜなら、貸し渋りの銀行をバイパスさせてマネーサプライを拡大できる上に、企業育成能力のない市中銀行は自然淘汰されるだろうからです。 (ポイント3) 急激な不況が様変わりした市場を一気に露呈して、本物のみが大飛躍できる時代がやってきました。 中古車には、丁寧に乗り続けてきたものとその逆のものがあります。ところが、その差を反映させた中古車市場が形成されることはほとんどありませんでした。その結果、価値の低い中古車に鞘寄せされる形で価格が設定されがちとなり、価値の高い中古車のほとんどは「割を食ってしまうことに我慢する」「市場に参加しない」のいずれかの道を選択するしかありませんでした。(実はこれは2001年度の経済学部門におけるノーベル賞のテーマなのです) 本物がひっそりと生きている時代が長い間続いていたことは、中古車に限ったことではありません。ところが、世の中が大きく変わることを示す象徴的な出来事が生まれました。 IT不況に9・11事件が加わって米国内の自動車売り上げが急落した中にあって、BMWのみが売り上げを伸ばしているのです。2001年度の利益は前年比50%増が予想されるほどです。「究極の車」と噂される新車の登場がこの背景にあるのです。この現象は急激な不況が様変わりした市場を一気に露呈して、本物のみが大飛躍できる時代がやってきたことを物語っています。
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||
| → トップページ | ||
|
|
||