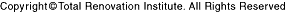![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯414-7 来客用駐車場があります ☎ 029-229-0225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【斬新な着眼】
中国は世界経済の中にあって突出した成長セクターになりつつあります。これはデフレ圧力軽減に結びつきますので、世界経済にとって好ましいことです。しかしながら、この効用はあくまでも短期的にしかすぎません。なぜなら、放置しておきますと、中国が世界の工場機能を貪欲に飲み込みかねないからです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界経済の最大の不安要因はドル価値の暴落である |
どうしてこんな不思議なことが発生しているのでしょうか?理由は大別して二つある、と私は理解しています。
| (理由1) ドル安 ⇒ アメリカ人以外の財産の目減り…という図式が世界経済の中に組み込まれている 円は日本人のためにあると同じように、ドルは本来アメリカ人のためのものです。ところが、このドル発行額の半分以上がアメリカとは無関係なところで使われている。つまり、アメリカ以外の国同士の貿易の決済やアメリカ人以外の貯蓄手段としてのドルの需要がドル発行額の半分以上を占めているのです。 こういう状態になったら、「アメリカが憎い」「ドルを持っていると不安」…と思っても、自らの首を絞めることに結びつくドル売り…という行動には歯止めがかからざるを得ないのです。このことを普通の人間関係に例えて説明してみましょう。 Aさんの借金は膨らむ一方。ところが、このAさんにお金を貸している人達はAさんのお陰で生活が成り立っている。となると、他の人々は仮に「けしからん」…と思っても、Aさんに対して貸したお金の取立てをすることができない──、アメリカのドルはこのAさんの立場にあるようなものなのです。アメリカはAさんのように他国のお金を使って、他国の経済を潤しているのです。 |
|||||||||||||
| (理由2) 「貿易決済はドルで行いたい」…という気持が世界中に生まれてしまっているために、ドルに代わる他の通貨の普及を妨げている ドル独裁の傾向に歯止めをかけるために、ヨーロッパ人共通の通貨、ひいては世界の通貨になることを願ってユーロが誕生しました。ところが、思惑通りに事は運ぶに至っておりません。なぜなら、ドルからユーロに乗り換えると、二つのことが発生してしまうからなのです。
したがって、対抗通貨のユーロが誕生していながら、ドルは世界の人々の共通の通貨に実質的になってしまっているのです。ドルは金のようになってしまっているのです。 「BさんだってAさんに負けないだけ皆に役立つ。だから、Bさんにもお金を貸そう」…と言うわけにはなりにくいのです。なぜなら、Bさんの勢いが増して、Aさんが没落してしまうと、Aさんに対するこれまで積み上げてきた貸しの経済価値がなくなってしまうからです──、アメリカのドルはこのAさんのような状態にもなっているのです。 アメリカは世界(特にアジア)に向かって「私にどんどんお金を貸しなさい。この貸付金は皆さんの財産になりますよ」…と言えるような強い立場にあるのです。(補足説明 ⇒『先進国と途上国の経済融合が進む』) このように非常に強い立場を確立したドルであっても、世界貿易がなくなれば、その価値を失ってしまいます。買うものがあって始めて円の価値があるのと同じことなのです。世界貿易がなくならなくても、縮小していきますと、それに応じてドルの価値は減っていきます。購買対象が減れば減るほど円の価値が低下するのと同じことなのです。 そうです。ドルの価値を維持・上昇させるためには、世界貿易の拡大が必要なのです。このことを普通の人間関係に例えて説明してみましょう。 Aさんにお金を貸すと、Aさんが他の皆の活躍場面を広げてくれる。そして、それがいくらでも可能である──、これと似た状態があって始めてアメリカは借金し続けることができるのです。 ところが、世界貿易拡大に赤信号が点りました。先進国の工業化の限界に伴って、保護貿易の兆候が生まれ始めたからです。この傾向がそのまま放置されますと、ドル安が進まざるを得ません。 Aさんは借金を拡大しても他の皆の活躍の場を広げることができなくなった。となると、その分、Aさんに貸したお金の価値が減ってしまう──、これと似た状態が発生しつつあるのです。 このドル安にアメリカの経済力弱体化が加わりますと大変なことになってしまいます。なぜなら、「アメリカの経済力低迷 ⇒ アメリカへの投資の魅力低下 ⇒ アメリカへのドル還流量の減少 ⇒ ドル安 + アメリカの消費低迷 + アメリカ産業界の過剰能力 ⇒ 世界各国へのアメリカ製品の輸出拡大 ⇒ 経済がデフレ化している世界各国の失業率拡大」…という図式が待ち構えているからです。 Aさんが皆の活躍場面をブルドーザーのように拡大することができなくなった。さりとて、他の皆はアメリカにおんぶに抱っこの生活をし続けていたために、自力で活躍場面を拡大することができない。Aさんも生きるために他の皆の仕事を奪うしかない。すると、他の皆は生活難に陥ってしまう。そして、回りまわってアメリカも同じ運命を辿るしかなくなってしまう──、このような共食い状態に世界は陥りかけているのです。 |
| アメリカは中国経済が突出する形で発展することを歓迎しない |
これまでの説明でご理解頂けましたように、世界はデフレ経済の様相を濃厚に帯びてきました。したがって、上記の世界経済恐慌の図式が現実化する危険性は大です。だから、世界は中国経済に熱い視線を浴びせているのです。
普通の人間関係に例えて言いますと、共食い状態のところに、お金を貸して上げさえすれば、生活苦から抜け出させてくれるCさんが登場したのです。このCさんはずーっと前からいましたが、この頃めきめきと力をつけてきたのです。
ところが、Cさんのような中国経済が突出する形で発展することをアメリカは歓迎しません。理由は大別しますと、二つあります。
| (理由1)現状路線を歩む限り中国が超経済大国になるのは時間の問題である 日本のかっての模倣対象であったほどに中国の人的資源の質的潜在力は高い。ところが、経済開発は海岸線のみが進んでおり、膨大な人口と土地を抱える内陸部は遅れている。世界貿易機構に正式に加盟したために外国は安心して中国に投資できるようになった──、これが中国の実態なのです。中国は将来的にはアメリカをも凌駕する超大国になる素質を持っているのです。 工業化がいくらでも可能な世界でしたら、中国の経済開発はそれほど進まないでしょう。ところが、世界は工業化の限界という壁にぶつかり、デフレ経済の様相を呈してきました。となると、世界中の余ったお金や生産能力は中国に殺到するしかありません。かくして、中国は世界の工場機能を一手に引き受ける勢いを見せ始めているのです。 このように言いますと、「工業化の限界が国内生産の中止に結びつくのはおかしくありませんか?」…という疑問が生まれることでしょう。これはもっともな疑問です。でも、中国は世界の工場機能を一手に引き受ける勢いを見せ始めているのは事実なのです。どうしてだと思いますか? 中国の賃金水準がべらぼうに安いので、国内生産に固執していますと、価格競争に負けてしまうからなのです。しかも、中国は気が遠くなるほど膨大な労働力を抱えていますので、いくらでも生産能力を拡大できるのです。 ということは、中国への資本投下は他国の従来型産業の存立を困難にしてしまうことを意味します。世界経済はとんでもない状況に入りつつあるのです。このことを普通の人間関係に例えて説明してみましょう。 Cさんにお金を貸しさえすれば、Cさんは他の皆の仕事を生んでくれる。のみならず、低価格の商品を提供してくれる。ところが、その内、Cさんは他の皆の仕事も自分でやるようになってしまう──、世界各国にとっての中国の存在はこのCさんと似ているのです。 他国にとって中国はアメリカと根本的に異なっているのです。アメリカは自国の産業構造を高度化し続けることによって他国の雇用拡大に貢献してきたのですが、中国は世界の雇用を奪う形で他国の産業を限りなく侵食し続けるのです。(この構図の基本は2006.8.12現在でも変わっていないはずです) |
|
| (理由2) 中国が超経済大国になることは超軍事大国になることを意味する 中国は他国の産業を限りなく侵食し続けるだけではなく、同時に超軍事大国への道も歩みつつあります。この様子を図式化しますと、次の通りです。 中国で研究開発を行う先端的技術を持つ世界の企業の増加(先端技術の漏洩を恐れていたのでは拡大する中国市場獲得競争に勝つことができないのです) + 経済発展に伴う軍事予算の拡大 + 軍事技術と民生技術の境目の消滅(真っ暗闇でも写真撮影できる民生技術が軍事技術に転用されている等が一例です) ⇒ 中国の軍事力の質・量の飛躍 上記図式が実現することをアメリカは許容できません。なぜなら、アメリカは世界ダントツの軍事力を維持することを決意しているからです。 |
| アメリカは中国を凌駕するアジアの輸入大国を必要としている |
アジア全体の経済発展を抑圧しさえすれば、中国経済を突出する形で発展させることを阻止できる…というアメリカの思惑は実現できます。しかしながら、この道はドル安につながります。それから経済が縮小していまい、高齢化する人口を養うことができなくなります。経済の縮小 ⇒ 株価の一層の下落 ⇒ 年金不足…となってしまうからです。
となりますと、アメリカは中国を凌駕するアジアの輸入大国の登場を願うしかありません。このあたりのことを突っ込んで説明しますと、大別して三つの理由が浮かび上がってくる、と私は理解しています。
| (理由1) 大きな潜在力を持った開発途上国の経済開発を急がなければならない ドル価値の上昇傾向を促進するもうひとつの要因があります。発展途上国の存在がそれです。発展途上国の人々は先進国のような生活をしたい…という思いが強烈です。この思いを遂げるためには輸出を拡大するしかないのです。 なぜなら、「道路、通信施設、住宅等の社会資本の整備をしなければならない ⇒ お金がないので外貨を稼がなくてならない ⇒ 輸出を拡大しなければならない ⇒ 輸出しやすくするためには自国の通貨の価値を低くしなければならない(ドルの価値を高くしなければならない)」…という宿命があるからです。 中国はまぎれもないとてつもない発展性を秘めた発展途上国です。でも、前述しましたように、中国が突出して発展しますと、アメリカの国益が損なわれかねないのです。だから、膨大な人口を抱える他のアジア諸国への大きな期待があるのです。 |
| (理由2) 世界経済運営の仕組みを変えなければならない 日本、アジア諸国、アメリカの三つを中心に世界経済運営のこれまでの仕組みを単純化して説明しますと、次の通りです。 日本が生産設備等の資本財並びに光学関係等の部品をアジアに輸出(したがって、アジアの対日貿易は大幅な赤字)。アジアが完成品をアメリカに輸出(したがって、アジアの対米貿易は大幅の黒字)。日本はアジアとの貿易で溜め込んだドルをアメリカに還流。この還流されたドルがあるので、アメリカの旺盛な消費需要 ⇒ 世界経済の牽引…という図式が成立。 上記の図式を支えてきたのがアメリカの旺盛な民間需要でした。ところが、民間部門がマイナスの貯蓄となってしまったこと等が原因して、この図式を継続することができなくなってしまったのです。つまり、世界経済運営の仕組みの再構築が必要不可欠になったのです。 |
|
| (理由3) 現状路線を歩むと、アジアはテロの温床になりかねない だからかといって、アジア諸国の対米輸出の低迷状態を放置できません。日本の産業界が困るだけではありません。「貧困 ⇒ アメリカへの反感 ⇒ 新たなテロの温床化」…ということでアメリカも困るのです。 アジアの大都市は、整然…という状態とは程遠い、不気味な人達の溜まり場となっていることが多いのです。アジアの大都市には新宿の歌舞伎町に似た怪しげな雰囲気のところが少なからずあるのです。 |
そうです。アメリカに代わって、しかも中国を凌駕するアジアの輸入大国の存在をアメリカは必要不可欠とするようになったのです──、これが上記の理由1・2・3の意味するところです。
| エネルギー問題は世界経済の大きな撹乱要因にはならない |
世界の石油宝庫である中東の情勢が不穏であるのに、中国を凌駕するアジアの輸入大国の必要性だけに目を向けていて良いのか?…という当然の疑問にお答えします。お母さんが62歳になるちょっと前に石油価格が突如として大暴騰して、トイレットペーパー騒ぎ等の物不足、そして、やがて大不況──、この記憶が生々しいだけにこの疑問が出て当たり前なのです。
石油価格は大変動するにしても決して長続きしないだろう──、これが結論です。理由は大別して三つある、と私は理解しています。
| (理由1) 供給能力は需要量を大きく上回っている 石油の採掘コストは地域によって大きく異なります。中東の湾岸で1~2ドル、その他の地域で10~20ドル…といった具合です。いずれもバーレル当たりのコストです。したがって、石油価格が低く抑えられていますと、中東湾岸諸国の供給独占状態が実現されてしまい、世界経済は不安定化してしまいます。 ところが、バーレル当たり18ドル以上の相場価格が3年以上続いたために、その他地域の石油資源の開発が進み、供給能力は需要量を1日当たり100万バーレル上回ってしまい、しかも、この数字は拡大傾向にあるのです。 |
| (理由2) アメリカのイラク攻撃は供給量の大幅削減には結びつかない アメリカがイラクに対する武力攻撃を開始しますと、イラクは様々な報復をすることでしょう。そのひとつとして、隣接のクエート等の石油基地が破壊されることでしょう。だからといって、中東からの石油の供給が途絶えることはないものと思われます。なぜなら、イラクと他国の石油基地との間にはそれ相応の距離があるからです。 |
|
| (理由3) 石油価格は高すぎても低すぎても採算が採れない 30ドルを超えると、石油需要が激減するし、石油以外のエネルギー資源の開発が進んでしまう。一方、17ドル以下だと、量で稼ぐ必要が生まれ、虎の子である石油資源がたちまちの内に枯渇してしまう──、これが石油ビジネスの実態なのです。 |
上記三つの理由に加えて、非常時に備えた石油備蓄量十分。ということは、石油問題が世界経済を大混乱に陥れることはない、と結論づけることができます。但し、1991年の湾岸紛争時と比べて、世界経済の状態はかなり悪いことを念頭に置く必要があること言うまでもありません。
アメリカがバブルの後遺症を引き引きずったままの中にあって、頼みのヨーロッパ共同市場は金融政策が硬直的、そして、日本はデフレに突入してしまっている。しかも、石油産出国・ベネズエラの国内紛争が長引いている──、こういう悪材料の存在を忘れてはならないのです。
したがって、なおさらのこと、世界経済の安定と成長のために努力を傾注すべきは、これまでの世界経済を引っ張ってきた製品・サービスとは質的に異なる、新しい成長機会を発見・開発することです。
日本は明治維新以来の歴史的転換期にあります。180度の発想の転換が必要なのです。ところが、政界・官界・財界・学界の指導者の方々は過去の延長線上に未来社会を捉えたり、経済を機械装置のように操作できる…と考えたりするところがあります。だから、窮地から脱することができないのです。
お母さんは明治だけでなく、これからの転換期を見物できるわけですから幸運です。日本がこの転換期を見事に乗り越えることができるか、それとも、かっての貧乏国になってしまうのかを見極めるまで元気でいてください。
日本は地下資源がないに等しい国です。したがって、単なる輸入大国に転換するだけでは駄目です。「社会構成員全体の相互依存を高める ⇒ May I help you ?…の輪を広げる ⇒ 新産業の継続的な発祥地になる ⇒ 日本経済が再生・躍進する」──、という図式の実現が必要です。
日米の協力関係は、目的達成のための日本の弱点が補強される形で上記図式の中に位置づけられなければなりません。
| 概略…という限界はありますが、「これが統合戦略だ!」…というものを提起させて頂きます |
そこで、社会構成員全体の相互依存を高める。新産業の継続的な発祥地になる。輸入大国に転換する──、この三つの実現に結びつく、日本経済再生の統合戦略の概略デザインを試みることを予定しています。「東電等の不祥事問題」「政治の劇場化現象」「北朝鮮問題」はこの試みの中で目的達成にとっての好材料として論じさせて頂きます。
様変わりした時代に適応できるようになるには創造的な統合戦略の策定が必要不可欠。にもかかわらず、相変わらずの継ぎ接ぎ的対策が目立っている。だから、国家・地方自治体・企業・個人は立ち往生状態から脱出・飛躍できない──、こういう危機感も手伝って国民最大の関心事であるテーマを題材に用いて、
| 悪しき現象を断片的に捉えるのではなく、体系化(構造化)し、核心となる問題を抉り出す。 | ||||||
| 世の中の動向、自らの潜在能力、突破口に使える“神風”──、の三つを見抜く、 |
の二つを前提に統合戦略の概略デザインを試みよう、と思い立った次第です。
この概略デザインをご覧頂くことによって、 「これまでの対策では駄目であることがよく分かった。こういうものがあれば、我々だって難局から脱出して新たな躍進ができそうだ」…と多くの人々が立場を超えてお思いになられることでしょう。なぜなら、組織・個人が様変わりした環境に適応できるよう自らを再構築するためには、上記二つを前提とする統合戦略の策定が必要不可欠だからです。
上記の提起の準備にはそれ相応の日時が必要です。したがって、次回の発表時期は来週の木曜日ではなく、かなり先になることをご了承ください。
先進国の国内は工業化が限界に達してしまっている。中国は世界の製造業を貪欲に平らげつつある──、このような事態を世界はこれまで経験したことがありません。どうしたらよいでしょうか? 前述したように、これまでの世界経済を引っ張ってきた製品・サービスとは質的に異なる、新しい成長機会を発見・開発する──、これが先進国の企業が国内に雇用を保ちつつ生き残るための唯一の方策です。
具体的には、爆発寸前のマグマのような状態になっている新しいサービス需要を発見・開発できるような経営体制を構築することです。だからといって、「製造業よサヨナラ」…というわけではありません。新しいサービス事業への進出が製造業の高度化を可能にする事業戦略を、ひいてはビジネス・モデルを独自に策定・構築することが望まれているのです。詳細については ⇒『勝ち組メーカーに学ぶサービス事業戦略』
| ● | 従来の人材を活用して新しいサービス事業に成功裏に進出するための方策について関心のある方は ⇒『オープンリソース経営を行えるようにする』&『経験の浅い人材でも高質のサービスを提供できるようにする』をお読みください。 |
| (前号に戻る) |
▲トップ
|
|
||||
|
→ トップページ | |||
|
|
||||