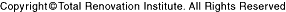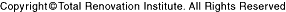|
「思考の三原則」を適用した智恵と勇気の安直な付与がなぜ必要なのか? |
新成長機会を掴むことが必要不可欠になった。ところが、前途に二つの壁が待ち構えている場合が多くなったからです
 |
インサイダーではなくアウトサイダーの力を借りることがなぜ必要なのか? |
「環境が様変わりした + 先行きが不透明になった ⇒ 過去の延長線上を歩んだり、突っ走ることが許されなくなった ⇒ 培ってきた経験則が陳腐化してしまった」
or 「合理よりも人間関係を優先する習慣が過去の延長線上を歩むことに異を唱える気持ちを萎えさせる ⇒ 組織運営の舵取りを誤る」という図式があるからです。
(参考資料 ⇒ 『最悪のシナリオ「新成長機会深く潜在 + (習慣のロックイン ⇒ 精神的視野狭窄症 ⇒ エアーポケットの中をもがくが如き努力)⇒ 没落」があり得る時代になったことを認識しなければならない』)
 |
コンサルタント会社は一般的にどんな実態になっているのか? |
(コスト配分) 受注金額の7~80%を営業活動に投入している。したがって、顧客サービスのために投入できるのは受注金額の2~30%のみである。
(アウトプット) 顧客企業の社員に提出させた問題点・問題解決策を巧みに編集する。調査・開発済みの問題解決策メニューの中から一番相応しい問題解決策を企業の実態に即して選択する。── この二つのいずれかである。
(顧客企業側の人間は「目新しい意見がほとんどない」「知的興奮を感じるものがない」という感想を提案書に対して抱きがちなのです)
(最終成果) 当事者が「よし、これだ。なんとしでもやり遂げよう!」と思いこめる状態になっていないので、巨額の費用は所期の目的達成に結びつくことなく“お蔵入り”。仮に当事者の新しい行動の引き出しに成功しても、コンサルタントが想定している経営環境ではなくなりつつあるので、賞味期限が切れかかっている提案内容になっている。
上記の文章は何を説明しているのでしょうか? コンサルタント会社一般の実態なのです。日本人が不得手な知的アクロバットを伴うジグソーパズル思考を伴う構想・独創力の不足だけがこの実態を招いているのでしょうか? 否」です。日本のマスコミにも共通していることですが、この実態の背景には、下記二つの図式もあるのです。
図式1 : 先見力をも含めた構想・独創力が大幅に不足している ⇒ 既存の優良企業の経営のあり方を問題解決策メニューとして採用している。(先見力をも含めた構想・独創力の説明 ⇒ 『先見力を磨き、異変待ち受け型経営を志向しなければならない』)
図式2 : 日本文化の本質をほとんど理解していない ⇒ 米国式の改革方法を持ち込んで平然としている。 (詳しくは ⇒ 『米国は“外生変数重視主義”でOK。日本に必要なのは“内生変数重視主義”』)
コンサルタント会社がこんな実態のままでいいのでしょうか? 「否」です。「思考の三原則」
(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える) を適用した智恵と勇気を安直に与えてくれるアウトサイダーの力を借りることが必要不可欠な時代がやってきたからです。
図式3 : コンサルタント会社が大組織化する ⇒ (だぼハゼ的な受注活動を行う ⇒ 衰退企業や新参企業との取引が拡大する ⇒ 既存のコンセプトですますことが多くなる)
or (経営者ではなく部門長との付き合いが増加する ⇒ 長期・全体最適志向をする必要性がなくなる ⇒ 既存のコンセプトですますことが多くなる) ⇒ 脳力が陳腐化する。(詳しくは ⇒ 『世界的権威であっても「組織の力学」に嵌ると道を誤る』
|