![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528 FAX: 03-3773-6082 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【斬新な着眼】
この10年間、政治家も官僚も口を開けば改革を叫んできた。ところが、改革を行えば行うほど、世の中は悪くなっていくばかりである。こうなってしまっている背景には、 日本の戦後教育は「個性の尊重」という美辞のもと、子供が我慢力を養う機会を奪ってきた ⇒ 日本の活字文化はテレビやインターネットに押され気味となり、幅広い読書を積み重ねることがなくなった ⇒ 教養レベルが低くなった ⇒ 現在の日本の政治家や官僚には「大局観」「長期的視野」が欠けているので、対処療法しか出てこない──、という図式がある。
「大局観」「長期的視野」の源である幅広い読書を多くの人々が行うようにするために、 小1から小4までは国語の授業を週10時間行って読書力をつける + 「テレビは1日1時間国民運動」「携帯電話不携帯運動」を展開して、読書・自然との交流・家族団欒に費やせる時間を強制的に増やす + 子供に手伝いの強制や人間が尊重すべき価値観の押しつけを行う ⇒ 問題意識と我慢力の強化が同時に進む ⇒ 読書の時間が増える ⇒ 問題意識と我慢力の強化が同時に進む──、というプラスのスパイラル現象が生まれるようにする。
我慢力とは何を指すのでしょうか? 我慢力には2種類あります。
藤原正彦さんが指摘しているのは「受動的我慢力2」です。これが大事なことであることは間違いないところです。しかしながら、もっと大事なことは、一度始めたことは辛くてもじっと耐えることがどうしてできないのかを認識することです。どうしてなのでしょうか? 人間誰しもが持っている「恒常性の維持」並びに「生存の拡大」という二大本能が作動していないからなのでしょう。どうしてこうなってしまうのでしょうか? 「我慢力1」がないからなのでしょう。逃げることなく現実を直視して始めて人間の持つ素晴らしい本能が作動することを忘れてはならないのです。
日本にとって焦眉の急を要するのは日本の本格的再生の決め手となるイノベーション力の源となる「能動的我慢力」の強化です。そして、この「能動的我慢力」の源となるのは「受動的我慢力1」です。 ── このことをより深くご理解頂くために、 能動的我慢力がどうして弱体化してしまったのか? 適切なイノベーションはどうしたら生み出せるのか? 能動的我慢力はどうしたら強化できるのか? 能動的我慢力を子供に植えつけることがなぜ必要なのか?…を順次考え、その中に受動的我慢力問題を位置づけさせて頂きます。
母親が子供に過干渉になった ⇒ 子供の内発的動機に基づく自己決定力が弱まり、自己決定は外発的動機に基づくのが精一杯となってしまった ⇒ 厳しい現実を受け止める我慢力が養われなくなってしまった ⇒ 「どうしてもやりたい」と心の奥底から思い込むこととは縁遠くなってしまった ⇒ 自己責任遂行的な粘り強さがなくなった──、という図式が実現されているからです。
「子供がどうしてもやりたい」と心の奥底から思い込むことを尊重することが適切なイノベーション行動に直結するでしょうか? 「否」です。なぜなら、 基礎知識がある + ハングリー精神がある ⇒ (知識欲が生まれる + ハングリー精神がある) ⇒ (知識が豊かになり、臨界点を越える + ハングリー精神がある) ⇒ 適切なイノベーション行動が採られやすくなる──、という図式が必要である、と思われるからです。 イノベーションに必要不可欠な斬新な着眼を入手するためには、「視野を極力広くする(知識を極力豊かにする) ⇒ 豊かな知識を使ってジグソーパズルのような解析を行う」という図式の実現が必要であることを忘れてはならないのです。 このように申し上げますと、「豊かな知識がなくても独創的なアイディアは生まれるのではないか?」という反論が出されるかもしれません。しかしながら、この反論は間違いです。なぜなら、 社会的に有益な価値創造に結びつくアイディアは大きな隙間市場の発見・洞察に基づくものでなければならないからです。我々は多様な知識や技術が氾濫している時代に生きていることを忘れてはならないのです。
それでは「どうしてもやりたい」と心の奥底から思い込むことを実行するようになる ⇒ 自己責任遂行的な粘り強さが目立つようになる」という図式がどうしたら実現できるのでしょうか? 子供に対する過干渉を極力控える一方において、名著と言われる文学書を読み耽ったり、自然と親しむ幼年時代を過ごさせることです。なぜなら、そうすることによって、様々な事象に知的好奇心が次々と沸いてくるようになるからです。 (事の成否を判断できるようにするためのしつけを行う意味での干渉が必要であるのは言うまでもありません) このように言うと、「過干渉な生い立ちを送った人間は能動的な我慢力とは無縁の存在であることに甘んじなければならないのか?」という質問が出ることでしょう。この質問は是認するしかないのでしょうか? 3段階の気づきがこのような宿命論を吹き飛ばす道を歩むことを可能にしてくれます。
挑戦意欲よりも失敗を恐れる心の方が勝りますと、イノベーションは決して生まれません。ここに、子供の頃から能動的我慢力を植えつける必要性があるのです。なぜなら、子供時代に能動的な我慢力を養うことは、 幼い頃から内発的動機に基づく自己決定を行い続けてきた ⇒ 挑戦成功が生み出す「もう一度…」というリズムが醸成される + 未知への挑戦を成功させるために必要不可欠な勘と度胸が養われる ⇒ 社会人になって「繰り返しの快本能」が疼くようになる ⇒ 挑戦行動を成功させる ⇒ 「繰り返しの快本能」が疼く・・・・・──、という良の循環の図式に結びつきやすくなるからです。 社会人としてのイノベーション行動は大きなリスクを伴います。このリスクの大きさを考えると、挑戦意欲があっても身がすくんでしまうものなのです。ところが、社会人になる前からイノベーション行動に慣れていれば、「挑戦したい意欲の大きさ > 社会的リスクの大きさ」となることが多くなるのです。 以上の説明からお分かり頂けましたように、藤原正彦さんが強調している「基礎知識」の習得はイノベーションの火種のような存在なのです。そして、この火種を円滑に宿せるようになるためには 「時間的余裕」よりも「内発的動機に基づく自己決定」を優先させなければなりません。なぜなら、そうすることは下記の図式実現に結びつくからです。 本人の心の奥底から湧き上がってくる学習意欲が大きくなる ⇒ 情報の方から本人に飛び込んでくるようになる ⇒ 読書や勉強の時間が仮に少なくても大きな成果が上がる。
以上の説明をお読みになり、「適切なイノベーション行動が採れるようなるためには生い立ちが大事である。したがって、理想的な生い立ちを送らなかった青壮年者はもう間に合わない」と思われる方がいるかもしれません。しかしながら、この考え方は間違っています。なぜなら、前述したように3段階の気づきがこのような宿命論を吹き飛ばす道を歩むことを可能にしてくれるからです。子供や若者だけではなく熟年に達した大人であってもです。
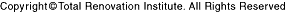 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||