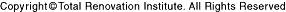![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com 〒311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町414-7 来客用駐車場があります TEL 029-229-0225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(節子) 引退した高齢者がうつ病症状になる仕組みは納得できる。ところが、仕事にも趣味にも生き生きとしていた人が管理職になってうつ病になってしまうことが多いそうね。これってどう解釈したらいいのかしら? ますます張り切って出世街道をばく進する人もいるのに。 (高哉) 「頑張らくなくっちゃ」と思いだけが先行してがむしゃらに働くので、次の図式実現とは程遠い状態になってしまうからだと思う。
(節子) なるほど。よく分かる。仕事に追われるのではなく仕事を追うようになることは大事よね。というのは、次の図式の実現に結びくんだから。 気持ちが前向きになる ⇒ 記憶と胆力を司る海馬が心地よく刺激される ⇒ 仕事を通じて知識・ノウハウがどんどん身に付く。 でも、ちょっと分からないことがある。出世や評判を気にしているとうつ病になることがあるそうよ。どうしてかしら? 気持ちが前向きでも駄目なことがあるということよね。 (高哉) 性格発の衝動強迫に支配されている状態になっている。このことが次の図式の実現に結びつくからだと思う。 (仕事を楽しむことができない ⇒ 記憶と胆力を司る海馬が心地よく刺激されない ⇒ 仕事を通じて知識・ノウハウが溜まりにくい ⇒ 「もっともっと」とならないために仕事をすることが苦痛になる) + (冷静ではないので盲点が生まれやすくなる ⇒ 仕事を臨機応変にこなせなくなり、へまをしがちとなる) ⇒ 仕事をすればするほどストレスが溜まる。 (節子) 適切で好きな道の世界に入ることが大事だというわけね。でも、そうであっても、「人員が削減されている + 納期の短期化が進んでいる ⇒ 仕事量が増えている」といったような場合は心身のフレキシビリティを奪うことに結びつく過剰労働になり、やがてうつ病になってしまうんじゃないかしら? (高哉) 仕事量が過剰に増えているのに仕事の仕方が同じであればそういうことになる。そういう場合は安宅産業入社早々の僕がやったように仕事のやり方を抜本的に変えなくては駄目だ。ゼロベースで考えればそんなに難しいことではない。 (節子) その通りだけど、その場しのぎの体質が染みついている普通の日本人には難しいんじゃないかしら? それに30歳代の人は20歳代初めの人の教育に手こづるといったような問題もあるみたいよ。どうしてこうなってしまうのかしら? (高哉) 個を埋没させることに役立った日本モデルの賞味期限が切れてしまったことが次の図式に結びついたからだと思う。 (日本的集団主義の強い影響を受けてきた ⇒ 物事を深く考えない習性が根付いた) + 性格と歴史的立場無知の状態が放置されている ⇒ 何かあっても自動応答的に対応しがちとなった ⇒ 性格・性差・立場から生まれる違いを認める習慣は醸成されようがない ⇒ 価値観の壁にぶつからざるを得ない ⇒ 円滑なコミュニケーションはできようがない。 仕事のやり方を抜本的に変えることを困難にしているその場しのぎの体質。30歳代の人が20歳代初めの人の教育に手こづる問題 ── この二つの出所は同じなんだ。 こういう状態が長く続けば、溜まるストレスは限界を超えてしまう。この先には、ガン、動脈硬化などの血管疾患、人格障害、うつ病が待っている。どうなるかは体質次第だけどね。 (節子) 先の見えない状態の下で疲労困憊になってしまえば、ガン、動脈硬化などの血管疾患や人格障害になる。そうならなければ、うつ病になってしまう。・・・・・頑張り続けてきた人が突如としてうつ病になることがあるそうだけど、どうしてなのかしら? 管理職になったような事情がなくてもよ。 (高哉) 脇目を振らずひとつの仕事をしていると、「押して駄目なら引いてみる」といったような発想ができなくなり、次の図式にはまってしまうからだと思う。 (頑張り続けてきた ⇒ 行動がパターン化される) + 厳しい競争社会の中に置かれるようになった ⇒ 頑張って限界を打破しようとする ⇒ 限界が打破できない状態が長く続く ⇒ ストレスが溜まり続ける。 (節子) 昔の農村社会のような環境であれば、頑張り続けてきた行動がパターン化されても問題はなかったけど、今の世の中では厳しい生存競争がある。その上、先行きがどんどん不透明になるので、ストレスが溜まり続けるのは仕方がないかもしれない。・・・・・フリーターが「やるべきことをやっているのに自己責任だと言われても困る」と言ってうつ病になることが少なくないそうだけど、これも同じことね。どうしたらいいんのかしら? 変な言い方だけど、臨機応変力を臨機応変に再構築できればいいんでしょうけど。 (高哉) IT業界のような変化の激しい業界に身を置けば、貴女が言ったようなことが可能になるように思うかもしれない。しかし、実際はそうではない。というのは、次の図式が待ち受けていることが多いからだ。 技術の変化が激しい ⇒ 優勝劣敗が明確になりやすい ⇒ 成果主義の人事考課を行わざるを得ない ⇒ 脳力に不安があると、いつも怯えていなければならない ⇒ ストレスが溜まり続ける。 ということは、どんな時代になってもどんな仕事についても必要性が増す一方となる創造的問題解決力やコミュニケーション力を身に付けて、新技術を身につけた人を使いこなすことができるようになることが一番だ。そうすれば、泰然自若としていられるようになり、力強く生き抜け、かつ不安や怯えを寄せ付けないようになるからね。そういうことで強く勧めているのが新創業なんだ。
(節子) 「人生目標実現手段としての管理業務位置づけ」や「新創業」という貴方のこれまでの説明を聞いて「なるほど」と思ったけど、心に響かなかった。その理由に今気がついた。異分野の開拓に成功した経験のある人でないと、貴方の提案は通用しにくいんだと。平凡な人生を歩んできた人には実践にすぐ役立つやり方が必要と思う。どうかしら? (高哉) 前向きの姿勢を持つことができれば、「環境適応のために新思考を採用する ⇒ 記憶の再編成が自ずと進む ⇒ 新職務に相応しく脳細胞間の円滑なネットワーキングができるようになる」となる筈と思ったから二つの提案をしたんだ。 (節子) 新しいことへの挑戦に慣れていないと、そうはうまくいかないわよ。管理職には「部下を通じて成果を出さなければならないので、自分のペースで事が運ばない」という特殊性があるんだから特にそうよ。脳力革命に成功した貴方と違って殆どの人は実質的社会主義体制にどっぷりつかって生きてきた。こういう人には荷が重いのよ。 (高哉) 貴女の言う通りだ。管理職になってうつ病になるのは、ナアナアやその場しのぎの人生を送って来たので、臨機応変力の源である脳内シソーラス機能と海馬が鍛えられていないからだ。この根本にメスを入れずに前向きの姿勢を持たせるだけでは問題は解決しない。こういう人には ─────
の2段階の作業を行い、管理者になってもストレスが溜まらず脳力進化を実感できるようになる秘訣と同様に「仕事に追われる」から「仕事を追う」人生に転換することを強く勧めたい。就いている仕事の究極の目標値を追い続けることが「仕事を追う」人生であることは言うまでもない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||