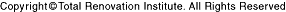![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528 FAX: 03-3773-6082 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(節子) 年金制度を一本化して財源を税金にシフトさせることを頑として許さない。こういう対決姿勢を貫こうとしてる民主党に軍配が上がるんじゃないかしら? (高哉) 国家財政が破綻しなければね。破綻してIMFの管理下に入ってしまえば、民主党の考えていることは夢物語となってしまうよ。日本がIMFの管理下に置かれれば、国家財政の帳尻を合わせることだけを考えて歳出カットを徹底的に行うようになることを忘れてはならない。 このように言うと、「財政再建をしさえすれば大丈夫ね」という声が聞こえてきそうだけど、こういう考え方だけでも年金不安は消えない。財政を再建して年金の財源を税金にシフトさせるだけでは駄目な大問題があるんだ。 現行の年金制度の大前提が様変わりしてしまっていることを皆忘れてしまっている。1947年の平均寿命は50歳ちょっと。ところが、今や82歳を超えている。このような状態の下で次のようなことが発生する可能性が極めて高いことを考えなければならない。
(節子) その上、引退者を支えることができない働き手が増えているのよね。600万人が年収200万円そこそこ。したがって、毎日の生活で精一杯で健康保険ですら払えない。年金なんてとんでもないのよね。 (高哉) 社会保険庁の解体や新歳入庁の創設が年金問題の切り札であると考えるとしたらとんちんかんの極みであると言うしかない。 (節子) だから大都市と過疎化が進む地方社会の両方で有効な対策として新・公共事業を提唱したんでしょ? (高哉) そうだけど、この新・公共事業を行ってもまだ足りない。定年制の大幅延長どころか生涯現役社会の実現を真剣に考えなければならないだろうね。
(節子) 生涯現役社会の実現なんて普通の人にとっては夢のまた夢よ。貴方がある会合で定年間際の人物に「人間は棺桶に入るまでは分からない」と言ったら、手を握り締めながら「よーし」とつぶやいた。ところが、何年か後に再会してその事を言ったら「挑戦しようとしたけど、どうしても身体がついていかなかった」という返事が返ってきたという話だってあるじゃないの。 (高哉) 問題の根本的原因を抉り出し取り除くことを考えれば、どんなことにだって打開策は見つかるものだよ。簡単に諦めないで生涯現役社会の実現を阻む原因を一緒に考えてみよう。原因は大きく分けて二つある。脳力・能力が中年に達すると衰えてしまうこと。これが第1の原因。脳力・能力が加齢に応じて強化されても適切な仕事に就くチャンスがないこと。これが第2の原因。 (節子) 脳力・能力が中年に達すると衰えてしまうことがないようにするためには、脳力のピークは80歳代だ!にあるような人生を送らなければならない。このように言いたいんでしょうけど、こういう人生を送るのは容易ではないわよ。というのは、倒産・リストラ・配置転換が付きまとうので、本人にチャレンジの意欲があってもそれが許されないことがあるからよ。この問題をどう考えるの? (高哉) 受身の人生しかないんだったらそうだけど、現実はそうではない。人生はその気になればいくらでも切り開くことができる。ギブ&テイクの度重なる転職が夢見ていた脳力獲得に結びついた具体例やアルバイトから大企業に伸し上がった例だってある。 (節子) 例が極端だわよ。普通の人生を普通に送ってきた人でも「だったら自分でもやれそうだ」となるような例でないと、説得力に欠けるわよ。 (高哉) 日本的集団主義が生み出したその場しのぎの弊害を貴女の反論に感じるね。過去の延長線上だけに人生があると考えるとしたら、大間違いだよ。人間は潜在能力のほんの一部しか使っていないことに気がつかなければならない。(必読のコンテンツ ⇒ 『誰だって発展性のある独自の脳力・能力を潜在的に持っている』/『シナリオを緻密に描いて目標を設定しよう』/『成長分野に成功裡に進出する秘訣』) (節子) 視野狭窄症、ひいては拘禁服着用症にわざわざ罹り、自分の可能性を極端に狭めてつまらない人生を送ることになってしまっている人がほとんどである。そうならないためには、個性的才能を引き出す性格診断を受けなければならない。このことを改めて強く再認識できた。 と言いながら変だけど、ひとつだけ反論させてくださいね。経済成長によるパイの拡大がなければ、成功者は所得を拡大させ、そうではない人は所得が縮小してしまうんじゃないかしら? 経済のパイを拡大し続けるうまい方策はないのかしら? (高哉) 他社や社外の人とのタイアップを考えずに自社だけで新規事業をやろうとする。こういう考え方にしがみつく。いいかえれば、社会を構成する人々が自分の勢力圏を拡大することだけを考える。多くの企業や人がこういう状態を続けていたら「収穫逓減の法則」が働いて経済成長はいずれ限界に達する。こうならないようにすれば経済のパイを拡大し続けることができるようになる。 (節子) その説明は納得できる。「自給自足経済から物々交換経済になった ⇒ 一人一人が生産性を拡大するようになった ⇒ 社会全体に余裕が生まれた ⇒ 僧侶のような生活の糧を稼がない職業が生まれた ⇒ 天文学や科学技術が発展した」という図式を思い出しなさい。こう言いたいんでしょ? (高哉) ピンポン! 大当たりです。蛸壺からネットワーク型社会に転換すれば、永遠の経済成長を可能にする秘訣を手に入れることができるようになるんだ。そういう意味で、日本モデルが崩壊するのは歴史的必然性があると言える。 (節子) ネットワーク型社会への転換が経済のパイを拡大し続けることに結びつくことはよく分かったけど、どうすればいいのかしら? (高哉) 南米はワーキング・プアーが沢山いることで知られているけど、チリがそういう状態から突出する形で抜け出している。チリは生活保護ではなく粗末ながらも住居を提供するだけではなく、ミシンを買い与え、受注支援を行って裁縫で食べていけるようにする。このように自営業が営めるような支援を行っているようなんだ。 (節子) 大都市と過疎化が進む地方社会の両方で有効な対策としての新・公共事業でもそういうことをするといいわね。 (高哉) そのための共同作業場を建設することも考えられるよね。ネットワーク型社会への転換のための大掛かりな対策としては僕が提唱し続けているをケインジアン・マネタリアンを糾合できる斬新な経済政策を推進しよう!の趣旨を生かしたことを実行して欲しい。但し、この政策の実行が実りあるものにするためには、個性的な才能を持っている人を輩出しなければならない。ここにも、個性的才能を引き出す性格診断の必要性があるんだ。
(節子) 雇用機会は工夫次第でいくらでも増やすことができることは分かったけど、高齢者に有利になり、かつ生きがい増進につながらないと生涯現役社会の実現に結びつかないんじゃないかしら? 高齢者ならではの仕事でないと、若者の方がついつい選ばれてしまう。それから、苦痛を伴う仕事であると、「毎日が日曜日の生活の方がいい」となってしまうわよ。 (高哉) 「仕事は生活の糧を稼ぐ手段に過ぎない」という考え方に凝り固まったままでいれば、そういうことになるだろうね。しかし、「性格に合った仕事に就く ⇒ 好きこそものの上手なれの世界に入ることができる ⇒ ポスト小泉改革の重要課題にある数学者のようになる人の輩出が進む」という図式を実現させれば、話は違ってくるんじゃないかな。 このように言うと、「例が極端すぎる」という批判が生まれるかもしれない。もしそうだとしたら、自信がなく読書嫌いであったにもかかわらず、明確な目標を持って勉強し続けるようになったといったような例もあることを思い出して欲しい。 (節子) 大勢の日本人が好きこそものの上手なれの世界に入ることができれば、財政再建は可能になりそうね。だって、次の図式が実現できるわけだからね。
これって凄いことだと思う。「好きこそものの上手なれの世界に入ることは自分のためだけではなく財政再建にも結びつくんだ。だったら迷うことなく好きこそものの上手なれの世界に入ろう!」となるようになるような説明を理路整然としてくださらないくれないかしら? (高哉) お安い御用だよ。生涯現役の人生を歩む人が増えることは次の図式の実現に結びつくからね。 加齢に応じて脳力・能力の強化が進む人が増える ⇒ 成長が見込める新しいサービス事業の開発が容易ではないということがなくなっていく ⇒ 日本経済は拡大均衡路線を歩むことができるようになる。
(節子) 「競争なくして経済成長なし、経済成長なくして国民福祉の向上なし」ということで改革が進められてきた。そのお陰で日本経済は長い停滞から脱して成長路線を歩むことができるようになった。しかしながら、二つの大きな問題が残された。
この二つの問題解決策として次の三つがクローズアップしたわけだけど、これだけでいいのかしら?
(高哉) 共同体の再構築で気をつけなくてはならないことがある。グローバリゼーションの中で生き抜くためには もたれあい関係を復活させてはならない。そのためには、次の図式の実現が必要になる。 自分の性格と由来を認識する ⇒ (性格に振り回されたために酷い目に遭ったり、幸せを掴みそこなったことを認識する + 性格に振り回されそうになることに気がつくようになる) ⇒ 「幸せを壊したくない」「もっと幸せになりたい」という本能が作動する ⇒ 性格に振り回されないようになる ⇒ 現実直視力が強化される ⇒ この世の中を生き抜くためには何をすべきかが分かるようになる ⇒ 自分にはどんな能力が不足しているかが分かるようになる ⇒ 社会横断的人的交流を通じて足らざるを補う努力をするようになる。 (節子) 再構築される共同体は従来のような閉鎖型ではなく開放型を目指さなければならないというわけね。 (高哉) ピンポン! 大当たりです。共同体はオープンリソース経営を取り入れながら再構築されなければならないんだ。 (節子) ということは終身雇用制度は崩壊の一途を辿るということかしら? 社会を安定させるためには終身雇用制度を残す工夫が必要だと思うんだけど。 (高哉) 終身雇用制度は貴女のお望み通りに力強く復活するんじゃないかな。但し、年功序列ではなく能力主義に基づく人事が行われるようになると思うけど。 (節子) 上司と部下が入れ替わるようなことを多くの日本人が受け入れるかしら? 受け入れざるを得ないとしても人間関係がぎくしゃくしてしまうような気がするわね。 (高哉) 上司と部下が入れ替わることが指揮の低下に結びいてしまうのは、自分が携わっている仕事が好きで好きでたまらない。そういう状態ではないからだと思う。自分が携わっている仕事が好きで好きでたまらない状態になれば、上司が誰であろうとそんなに気にならないんじゃないかな。但し、自分の仕事振りにけちを付けられないようにするためには、次の図式の実現が必要になると思う。 経験を積むにつれて力がどんどんついていく ⇒ 個人の自由裁量権を拡大する ⇒ 上司が細かいところまで干渉しないようにする。 各人が性格に合った仕事に就くことが年功序列ではなく能力主義に基づく人事を根づくことに結びつくというわけさ。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||