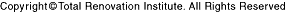![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性的な需要。これが新成長機会です。豊かだが深く深く潜在しているのです。したがって、洞察力が必要です。企業が成長の限界に達したり、新たに起業することが難しいのはこの洞察力が不足しているからです。(補足説明 ⇒『洞察力はやり方次第で短期間に身につくものです』) どうしたら洞察力が身につくのでしょうか? 知識を豊かにするだけでは駄目です。現実を直視して総合的に判断する脳力が必要です。「現実を直視してだって。そんなことは簡単なことだ」となるでしょうか? 残念ながら「否」です。「気がつかなかった」と後で臍を噛むことが多いのが何よりの証拠です。 後悔先に立たず。このようになってしまうことが多いのはどうしてなのでしょうか? 横並びや無思考の融通無碍の生き方をしていることが感覚麻痺に結びついているからなのです。 ここまでの説明を読み、お気づきになったことでしょう。そうです。新成長機会に逸早く気づくことを妨害している真犯人は日本の伝統的な社会なのです。なぜなら、日本的集団主義にどっぷりと浸かり続けることが横並びや無思考の融通無碍の生き方を染みつかせることに結びついているからです。
開発目標が適切であるかどうかに自信が持てない。資金、仕入れ網、販売網、ブランド力がない。── こういったようなことを理由に「事業化のアイディアはあるのだが…」と嘆くことが少なくないのが産業界の実態です。この世の中には足らざるを補ってくれるリソースは必ず存在するにもかかわらずです。開発目標を適切にしてくれる人材だって例外ではないのです。 上記のような状態にどうして陥ってしまうのでしょうか? 日本的集団主義の影響を受けて社会が閉鎖的になってしまったままだからなのです。(具体例 ⇒『日米のビジネス・パーソンの行動の際立った違い』) この閉鎖性は資金の流れをも停滞させたことにも結びつきました。その結果、日本経済は長期低迷を余儀なくされたのです。(詳しくは ⇒『金融資本の本来のあるべき姿』)
新成長機会を洞察する力が身につき、かつリソースの臨機応変の調達に便利なネットワーク型社会が実現できれば、念願の企業力はぐーんとアップするのでしょうか? 残念ながら「否」です。なぜなら、日本的集団主義の影響を強く受けた人生を送り続けると、「無思考の融通無碍の習慣が染みつく ⇒ 周囲の状況に合わせてころりと変節しやすくなる」という図式に嵌り込み、ひいては下記いずれかの状態になってしまうのが一般的な姿だからです。
サラリーマンが定年退職をすると途端に人が群れなくなることが少なくありませんが、この理由は上記のことを考慮に入れるとなんとなく分かるのではないでしょうか。そうです。「個性的な魅力がない + 組織の拘束がないので無責任になりかねない ⇒ 敢えて付き合いたいとは思わない」という図式がさっと脳裏を掠めるからなのでしょう。これは鶏が先か卵が先かとという問題と似ています。なぜなら、「自分もそうだから他人もそうだ」と思っている人が多いからです。
小泉改革政権の目玉のひとつであった地方分権の風向きがおかしくなってきました。マスコミで報道される事情もあるでしょう。しかしながら、ほとんどの人は根本的原因に気づいていないようです。中央集権を確立した(廃藩置県に踏み切った)のはなぜなのか? 地方分権体制(道州制の導入)が必要になったのはなぜなのか?── を考えてみる。これが根本的原因をきちっと認識するための早道です。
各藩の財政赤字は平均して収入の3倍に達していた ⇒ 各藩個別の合理化による財政再建は不可能であると認識された ⇒ 行政機能のスケールメリット追及の必要性が認識された──、という図式のなせる業だったのです。
国・地方自治体の両方が財政破綻状態に陥ってしまった + 民間部門が育ったために国営事業の必要性が大幅に減った ⇒ 官から民に事業主体を移すことが決断された──、という図式があるだけではありません。工業化が限界に達しているグローバリゼーション時代における日本の発展策をも考慮に入れなければなりません。
財政再建がメインテーマですが、明治時代とは違って事は単純ではありません。グローバリゼーションと工業化の限界を考慮に入れた財政の再建が必要だからです。 企業力を阻害している真の要因を取り除いて日本を拡大均衡路線に乗せるしかないでしょう。大いなる実験です。この実験を成功させたために地方分権があるのだ。こういう考え方が必要なのではないでしょうか。 この考え方をよしとするのであれば、地方分権を梃子に用いた「拠点開発 ⇒ 水平展開 ⇒ 垂直展開」という新規事業開発の鉄則を適用したいものです。 このようなことを実行できる地方社会が存在するでしょうか? 現段階ではほとんどが「否」でしょう。なぜなら、10年近く行い続けている『国民の構想力を強化する 』『母産業都市機能を拡散させる 』や数年前からの『広域を一体的に捉えた再開発が必要である』等の提案に対してほぼ無反応なのです。 言われがちな「日本人の多くは鳥かごが取り払われたにもかかわらず飛び立とうとしない」は地方自治体の責任者にも当てはまるのです。 このような状態で地方分権に踏み切ることは財政を更に悪化させることに結びつきかねない。だから、地方分権の風向きがおかしくなってきたのではないでしょうか。「明確なビジョンを追って生きている人間は野放ししても大丈夫。しかし、そうではない人を野放しにすることは危険極まりない」という経験則があることを忘れてはならないのです。
日本的集団主義が新成長機会に気づきにくくしていることを知って、「社会構造の問題だから…」と諦めるしかないのでしょうか? そんなことはありません。皆さんの日常生活のことを思い出してください。現実を直視して問題解決に取り組むのではなく、現実を回避して安易な道を選んだり、伝言ゲームのような悪しき知覚プロセスに陥ってしまうことが多いのではないでしょうか。 上記のような状態にどうして陥ってしまうのでしょうか? 染みついた癖であり、人の行動力学になっている性格に振り回されてしまうからなのです。「性格がどうして?」と思われる方は「性格が邪魔して…」というよく聞かれるぼやき、「無くて七癖」という格言を思い出してください。 「社会構造の問題だから…」と諦める必要は全くないことを以上の説明から理解されたのではないでしょうか。そうです。性格に振り回されないようにすれば、新成長機会に逸早く気づくことができるようになるのです。あれこれを結びつけて総合的に判断できるようになるためには、それなりの訓練が必要になりますが…。(必要な場面の具体例 ⇒『大きな隙間市場のイメージ』) 性格を乗りこなせるようになる効用は上記したことだけに留まりません。「取引相手の性格を正しく認識する ⇒ 取引相手の行動力学を正しく認識する ⇒ 全ての交渉事が円滑化する」という図式に結びつくことを忘れてはなりません。 政府が実現を目指している機会平等社会が日本人一人一人の羽ばたき実現に直結するわけではありません。高速道路が敷けたことが快適なカーライフ実現に直結するわけではないのと同じことです。車と免許証の入手という自助努力があって始めて敷けた高速道路を使った快適なカーライフが実現できるのです。 同じようなことが日本人一人一人の羽ばたきについても言えます。そうです。彼我の性格を正しく認識することによって始めて機会平等社会を享受できるようになるのです。(関連記事 ⇒『仏に魂を入れなければならない』) 但し、性格を乗りこなせるようになりにくい人がほとんどであることを肝に銘じる必要があります。なぜなら、 「日本的集団主義の影響を強く受けている ⇒ 個を抑制して生きてきた ⇒ これまでの生活のリズムが乱されることを極度に嫌う」という図式に嵌っている。これが圧倒的大多数の日本人の実態だからです。 上記の図式に嵌っている人は性格を乗りこなせるようになることを諦めなければならないのでしょうか? 「否」です。変身の円滑な誘導に結びつくカルチャー・ショックを受ければ大丈夫です。(具体策 ⇒『ワタナベ式問題解決へのアプローチ』)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||