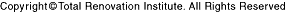![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528 FAX: 03-3773-608 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小泉首相が改革に協力してくれそうな閣僚を各派閥に相談することなく独断で一本釣りした(できた)のはどうしてなのでしょうか? 理由は二つあります。 (理由1) 破綻寸前の財政を再建する等首相は強力な指導力を発揮しなければならなくなった 国政運営は過去の延長線上を歩めば事足りる ⇒ 伝統的な和と共存の精神を大事にできる ⇒ 中央官僚と直結した族議員を抱える派閥のバランスの上に立った国政運営を行う──、という図式が通用しなくなったのです。 (理由2) 小選挙区制が導入されたために派閥の力ががくんと弱くなった 「中選挙区制である ⇒ 党よりも派閥への忠誠の方が強い ⇒ 総裁(首相)はリーダーシップを発揮しにくい」から「小選挙区制である ⇒ 派閥よりも党への忠誠の方が強くなってしかるべきである ⇒ 総裁(首相)のリーダーシップが発揮しやすい」となっていたのです。 しかも、選挙民の実態は「与党・自民党3割、野党3割、浮動票3割」から「浮動票(無党派)5割」になりました。適切な政策の下に国民を糾合できる政権党並びに首相誕生の条件が整っていたのです。
小泉首相が伝統的なコンセンサス手法を採らなかったのはどうしてなのでしょうか? 下記の図式に嵌ってしまうことを防止するためだったのでしょう。 総務会で各人各様の意見を聞く ⇒ 合理よりも人間関係重視主義に引っ張られる ⇒ 郵政民営化法案の骨抜きが進む。のみならず、実行が遅れる。 小泉首相の英断を「許し難い独裁政治である」と痛烈に批判した造反組に思い出して頂きたいことがあります。 前述したように日本が濁流に飲み込まれるように悲劇の太平洋戦争に突入してしまったのは、名実ともに国政の最高責任者であった昭和天皇並びに宰相であった東条英機首相が下記の図式に嵌っていたからです。 合理よりも人間関係優先の生活を送り続けてきた ⇒ メリハリなく融通無碍に生きてきた ⇒ 丸投げの習慣が染みついてしまった ⇒ 不戦体制堅持の仕組みを思いつかなかった。
地域社会が国会議員を擁立してきたのはどうしてなのでしょうか? 「中央集権体制が確立された ⇒ 中央は地方の事情に疎くなる」という図式に歯止めをかけるためだったのでしょう。それなりのメリットがあったのです。ところが、この方式はメリットよりもデメリットの方が大きくなってきました。下記の図式を読んでください。そうすれば、「なるほど」と思われることでしょう。 日本の社会には人間関係を重視する垂直的民主主義が根づいている + 中央が地方に交付金を支給する ⇒ 国会議員と地域社会が癒着した ⇒ 国会議員は中央官庁と選挙民の間に立つブローカーになってしまった ⇒ 官主導の政治が行われるようになり、競争のない官僚社会が腐敗してしまった & 地方独自の発展力を殺いできた ⇒ 国と地方の財政が破綻してしまった。 時代は「政策立案あるいは検証・肉付けのできる政治家を選出する ⇒ 国会議員は地方と中央を仲介するコーディネーター・コンサルタントになる ⇒ 巨視的観点に立った地方発展力を育成する ⇒ 国と地方の財政の再建が進む」という図式の実現を求めているのです。
上記の例1・2・3はしがらみのない一匹狼ならではの離れ業ですが、豊富な人脈に支えられた基盤がないにもかかわらず大きな仕事を小泉首相は成し遂げることができました。どうしてなのでしょうか? テレビを駆使して単純明快なメッセージを国民に幅広く伝え続けることが功を奏したからでしょう。「どうして?」と思われる方は二つの図式の存在を認識することにより「なるほど」と納得されるのではないでしょうか。 図式1 : 自民党一党独裁時代は終わった ⇒ 浮動票(無党派)5割を惹きつけなければならない ⇒ 国民に分かりやすく面白い政治にしなければならない ⇒ マスコミを最大限活用しなければならない。 図式2 : 視聴者は心に余裕がない上に氾濫する情報の中で生きている ⇒ 視聴者には情報のインプットを妨げるバリアーができている ⇒ 視聴者の心にすとんと入り込む、鮮烈にして単純明快なメッセージでなければこのバリアーは突破できない。 「小泉劇場型政治」「ワン・フレーズ・ポリティックス」と揶揄した挙句に「このようなやり方は賞味期限が切れた」と言っている評論家諸氏は「合理よりも人間関係優先の生活を送り続けてきた ⇒ メリハリなく融通無碍に生きてきた ⇒ 性格に振り回される習慣がノンチェックで作動してしまった ⇒ 環境の様変わりに気づかない」という図式に嵌っているのでしょう。 世の中の動きを鋭く見抜くことができさえすれば、支持基盤がなくても大事の成就は可能である。このことを小泉首相は証明してくれたのです。(小市民的な立場での証明例 ⇒『新規事業開発成功に必要な理論的条件が完備していた』) 但し、選挙民が全体を知ることなく賛否を決することから生まれる危険を除去するためには、「ワン・フレーズの意味を解釈する人を発掘する or 育てる ⇒ ワン・フレーズの意味を解釈できる人をコーディネーターに用いた公開討論会を開催する」ということの実施が必要であるのは言うまでもありません。(理由 ⇒『あるべき世論形成も容易ではない』)
前述の例1・例2・例3並びに一匹狼でも大きな仕事ができることを示したこと。これらは様変わりした環境に適応して幸せな人生を送るための貴重な教訓を残してくれています。
小泉首相が派閥順送り人事を無視して適材適所の閣僚人事を断行した。これは大事を決断・決行する時は下記の図式に身を置くことが必要であるという教訓を与えてくれています。 自分の性格を識別する(自分の行動力学を識別する) ⇒ 自分の性格に振り回されないように注意する(自分の行動力学に振り回されないように注意する) ⇒ 見過ごすかもしれなかった環境変化を認識した適切な行動を採ることができる。
小泉首相が郵政民営化法案を党内審議不十分なまま国会に持ち込んだ。これは大事を決断・決行する時は下記の図式を反面教師にしなければならないという教訓を与えてくれています。 合理よりも人間関係重視主義に引っ張られる ⇒ 性格に振り回される習慣がノンチェックで作動する ⇒ 現実を直視することなく大事を決断・決行する ⇒ 悲劇に突入する。 悲劇の未然防止よりも人間関係を優先させる。こういう馬鹿げたことが日本の社会では横行しがちであることを肝に銘じなければならないのです。
自民党本部が独自に国会議員を擁立する。こういう方式を採用したのは英断だったのです。「地域社会に縁もゆかりのない人物を送り込んで…」という批判は「合理よりも人間関係優先の生活を送り続けてきた ⇒ メリハリなく融通無碍に生きてきた ⇒ 性格に振り回される習慣がノンチェックで作動してしまった」という図式から生まれたものなのです。
一匹狼でも大きな仕事ができることを示した。これはエスタブリッシュメントが「成功し続けてきた ⇒ 行動の自由を奪い取る習慣が染みついてしまった ⇒ 性格に振り回される習慣がノンチェックで作動してしまった ⇒ 現実を直視できなくなってしまった 」という図式に嵌ったために生じた間隙を突いたが故に可能になったのです。 これは弱者や持たざる者にとって福音です。なぜなら、下記の図式が待ち構えている時代になったからです。 (先行きがどんどん不透明になる ⇒ 市場ニーズが変化しやすくなる) + (エスタブリッシュメントは存立基盤の侵食に結びつく行動を採ることを避けたがる ⇒ エスタブリッシュメントは変化する市場ニーズへの適応が遅れがちとなる) ⇒ 需要と供給にギャップが生じやすくなる。 但し、上記の図式が生み出す大きな隙間市場を掴み取るためには、「性格に振り回される ⇒ 視野狭窄症や拘禁服着用症に罹る」とならないようにしなければならないのです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||