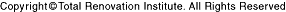![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 04-7138-5421 〒277-0886 柏市西柏台2-3-1 柏ハイライズ106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで紹介する事例はインターネットや出版物に基づいての推理結果であってクライアントを診断したものではありません。クライアントから知りえた情報が新創業研究所から具体例で洩れることは一切ありません。ご安心ください。
(節子) 「東京裁判は間違っていた」「自衛隊の存在を憲法の中に明記すべきだ」とする日本人が増えてきているようだけど、この背景に何があるのかしら? 国際社会の中における日本人は今どんな状態になっているのかを知りたいの。詳しいことは次回の議論に譲るとして簡単に説明してくださらないかしら? (高哉) 貴女が今言った主張をする日本人が増えてきたのは、ストレス発散手段としての間違ったナショナリズム高揚が次の二つの図式から生まれたからではないかと思う。 ●図式1:(なし崩し的な決定に慣れている日本人にとって東京裁判はドラスティックなものになった ⇒ 日本人の変革に必要な内生変数が優先されなかった ⇒ 東京裁判の結果は国民的コンセンサス形成に程遠いものになってしまったので、 国民にもやもや感が残ることとなった) + 対米追従一辺倒であった日本は経済的苦境やサラ金経済に陥っているだけではなく北朝鮮問題で誤解があったとしてもアメリカから裏切られた思いをさせられた ⇒ 国民はストレスを貯め込むに至っている。 ●図式2:創造的統合戦略が欠如している ⇒ 総理大臣は日本再生のグランドデザインを提起できない。のみならず、国民を糾合できる形で優先順位をつけて政策を実施することができない ⇒ 国民はストレスを貯め込むに至っている。 (日本人の変革には内生変数を優先させることが必要な場合が多いことを深く理解するための参考資料 ⇒ 『米国の宿命的な体質である“外生変数重視主義”とは何なのか? どうしてこのような体質になったのか?』) 太宰治の自殺や厚生省元次官宅連続襲撃・殺害という悲劇は人生を総括することなくもやもやした心理状態を引きづり続けていたことに原因があった。このことの本質は「東京裁判は間違っていた」「自衛隊の存在を憲法の中に明記すべきだ」とする日本人にも当てはまるかもしれない。 (節子) 安倍元首相が拉致問題の解決にこだわったのは、だからなのね。というのは、拉致問題の解決は「日本の政治は捨てたもんじゃない」となり、このことが日本人の政治に対する信頼の回復に、更には日本国への求心力回復に結びつく可能性があるから。・・・・・アメリカのブッシュ政権が日本の頭越しに北朝鮮をテロ支援国家の指定から外したのはどうしてなのかしら? (高哉) アメリカはこの決定を下す前に日本政府が拉致問題を独自に解決するために一年の猶予期間を与えた。ところが、日本政府は何もしなかったそうだ。これが事実とすれば、この問題でアメリカ政府を非難することは筋違いということになる。
(節子) 日本政府が拉致問題を独自に解決しようとしないのはどうしてなのかしら? 何か深い理由がありそうね。 (高哉) 日本人が常套手段にしがちな問題先送りも影響していそうだ。というのは、次の図式が考えられなくもないからだ。 横田めぐみさん達の救出が国民を自民党に惹きつけるための重要な手段になっていた ⇒ 横田めぐみさん達が死亡しているような事態は自民党にとって受け入れがたい ⇒ 日本政府は拉致被害者の実態調査に乗り出しにくい。 (節子) 横田めぐみさん達の救出が国民を自民党に惹きつけるための重要な手段になっており、これにしがみついていたとすれば、情けない話。こうならないために、安倍元首相は前回の議論で紹介されたような政策を推進しようとしたというわけね。・・・・・この政策が国内外で受け入れらなかった深い事情があったことも考えられそうだけど、どうなのかしら? (高哉) 中国もアメリカも日本独自の外交を展開できることに結びつくようなことになることを阻止しようしたこともあるんじゃないかと思う。というのは、アジアでの覇権国家になることを目指している中国は日本が軍事力を抜本的に強化して外交力を持つことは困る。アメリカだって日本が忠実な子分的な存在であり続ける方がに何かにつけて都合がいいだろうからね。 (節子) 国内だけではなく外国の利害が絡んでくるので、安倍さんの思い通りにはいきにくいことがよく分った。熟した柿がぽとりと落ちるような対策を講じることが現代社会のリーダーの要諦であるということの教訓となる。権力基盤が弱かったにもかかわらず思い通りのことをやってのけたローマ初代皇帝アウグストゥスの知恵に学ばなければ駄目ね。
ここに熟した柿がぽとりと落ちるような対策を可能にする創造的統合戦略の必要不可欠性があるわけだけど、これだって問題解決の突破口が見つかって初めて効果が生まれると思うの。今議論している問題の日本にとっての突破口は何かしら? (高哉) アメリカが北朝鮮との二ヶ国間協議を拒絶してきた理由を考えぬけぱ、突破口は自ずと見つかるんじゃないかな。 (節子) クリントン大統領時代に二ヶ国間協議をして騙されたからでしょ? この背景に北朝鮮はアメリカにとって遠い国であることがある。そういうことで北朝鮮の近隣諸国との協調が必要となったんでしょうね。 (高哉) そういうこともあるけど、もっと大事なことがあるんじゃないかな。前回の議論で言った「北朝鮮だけではなく六ヶ国協議参加国の全てが北東アジア総合開発の動機を十分に持っている」には「同時に六ヶ国の協力が必要不可欠である」という言葉を付け加えないといけない。特定国だけではなく北東アジア全体の開発だからね。 (節子) 北朝鮮の経済開発を強力に進めるためにはある意味で義務化している日本の大型経済支援が欠かせない。但し、そのためには国民的コンセンサスが必要となる。米朝二ヶ国間協議では日本人は反発してこの国民的コンセンサスの形成は困難になる。ここに前回の議論で貴方が提起したシナリオの意義ある。したがって、安倍元首相の対北朝鮮の姿勢は正しかったと言うしかない。 しかしながら、さっき言った中国とアメリカの対日姿勢があるので、事は簡単ではない。これをどう考えればいいのかしら? (高哉) 日本が持ちつ持たれつつの関係になれるロシアと友好な状態を創り上げることがきわめて大事になる。というのは三つの効果を生み出すことが可能になるからだ。
但し、北朝鮮を個人に見たて性格と立場を見抜くようなことをせずにお人よし丸出しの外交だと日本の国益は大きく損なわれるようなことになることに留意しなけばならない。アメリカにだって同じことが言える。オバマ大統領の核廃棄宣言から生まれたシナリオが幸いしそうだから良かったけどね。さもなくば、次の図式になるところだった。 アメリカは北朝鮮を個人に見たて性格と立場を見抜くことができなかった ⇒ 北朝鮮に“飴”を与えれば何とかなると思った ⇒ 北朝鮮は強硬姿勢を採ることによって有利な立場を勝ち取ることができると思った ⇒ 北朝鮮は09年5月25日に06年10月に続いて二度目の核実験を前回の四倍の爆発規模で行うようになった。 (節子) ロシアとの関係強化は目立たなかったけど、安倍元首相の外交姿勢は素晴らしかったというしかないわね。にもかかわらず、挫折してしまったのはどうしてかしら? 「着眼は実に良かったのだが…」という御定まりのコースになってしまったにあること以外で説明してくださらないかしら? (高哉) 単純化して言うと、戦後レジームからの脱却が「官僚依存体制からの脱却 = 官僚の活躍の場の剥奪」というイメージに結びつき、官僚体制を敵に回すことになり、「内政面でも外政面でも根回し欠如 ⇒ 政策の空回り」となってしまったんだと思う。
(節子) 道州制の是非はともかくも脱中央集権の担い手は中央官僚である。いいかえれば、中央官僚は地方官僚に転身できる。このことを大きく打ち出せば、官僚体制を敵に回すことはなかったんでしょうね。でも、これだけでは国民は戦後レジームからの脱却を優先的課題とは認めようがない。この点はどうかしら? (高哉) 日本経済が経済的苦境やサラ金経済に陥っている背景には単純化すると、次の図式がある。「小泉・竹中改革が悪いんだ」とする意見は問題のすり替え以外の何物でもない。 工業化が限界に達したにもかかわらず、日本の企業は過去の延長線上を歩むことに慣れ切っている ⇒ 日本企業の殆どは成長の限界に達している。しかし、生き抜かなければならない ⇒ コストダウンと低損益分岐点経営に活路を見出すことになった ⇒ 企業の体質は脆弱になり、ワーキングプアーも輩出されることになった。 民間に任せるだけではこの図式からの早期脱却は困難。政治が出番の時代になった。ところが、日本の政治は歴史的役割を果たすことができていない。この背景に『国家中枢を頼みにしたいがままならない』で述べたようなことがある。こういう状態が放置されたままでのSNSや異業種交流会はコップの中の嵐みたいなものだ。この状態を正すのが戦後レジームからの脱却である。この中身はかくかくしかじかであるとすべきだったんだ。 (節子) かくかくしかじかはこのホームページに詳しく載っている。個人が努力すべきはプロフェッショナルへの道を歩むことよね。それはそれとしてさっき言った「外政面でも根回し欠如 」ってどういうことかしら? (高哉) 『冷戦終結後の国益を大きく左右する外交力を確立しつつあることを認めなければならない』にあるようなことは日本人にとっては歓迎できることだけど、アメリカ離れの印象を持たれ、アメリカの反・安倍に結びついたことは否定できないんじゃないかな。こうならないためには、「シミュレーションを徹底的に行う ⇒ 脳のシソーラス機能を充実させる ⇒ 適切な説明を臨機応変に行う」という図式を実現すべきだったと思う。 (節子) 交渉を成功させるためには構想力・独創力が必要不可欠。だから、今回の議論の表題になったのね。同じことが世界経済の牽引者になった中国に対する態度についても言えそうなので、聞きたいことがある。次の図式のようになることが心配なの。 (特定国が急速に力をつける ⇒ 保ってきた世界の秩序が乱れる ⇒ 既得権益を守ろうとする動きが生まれる) + (急速に力をつけてきた国にはそうならなかった時代に貯め込んだ鬱積した欲求がある ⇒ 急速に力をつけてきた国に気負いが生じる) ⇒ 国際紛争が生じる。 (高哉) 貴女の言っていることはこの問題に関する限りは杞憂になるんじゃないかな。というのは遠隔地から核施設をピンポイントで攻撃できるハイテク兵器がある。その上、次の図式は可能性だけではなく実際に実現されたからだ。 世界的規模での未曽有の経済危機に襲われた + 拡大した貧富の格差はパイの縮小の下では大騒乱に結びつく ⇒ 内需拡大政策を採ることとなった。 でも、貴女が気づいたことは「こうしたらこうなる。こうなるとこういうことが新たに発生する」という発想を適切に行うことの必要性を具体的に示したもので複雑時代を生き抜くための要諦だと言える。このことを経済の担い手である企業関係者に強調したい。というのは、世の中が複雑になっているにもかかわらず短絡的な思考・行動を採るから所期の成果が得られず、企業が深刻な業績不振に陥ることが少なくないからだ。 こうならないためには、企業はコンサルタント登用のあり方を見直さなくてはならない。億単位の巨額の費用を投じたコンサルティングや役割が曖昧な顧問に訣別して、大局観に裏打ちされた斬新な着眼の持ち主の指導の下に現場を担当しているビジネス・パーソン個々の問題を創造的に解決することの必要性を強調したい。 こういうことを言う背景には日本企業の国際競争力強化のあり方の抜本的見直しの必要性がある。(関連記事 ⇒ 『新時代のビジネスモデル』) ここに、『ビジネス・クリニック』の意義があることを強調したい。── 安倍元首相の性格と歴史的立場とその影響の分析は以上で終わりです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||