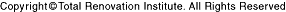![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで紹介する事例はインターネットなどの公開情報に基づいての推理結果であってクライアントを診断したものではありません。クライアントから知りえた情報が新創業研究所から具体例で洩れることは一切ありません。ご安心ください。
(節子) 安倍元首相が造反議員の復党を認めたことをどう解釈したらいいのかしら? 小泉改革によって自民党の支持基盤は弱体化し、党内は分裂気味。こういう状態であれば、和と共存を実現させたい性格の持ち主としては党内の融和を図ろうとするのは当然だと思うんだけど。 (高哉) 迷いに迷った挙句に「思い切って復党を認めよう!」となったんだと思う。小泉元首相が主導する郵政民営化を官房長官として全力で支えたからには造反議員の復党を認めるわけにはいかない。しかし、安倍シンパが多い造反議員を復党させたい思いも強かったはず。というのは、「援軍が増える ⇒ 自分の求心力が強化できる ⇒ 自民党内の和と共存を実現させやすくなる」という彼の性格に合ったシナリオが考えられたとしても少しもおかしくなかったからね。 (節子) 結果は失敗だったわね。参議院選で歴史的大敗を喫したんだから。2007年に改選期を迎えた15人のうち9人は事前の世論調査で勝てないと分ったので候補から降ろされてしまった。6人が選挙を戦って、当選2人、落選4人となってしまったのよね。 そして、海外の日本離れが始まった。これをどう解釈したらいいのかしら? 自民党が参院選で大敗を喫したことが日本離れに結びついた。いやそうではない。海外の日本離れが始まったことが自民党の参院選大敗に結びついた。こういう二つの意見があったんだけど。 (高哉) 小泉構造改革が進みかけたこと並びに自民党が参院選で大敗を喫したことに対する海外の投資家の評価を考えれば、自ずと回答が得られるんじゃないかな。 (節子) 小泉構造改革が進みかけたとき株価がぐんと上昇した。この背景には「日本の閉鎖性の打破が進む ⇒ 新しい成長の芽が育ちやすくなる」という判断があった。一方、自民党が参院選で大敗を喫したとき株価ががくんと下がってしまった。この背景には「ねじれ国会になる ⇒ 必要な政策が実行されにくくなる ⇒ 日本の閉塞性の打破が進まない ⇒ 新しい成長の芽が育ちにくくなる」という判断があった。こういうことなんでしょうね。 ということは、二つの意見はいずれも正しいが、いずれも核心を突いた説明が欠如している。こういうことになる。こういうことと安倍元首相が造反議員の復党を認めたことどういう関係があるのかしら? (高哉) 安倍元首相が造反議員の復党を認めたことは彼の政権に致命的な打撃を与えることに結びついたと思う。これを単純化して図式すると、次の通りになるんじゃないかな。 ( 安倍元首相が造反議員の復党を認めた ⇒ 対立軸がなくなった ⇒ 改革反対論が出なくなった代わりに賛成論も出なくなった ⇒ 歴史の長い保守性が歴史の短い革新性を凌駕する印象を国内外に与えた ⇒ 株価が下落した ⇒ 国民は自民党政権に不安を抱くことになった) + 政治とカネ、閣僚の失言、社会保険庁の年金問題が連日のようにマスコミを賑わした ⇒ 国民の自民党離れが急速に進んだ。 (節子) 強烈にして新鮮な印象を与え続けないと、 古い殻を破って革新的なことをやり遂げることができない。自民党の参議院選での歴史的大敗はこのことを示す見本みたいな話ね。安倍さんがこんな大事なことに気づかなかったのは性格無知のまま総理大臣になってしまったので、次の図式を実現できなかったと言うしかないわね。 安倍さんが大目標を掲げる ⇒ スタップが大目標の実現に結びつく緻密なシナリオを創る ⇒ 安倍さんがこの緻密なシナリオ実現のための後ろ盾や調整役になる。 (高哉) 安倍さんのような性格の持ち主は価値観の多様化時代における貴重な存在だけに彼の挫折は実に惜しまれる。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ではなく、「自分の性格を知り、長所を生かし短所を補うタイアップをすれば百戦危うからず」という教訓をしっかり身につけて再起してもらいたい。 前回の議論に出てきた「安倍内閣の強権的な政治手法が露骨になってきた」「安倍首相のタカ派的な体質が顕著に出てきた」という致命的な批判は適切さを欠いていると思う。さっきの図式が実現できなかったことがこういう現象になっただけのことだ。他人の性格と置かれた立場を適切に認識して長所活用だけを考えなければならない時代になりつつあることを認識しなければならない。(必読コンテンツ ⇒ 『だから逆転勝利の可能性があるのだ』) (節子) 昨年の暮れから今年の初めにかけての安倍さんの自民党内における行動は長所として受け止めるべきなのかしら? 麻生前首相の盟友でありながら党内における反麻生の急先鋒である中川秀直元幹事長らでつくる新議連「生活安全保障勉強会」に出席。町村派の総会後、中川さんや町村さんに対し「消費税を政局にする余裕はない」と付則の文案修正を持ちかけた。こういう一連のことを指しているんだけど。 (高哉) 党や所属派閥の分裂回避のための行動は和と共存を重んじる安倍さんらしいと思う。短期的には長所として受け止めることができる。しかし、足して二で割るやり方は過去の延長線上を歩める時代ではなくなったので長期的には通用しない。内需拡大の決め手になる相続税の抜本的強化を視野に入れた日本経済を再生に導く緻密なシナリオを創らなくては駄目だと思う。 この事実だけを判断する限り、安倍さんは政権に就いた頃と比べて大きく成長したとはとても言えなかった。そういう意味で短期的にはともかくも長期的には性格発の衝動強迫に相変わらず支配されていると言えるんじゃないかな。彼が再起するための最優先課題は『重大な環境変化があると落とし穴にはまり、深刻な状態になる仕組み』であることを肝に銘じることだと思う。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||