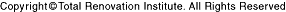![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで紹介する事例はインターネットや出版物に基づいての推理結果であってクライアントを診断したものではありません。クライアントから知りえた情報が新創業研究所から具体例で洩れることは一切ありません。ご安心ください。
(節子) 前回の議論の最後に「彼は性格が原因してか思考性の強い人物のようだ。ここに焦点を当てた役柄を演じれば、日頃の思考結果を反映できるので、適切な方向で“好きこそものの上手なれ”の世界に入ることが生み出す効用が入手できるようになるかもしれない」と貴方が言ったことは凄く大事だと思う。この言葉の持つ意味を考え抜けば、映画俳優以外にも彼の活路が見つかるような気がするの。こういうことに納まるように詰めさせてもらえないかしら? (高哉) 前回の議論の最後にあるように「踊るなんて死んでもできない」と言ったことが示すように裕也君は硬派の人間。一方において寂しがり屋。 ── この二つの整合的な解釈から始めなければならない。 (節子) 母親が留守がちであったことと彼の性格が結びついて、二つの図式を生み出したんじゃないかしら?
これだけでは、映画俳優以外の彼の活路の発見には結びつけにいくい。何を追加して考えればいいのかしら? (高哉) 貴女は裕也君のことを大分前の議論で「自分の意見を率直に述べたい気持ちが鬱積している」と言っていたじゃない。このことを考えればいいんじゃないかな。 (節子) 「硬派的なアイデンティティが醸成されていった」は格好をつけたい想いに、「独りでは寝られないほどの寂しがり屋になった」は仲間に自分のことを知ってもらいたい強烈な想いに、それぞれ結びつく。「自分の意見を率直に述べたい気持ちが鬱積している」という背景にはこういうことがあるのね。となると、自分の意見を率直に述べたい気持ちは凄まじいばかりの衝動強迫。その上、彼の性格は思考性を厭が上でも高める。こういうことになるのかしら? (高哉) ピンポン! 大当たりです。貴女が今言ったようなことがあるから彼は自分自身のことを「自分の気に食わない現実を理論づけして目をそらしてしまう」と評しているんだと思う。これは「嫌な癖の持ち主」とマイナス点になるのではなく、「貴重な素質を持った人物」とプラス点になる癖だ。 (節子) そのように考えれば、ある意味で恵まれなかった彼の生い立ちはプラスに転換できるわね。というのは、次のような図式化が可能だから。 (独特の性格の持ち主である + 甘やかされて育った ⇒ 母親の愛情が結果として大幅に不足することとなった) + 事実は見方次第でどうにでも解釈できる ⇒ 譲ることのできない空想の世界ができあがりやすくなった ⇒ 自分に都合の良い精神的な居場所を探す ⇒ 自分の主張を何としてでも通そうとする想いが強くなる ⇒ 自分の主張を通すための斬新な着眼が生まれやすい ⇒ 視野が広くなれば、交渉の達人になる。 子供のころ“お山の大将”だったことは交渉の達人の兆であると解釈できるわね。価値観の多様化した子供の世界ではコミュニケーション能力があるかどうかがリーダー的立場に立てるがどうかの決め手になっているようだから。・・・・・でも、彼は視野の広い人物になれるかしら? (高哉) うまく誘導すれば大丈夫だと思う。というのは彼の性格は「世の中の本質を見抜く ⇒ オリジナルな意見を述べる」という衝動強迫に結びつきやすいからね。冴えた議論をしたがることや立派な大人の話を聞くのが大好きだった少年時代の逸話が何よりの証拠だよ。 (節子) 彼は30歳近いのよ。間に合うかしら? 間に合うとは思うけど、背中をぽんと押すような何か激励の言葉ってないかしら? (高哉) その気になりさえすれば、十分間に合う。大文豪であった故・井上靖の旧制中学時代の恩師から次の話を聞いたことがある。高校1年の時という随分昔のことだけどね。 浪人して旧制沼津中学に入学。三高も浪人して入学。大学を卒業した後、ぱっとしない新聞記者だった彼は40歳を過ぎてから気が狂ったように小説を読み耽るようになった。そして、しばらくしてから小説を書くようになった。 40歳を過ぎてから気が狂ったように小説を読み耽るようになった原因は定かではないけど、“好きこそものの上手なれ”の世界に入ることの重要性を物語っていると理解すべきだと思う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||