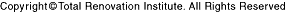![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学の姜尚中教授は「日本の基軸はアジアに置かなければならない。したがって、日米同盟は必要不可欠であるとしてもその関係はアジアの中に留まるべきである」といったようなことを繰り返し主張していますが、この主張は正しいでしょう? 「否」であると言えそうです。理由は次の通りです。
アジアとの関係強化はグローバリゼーションの一環でなければならない理由は上記したことだけではありません。下記の図式もあるのです。 (交通・通信手段が発展してきた ⇒ 遥か遠い外国との交流が容易になった) + (日本経済が生き抜くためには脱工業化を進めなければならない ⇒ 個性的なニーズに対応しなければならない ⇒ スケールメリットを追求できないので、商圏が広ければ広いほど好都合になる) ⇒ 日本はアジアをも含めたグローバリゼーションの推進が必要になる ⇒ 「アジアの中で生きていかなくてはならない」という強迫観念に駆られる必要性は大幅に低下する。 但し、「グローバリゼーションを更に推進しなければならない」と思うだけだけでは駄目です。産業構造をエンドレスに高度化できるだけではなく、日本人は偏狭さを改めて価値観の違う人々とも円滑に交流できるようにならなくてはなりません。(詳しくは ⇒『違いを認めることができる日本人を輩出しなければならない』)
日本がアメリカ同様にグローバリゼーションを一層推進することは対中国関係の希薄化に結びつくことを懸念するかもしれませんが、この懸念は当たらないでしょう。逆になることでしょう。この理由を説明しましょう。
(理由1) 韓国、引き続いて中国との間で先の大戦についての責任問題については決着がついている。(詳しくは ⇒ 日韓国交正常化条約 / 日中国交正常化条約) 但し、喉から手が出るほど必要としていた日本の経済協力を得ることを急ぐあまり後日紛争が生じる下記のような火種が残されました。
(理由2) A級戦犯の14人が靖国神社に合祀(ごうし)された後に靖国神社を参拝した大平首相に対して中国側は非難しなかった。 靖国参拝に中韓両国が反発するのは、1978年に東条英機元首相らA級戦犯の14人が「昭和殉難者」として靖国神社に合祀(ごうし)されたからです。 特に中国政府は日中国交回復の際、かつての日本軍による中国侵略は「一部の軍国主義者によるもので日本人民は被害者」と自国民に説明した経緯があります。したがって、A級戦犯が祀られている靖国神社に首相が参拝すればその説明が崩れ、日中友好の根拠を失うととらえています。しかしながら、この合祀の後に大平首相は靖国神社を参拝した。にもかかわらず、この行為に対する非難の言葉がなかったのです。中国には一貫性がないのです。 (理由3) 各国の相互依存の度合いが深まった現代社会においては各国は内政問題であっても他国に対しての配慮が必要である。 「日本の首相が靖国神社を参拝する ⇒ 中国と韓国の国民の反日感情が高まる ⇒ 両国の経済にマイナスの影響を与える」となるのであれば、日本の首相の行動は慎重でなければなりません。しかしながら、日本には日本の事情があることをも両国は理解しなければなりません。(中韓両国が理解すべきこと ⇒ 『危急の時は例外措置が許されてもいいのではなかろうか』)
(理由1) 複雑な国際問題は暫定的に決着されるのが通例である 中国本土とではなく台湾と賠償金ゼロの講和条約を締結したが、この背景には 「東西の冷戦が始まった ⇒ アメリカは日本をアジアのショウ・ウインドウにすることを決心した」というご都合主義があった。 きちっと総括しないご都合主義はこれだけではありません。日本からの経済協力を急いだために紛争の火種を残したまま締結した1965年の日韓国交正常化条約、1972年の日中国交正常化条約も同様でした。 しかも、日中国交正常化条約では上記講和条約の締結相手である台湾を独立国として認めず国交断絶が謳われたのです。 (理由2) 基本の基本であるサンフランシスコ講和条約ですら連合国が一致して調印したものではなかった 日本の国際社会への復帰並びに日本の独立を認めるサンフランシスコ講和条約が1951年に締結されました。しかしながら、先の大戦における最大の被害国であった中国は招待されなかったし、招待されなかったソ連は参加したものの条約への調印を拒んだのです。 (理由3) 押し付けられた憲法に反する行動ですら要求された実績がある 日本の平和憲法はアメリカ側が創ったものです。にもかかわらず、東西冷戦、朝鮮戦争といった国際情勢の大きな変化が発生したために、アメリカは自由陣営の一員である日本の再軍備を強く迫ることとなった。このことが自衛隊の発足に結びついた。 (理由4) 極東軍事裁判の結果に反する行動を戦勝国側からの特別の咎めを受けることなく採った実績がある 極東軍事裁判の否定に結びつくA級戦犯の14人が靖国神社に合祀された。にもかかわらず、戦勝国側からの特別の咎めがなかったようなのです。
上記「2段階の事情」があるにもかかわらず、小泉首相の靖国参拝を契機に日中並びに日韓の外交関係が冷え切ってしまったのはどうしてなのでしょうか? 両国の国内事情があることの他に二つのことがあるからなのでしょう。
どうすればよいでしょうか? 「国民レベルでの人的交流を拡充する⇒相互理解が深まる ⇒ お互いに盲点に気づくようになる ⇒ ウィン−ウィンの妥協が成立する」という図式を辿る必要があります。機が熟すのを待つ必要があるのです。 にもかかわらず、国政の指導者が現段階で「私はこうすべきだ」と発言したならばどういうことになるでしょうか? 盲点が残ったままであるので、神経を逆なでされる人が両国から多数生まることでしょう。そして、上記の図式実現にマイナスになることでしょう。 日中は融合せざるを得ないので、現段階では余計なことはしない方が良いのです。適切な方向で仕事をしようとしている人間に対しては叱咤激励するよりは暖かく見守る方が良いのとの同じことです。 歴史認識を強く求められるのであれば、「後世の歴史家の判断に任せる」と回答する。これが最善ではないでしょうか。 したがって、安倍官房長官が採り続けてきた「先の大戦をめぐる歴史認識のあいまい戦術」に対する著名な専門家、与野党の大物政治家、政府関係者並びに一流紙新聞の非難は軽率のそしりを免れることはできないでしょう。 このようなことを申し上げますと、筆者のことを安倍さんの関係者であると受け取られかねませんが、そのような事実は全くありません。日本の未来を憂う者として客観的な意見を述べただけのことです。
以上述べたことを総合的に勘案すると、日中首脳会談が年内あるいは来年早々に行われ、下記内容の協定が締結される可能性が大です。
「小泉政権がアメリカの言いなりであった」という根拠のひとつに牛肉の輸入問題が取り上げられています。誰だってBSUの牛肉は食べたくありません。しかしながら、輸入許可の条件は「100%問題なし」といったような趣旨の要求は正しいでしょうか? 非難を承知で言います。「否」です。ひとつひとつに完璧を期することは現実的ではない。これが理由です。このことを分かりやすい例で説明しましょう。 気温が氷点下になっても凍らない道路を建設することは技術的には可能です。なぜなら、「凍り始めたことを感知する ⇒ 熱湯が流れる」という順序の仕事を自動的にこなせるような仕組みを道路の直ぐ下に埋め込みさえすればよいからです。 但し、上記のような仕組みを備えた道路を全国的に敷設したらどうなるでしょうか? このことだけで国の予算は使い切ってしまうかもしれません。そこで、登場したのが一定の予算の下で国民福祉を最大にするための適切な予算配分です。 このように言うと、「でも、BSUの牛肉は命にかかわるから道路と同じ扱いにはできない」という反論が出るかもしれません。この反論は正しいでしょうか? 「否」です。なぜなら、国民の生命に関わることは他にも沢山あるからです。ここで必要になるのが、上記したことと同じ適切な予算配分なのです。この適切な予算配分のことを分かりやすい例で説明しましょう。 何事も完璧を求める人がいました。この人はひとつひとつを納得できるまで丁寧にやるために、大事なことが積み残しになりがちです。このような生き方で幸せになるのでしょうか? 「否」でしょう。なぜなら、朝食に万全を期したために大切な約束に間に合わなかった。こんなことが生じてしまうからです。BSUの牛肉についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。 BSUの牛肉に神経をとがらせるけれど、ガンを誘発する食生活を平気でする。これでは頭隠して尻隠さずです。命取りになるエイズが蔓延傾向。にもかかわらず、BSUの牛肉に神経をとがらせる。こんな日本の社会はおかしいのではないでしょうか。 それに北米産の牛肉は食べないという選択肢もあります。そのために、加工食品の中身と原産地の明示を厳しく義務づける。こういうことに政治的な圧力をかけることの方が必要なのではないでしょうか。
博識の学識経験者や一流紙の論説委員でも視野狭窄症に陥ってしまうのはどうしてなのでしょうか? 理由は二つあると言えそうです。 (理由1) 社会の成熟化が“複雑骨折現象”を生んでいる 「社会の成熟化が進んだ ⇒ 生き抜くために隙間を追うようになった ⇒ 専門分野の細分化が進んだ ⇒ 全体を的確に語ることができる人が極端に少なくなった」という図式が支配的になった。その上に、知識や情報の氾濫が世界の全体を的確に語ることを困難にしているのです。(補足説明 ⇒『超高速道路ががらがらに空いている状態であなたを待っている』) (理由2) 日本の社会環境が直観力の養成を妨げている 特定の世界に生き続けると、頭脳明晰であってもついつい慣性の法則の落とし穴に嵌ってしまう。(詳しくは ⇒『変革期に必要不可欠な斬新な着眼力が日本のエリートに育ちにくい図式』) そこへ持ってきて下記の図式が加わっているのです。 日本的集団主義にどっぷり浸かって生きてきた ⇒ 深い思考を伴わないその場しのぎの習慣が醸成された ⇒ 目先の具体的なことにしか関心を持たなくなった ⇒ 複雑時代に世界の全体を語るために必要不可欠な直観力が育ちにくくなった。 「衆知を集めたり、調査を積み重ね、その結果を取りまとめる」のではなく、「総合的な知見に基づいて直感し、その結果を検証しつつ肉付けする」やり方が必要になったのです。(参考資料 ⇒『衆知を生かして複雑問題を解決するための5留意事項』) どうすればいいでしょうか? 最善策であるビジョン効果の入手の前に、下記の図式を実現させることをお勧めします。 自分の性格とその由来(自分の行動力学とその由来)をきちっと認識する ⇒ 「もっと良くなりたい。そのために努力したい」という人間の持っている本能が適切に作動する ⇒ 性格に振り回されないようになる(現実直視力が抜本的に強化される) ⇒ 深い思考を伴わないその場しのぎの習慣からの脱却が進む ⇒ 個の確立が進み、もたれあいの習慣がなくなっていく ⇒ 自己責任の観念が強くなり、「思考の三原則」(全体を見る/長い目で見る/根本的に考える)適用の必要性を痛感するようになる ⇒ 直観力の強化が進む。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||