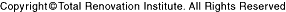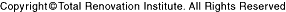|
岸久さんが世界最高峰のバーテンダーになれた秘訣 |
(節子) 「複雑問題解決の秘訣であるジグソーパズル思考とは無縁の人が殆どだが、指導層も例外ではない」には納得できた。しかし、「臨機応変の枠外思考を可能にするモーツアルト効果 が得られるような人生を歩んでいなくても未来を切り開くことが可能だ」となるような話をして頂けないかしら?
「陳腐化した枠内思考から脱却しないと生き抜くことが困難な時代になった」が当てはまらない場合もあることを認識しないと、うつ状態になってしまう人が増えてしまうと思うの。
(高哉) 各種カクテル・コンベンションで全日本大会で5回優勝し、第21回世界カクテル・コンベンションでも優勝している、世界最高峰のバーテンダー「岸久」さんの話をしよう。「カクテルの色や香り」「味わい」「飾りの美しさ」「ネーミングセンス」「創作性」など、ありとあらゆる角度から優れたカクテルを審査するのが全日本大会だそうだから「適切なジグソーパズル思考力が永遠の成長を可能にする」の具体例になれる存在だ。
(節子) 店は薄暗くても、カウンターの向こう側ではバーテンダーが振っているシェーカーに光が集まり、キラキラと輝きます。そして、でき上がったカクテルを飲む時は、なんだか背筋をピンと伸ばさないといけないようなそんな緊張感すら感じます」と言われているそうね。
こういう見本があるんだから腕に自信のあるバーテンダーだったら模倣・凌駕できる筈。ところが、そうではないから何度も優勝している。どこに秘訣があるのかしら?
(高哉) 寿司にとってのシャリに相当する氷に対するこだわり方が良い例になる。納入された大きな氷を単に砕いて使うようなことは決してしない。氷塊に入っている、よく見ないと分からない裂け目の箇所を「そのままカクテルに使うと、シェークしてできるバブルが理想的状態にならない」と言って削り取ってしまう。こだわりはそれだけではない。
来店初の客がカクテルを飲む様子を物陰から観察、少量しか味わっていないと、支払いをすませる前に、満足が得られるように残りを調整し直す。そして、店外でも「もっともっと」の精神で試行錯誤を繰り返している。とにかく研究熱心。努力継続力の塊でなければ、こんなことはできない。
(節子) 接客好きが旺盛なサービス精神を生み出しているのかしら? 接客好きでないと、貴方がよく言う「サービスの質はサービスの提供者と享受者の協力度合いによって決まる。これがサービスビジネスの本質」に適合できないと思うの。
(高哉) 彼は接客業に向いた性格ではないので、若い時に大変苦労したそうだ。にもかかわらず、世界最高峰のバーテンダーになれたのは、「味で勝負しよう!」と決心して、さっき言ったような精進を続けてきたからだ。
(節子) 「接客業に向いた性格ではないので、若い時に大変苦労した」となると、職業を変える人が多い。彼がそうならなかったのはどうしてかしら?
(高哉) 学生時代にレストランバーでアルバイトをして、カクテルを創る面白さにはまり、バーテンダーの道を歩み続けてきたので、年齢的にもつぶしが効かなくなり、「味で勝負しよう!」と決心。そのうち、「繰り返しの快」を味わうようになったからじゃないかな。
(節子) 「今の立場を適切で好きな道にすれば、どのような世の中になっても楽しく生き抜くことができるようになる」の見本になる良い話ね。
|