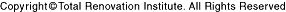【斬新な着眼】

 負けても堂々と再出発できる時代がやってきた
― ヤオハングループ元会長・和田一夫氏の近況から考える〈2000/10/16〉 負けても堂々と再出発できる時代がやってきた
― ヤオハングループ元会長・和田一夫氏の近況から考える〈2000/10/16〉
 敗者復活が困難であった仕組み 敗者復活が困難であった仕組み
減点主義が社会全体に行き渡っている。したがって、失敗者は冷遇されがちである。ところが、所属集団を離脱すると、生きて行くのが困難になるので、新天地での再起もままならない。
以上が日本の伝統的な社会の仕組みでした。だから、敗者復活が困難だったのです。
「時代が変ったので、敗者復活が容易になった」と言いきるためには、次の疑問に答えなけれぱなりません。
 |
減点主義がどうして社会全体に行き渡ったのか?
|
 |
所属集団からの離脱がどうして生きていくことを困難にしてきたのか?
|
模倣や「カイゼン」が可能である限り、試行錯誤を伴いがちな独創をする必要はありません。そこで、独創本能を封じ込めるために、減点主義がほぼ社会全体で採用されることになったのです。減点主義は経済合理追及の手段だったのです。
欧米先進国へのキャッチアップを効率的に進めるためには、国民がばらばらの行動をしないようにする必要があります。指導者以外はロボットのように行動してくれなくては困るのです。
かくして採用されたのが、「政官財のトライアングル体制」、終身雇用制度、系列取引
── この三つ等からからなる「長期コミットメント体制」なのです。このような国民総囲い込み体制が主な原因となって、日本におけるベンチャー企業の発展が阻害されてきたのです。
「何か新しいことを始めても、どこからか邪魔が入ったり、巧妙にそっくりと真似されてしまう」ということが言われがちでしたが、この背景には上記したことがあったのです。一匹狼やアウトサイダーを徹底的に排除する。これがこれまでの日本だったのです。
これまでの日本は所属集団を離脱すると生きて行くのが困難だったのです。こういう場合であっても、集団間の競争がきびしくなければ、集団間の連携プレイは行われます。ところが、現実はそうではなく、集団間の競争は激烈でした。
わが国の集団は他の集団の応援を求めることなど考えず、すべて自前主義を貫こうとする。この傾向が強くありましたが、この背景には、上記した事情があったのです。
(新規事業に乗り出す際に、足らざるを外部から補う習慣が欠如しているために、失敗してしまう企業が少なくありませんでしたが、この背景には、この自前主義があったのです)
このような日本の社会は個人や企業間の臨機応変のタイアップを行う「ネットワーク型社会」とは程遠い「蛸壺(たこつぼ)型社会」である。このように表現できます。
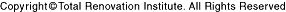
|
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)
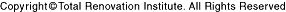
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)