![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 03-3773-6528/3777-5189 〒143-0023 東京都大田区山王2-7-13 山王パレス407 |
||||||||||||||||||||||||||||
【世界の出来事から問題解決の方法を学ぶ】
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8. ユーロ効果を学べば不況から脱出できる企業改造を急ぐか、それとも座して倒産するかアメリカを結節点とし、かつ共産圏との交易は限定的。これが東西冷戦構造時代の実態であった。しかも、わが国は共産主義の侵食を防ぐためのアジアのショーウインドー的な役割を担わされていた。したがって、わが国企業は競争なき競争場裡で経営を行うことができた。言ってみれば、保護された状態の下で高度成長を謳歌できたのである。 そして、東西冷戦構造の終結。わが国企業は大競争の海原に投げ出された。理論的にそうであった。ところが、実際はぬくぬくとした環境の下での経営が可能であった。なぜなら、わが国経済社会には、規制・系列取引・実績主義・人間関係優先主義が色濃く残存していたからである。したがって、わが国の市場は相変わらず閉鎖的であったのだ。 そこで、わが国経済社会に市場原理を浸透させるために採用されたのが、アメリカ政府の意向を組み入れた金融ビッグバンなのだ。ところが、景気回復の見通しが立たない。このような状態で金融ビッグバンが強力に推進されると、企業倒錯の嵐が吹きかねないので、やむを得ず採用されたのが、公的資金の投入を柱とする企業の救済策なのだ。 但し、この救済策はいつまでも続けるわけにはいかない。資金には限りがあるからだ。この限界を超えて資金を投入しようとすると、長期金利が上昇してしまうことは周知の事実である。 ユーロ効果は企業改造のあり方を示唆するそこへ登場したのがユーロ誕生である。ユーロ誕生はヨーロッパ先進国の企業の創造力と競争力の強化に結びつく。現状路線を歩む限り、わが国企業は後退を余儀なくされるのである。ユーロ誕生の影響はそれだけではない。他地域の共同市場の形成、そして、通貨統合を通じて、徹底した自由競争に結びつく、世界経済のボーダレス化が一段と進むのである。 東西冷戦構造の終結・金融ビッグバンの実施・ユーロ誕生の影響の三つが重なったので、前述した企業救済の時間切れの時期にはすさまじいことが待ちうけているのである。21世紀を生き抜くための改造を怠った企業は間違いなく淘汰されるのである。 それでは、わが国企業はどのように改造を進めればよいのであろうか。ユーロ誕生がもたらした、あるいは確実にもたらすであろう効果に貴重なヒントがある。「ユーロ効果」を踏まえて、二つのことを前述したことを思い出していただきたい。ひとつは次の通りであった。 中庸の挑戦機会を与え続ける。そして、ノルマには厳しいが、行動の自由がある社風を創る。そして、ノルマ実現を支援する体制が整っている。このようなことを実現しさえすればよいのだ。実り豊かな挑戦機会を前途に示し、社員一人一人を自立させる。自立した一人一人は自律しなければならないので、構想力・独創力の強化に勤しむ。但し、マイナスの効果をもたらした日本的経営があまりにも長く続いたので、構想力・独創力の強化を企業として支援しなければならない。(こういう目的のために適切なコンサルタントを登用することを真剣に考える必要があろう)このように、上記の「ユーロ効果が与えてくれた経営のヒント」を受け止めるべきであろう。 「ユーロ効果」が与えてくれた、もうひとつの経営のヒントは次の通りであった。 未来から眺めて、自社が守り強化する得意技術を発見あるいは確認して、この得意技術を梃子に使い、この得意技術の強化に結びつくことを可能ならしめる、欧米企業との積極果敢な提携を行うことである。前途に提示された実り豊かな挑戦機会を認識し、壮大にビジョンを策定する。その中に、社員一人一人は未来進行形の得意技を発見あるいは確認すると共に、足らざるは外部のタイアップで埋める。上記「ヒント」をこのように拡大解釈すべきであろう。 「ユーロ効果」の企業経営のあり方へのヒントは上記したことに留まらない。通貨も統合した真の共同市場は、域内経済のパイの拡大を実現するのみならず、過剰生産の抑制にも結びつくのであった。真の共同市場の実現は企業内の完全なネットワーク化と言い換えることができる。そして、ネットワーク化はリソースの有効利用を可能ならしめ、収益の拡大に結びつくのである。 以上の「ユーロ効果」から掴んだ経営のヒントを総括すると、次の通りである。人間の自信の源は徒手空拳でも世の中を切り開くことを可能ならしめる構想力・独創力。このような能力があるが故に自立できる社員を輩出しなければならない。個を解放しなければならないのである。 実りある挑戦機会を示し続け、社員の個の解放を動機付ける。そして、社員の構想力・独創力強化を支援し、社内外のリソースをネットワーキングするための体制を整備する。これが経営者の役割である。
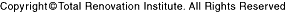 | |||||||||||||||||||||