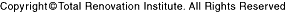【世界の出来事から問題解決の方法を学ぶ】

 ユーロ誕生と企業経営 ユーロ誕生と企業経営
5. "共同市場"別の"固定相場制"が根付いていく
共同市場の形成は途上国のみならず世界を救う
アジアはドル経済圏となって、共同市場への道を歩む。このように前述したが、なぜ共同市場なのか。そして、共同市場のゴールとも言える通貨統合がなぜドル経済圏となることによって実現しなければならないのであろうか。この2点をアジアの立場に立って説明する。
西ーロッパは共同市場構想を発表しただけで、経済開発が進み、経済が活性化し、長年にわたる停滞から脱することができことは周知の通りである。なぜこのようなことが可能となったのであろうか。この辺りの事情を図式化して説明すると、次の通りである。
貿易は遠隔の国の間でよりも、近隣の国の間で行われがちである。こうい経験則がある上に、近隣諸国間の間で共同市場が形成されると、この共同市場に参加しない遠隔地域からの輸出は困難になっていかざるを得ない。だから、共同市場構想がアナウンスされただけで、他の地域からの直接投資が拡大するのである。
共同市場構想の発表による投資拡大は域内からものだけではない。共同市場の実を挙げるためには、ボーダレスな経済活動を支援する交通や通信などの社会資本整備が必要になるので、この面の投資も拡大する。採算が取れなければ、いくら必要であっても、投資は行われないが、共同市場は社会資本整備のペイオフにも結びつくのである。
新たに敷設される社会資本の利用頻度が高いことが保障される。経済開発が進むが故に、この社会資本を利用する企業や住民のコスト負担力が増す。こういうことが実現するからである。
企業の設備投資並びに社会資本整備が進む上に、雇用が拡大を通じて消費者の懐が豊かになるので、共同市場構想の発表は内需拡大に自ずと結びつくのである。
このような共同市場効果は発展途上国にとって垂涎の的である。ところが、昨今の開発途上国は先進国からの直接投資を呼び込むための魅力が低下してしまったことは先に説明した通りである。開発途上国に対する資本投下は直接投資の形をとる必要があるという教訓を今回の通貨危機から得たにもかかわらず。
それから、共同市場の形成が必要であることは、上記した経済効果があるだけではない。地球環境の保全と世界平和のためにも必要なのである。先進国と開発途上国の経済融合は世界経済の問題解決に結びつくと前述したが、開発途上国の共同市場形成は次のような効果をもたらす可能性があることに注目しなければならないのである。
共同市場のゴールでもある通貨統合が実現すると、ユーロランドで証明されているように、経済のボーダレス化により、域内の相互投資が進む。そして、その結果、域内の経済のパイが拡大するだけではなく、水平分業の推進を通じての過剰生産の抑制にも結びつく可能性が大なのである。
それから、共同市場の形成は政治的要請でもある。東西冷戦構造の終結は世界秩序の維持において、二重のマイナスをもたらした。たがが外れたので、前述したように、宗教や民族間の対立が噴出しがちとなった。にもかかわらず、アメリカなどの強制力が大幅に低下したので、噴出しがちな対立を収めることもできない。このことは旧ユーゴスラビア紛争を見れば明らかである。
ところで、人間関係がもつれたとき、どういう人がこのもつれを解決に導くリーダーシップを発揮できるのであろうか。価値観が同じなどの理由により、相手の立場を理解でき、相手も共感を持つことができる。しかも、活躍の舞台が広いので、紛争当事者の新しい活路を見出す力がある。こういうことができる人による説得が有効である。同じことが国同士にも言えるはずである。
そして、価値観をまったく異にする人同士が密着すると、異文化を理解し抱擁できるできる例外的人物を除いて、ろくなことはないのを多くの人が経験していることである。
以上から言えることは、世界平和のためには、文明を同じくする国同士がまとまって経済交流を行う。そして、衝突が発生したときは、同一文明内であれば、この文明のリーダーが、異文明間に衝突が起きたときは、各文明のリーダー同士が話し合いで決着をつける。こういうことが求められていると言えよう。
途上国共同市場は世界の基軸通貨を共通通貨にせざるを得ない
ユーロランドの誕生が示すように、共同市場のゴールは通貨統合。だが、アジアを例にとると、開発途上国の通貨統合はまったく見えてこない。なぜなら、ユーロ誕生の経緯から明らかなように、通貨統合を実現するためには、まず共同市場を作り上げる必要があるが、アジアの場合は共同市場形成の緒にも着いていないからである。
域内の交易を拡大するために、関税同盟を結ぶ。その上で、人の移動の自由など、ボーダレス化のための取り決めを行い、共同市場を実現する。しかしながら、為替レートが不安定であると、為替リスクを恐れ、域内の交易や直接投資は十分に伸びない。そこで、相場圏を設定し、為替レートの安定化を図る。その上で、共同市場があたかも一つの国であるかのようにマネーの出入が自由に行えるように、金融・資本市場を統合する。
しかしながら、金融・資本市場が統合できても、各国がまちまちの通貨を使っている限りは、為替の度に経費がかかるだけではなく、一物一価が実現しないので、ボーダレス化に歯止めがかかる。しかしながら、共同市場並び資本・金融市場の統合の効果により、共同市場内各国の経済体質は近似してくる。そこで、漸くのことで通貨統合に踏み切ることができる。
アジアは関税同盟すら結ばれていない。したがって、共通通貨を持つなんてことは先の先のことなのである。しかしながら、アジアのみならず世界がアジアの共同市場の形成を必要としているのは前述した通りなのである。となれば、アジアはドルを共通通貨にせざるを得ないのである。
アジアの共通通貨としてユーロではなくドルを選ぶのは、前述したように、アジアはヨーロッパよりもアメリカとの経済交流の方がはるかに大だからである。
▲トップ
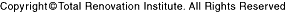
|
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)
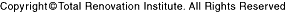
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)