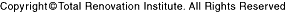【世界の出来事から問題解決の方法を学ぶ】

 ユーロ誕生と企業経営 ユーロ誕生と企業経営
3. ユーロランド政府の産業界支援力が強化される
ユーロランドの産業界の創造力と競争力が強化されることによって、ユーロランド経済は全体として成長を持続し、証券市場の拡大に伴って、株価も上昇を続ける。すると、これが影響して、経済も持続的に活性化する。こういう好循環が基調として実現するであろう。
高株価は企業のリスク負担力の拡大に結びつく。そして、インフレなき経済成長の持続は企業をして将来を楽観させ、機会損失を減らすために、供給力確保主義へと企業の姿勢を転換させる。となれば、企業は労働力を積極的に雇用するようになるであろう。
イギリスとアイルランドを除いて、つまり大陸ヨーロッパはおしなべて、過度の高福祉国家。これが産業界の活性化の足かせとなり、雇用拡大を妨げ、高い失業率になっている。そして、雇用不安の下では、この過剰福祉にメスを入れることは政治的にリスクが大きすぎるので、放置せざるを得ず、これが更に雇用拡大を妨げる。大陸ヨーロッパはこういう悪循環に陥っているのは周知の事実である。
上記した「雇用環境の好転」が実現すれば、政治的リスクなく、悪循環の源である過剰福祉にメスを入れることができよう。そして、社会保障費の削減は企業の雇用力拡大とあいまって、自然失業率の低下に結びつくであろう。なぜなら、社会保障費の削減は希望退職者の削減に、希望退職者の削減は自然失業者の削減に結びつくからである。
となれば、ユーロランドは全体としては国家財政は極めて健全なものになるであろう。なぜなら、経済成長の持続による税収の拡大に、金利水準の低下による国債の利払い並びに社会保障費の削減が加わるからである。
しかも、高株価による年金運用の妙味が増すこと、為替リスクがなくなるに等しいことの二つがあるので、ユーロランド国民の老後保障は弥が上にも増す。ユーロランドの求心力は強化されるであろう。
このように言うと、「各国の求心力が高まることはユーロランドの政治統合にマイナスになるのではなかろうか」という声が聞こえてきそうだが、その心配はなさそうである。なぜなら、次のようなシナリオの下に、ヨーロッパを横断する市民連合ができあがることが考えられるからである。
自分が所属している社会が自分のことを守ってくれない。こういうことが度重なると、人は段々と利己的になっていくものである。その意味で、日本の社会は利己主義が蔓延しつつあるといえよう。なぜなら、次のことが指摘できるからである。
日本人は情緒的であるので、理念で人を束ねるのは困難。このような国を辛うじて統合してきたのが終身雇用制度。ところが、これが崩れつつある。その上、国家財政の破綻の危険性が出てきたために、老後保障も危なくなってきた。このような状態で、「利己主義を捨て、社会全体のことを考えて行動しろ」という方が無理というものである。
ところが、ユーロランドは日本とは逆に公共精神が益々旺盛になりそうなのである。なぜなら、老後がしっかりと保証されるのを見て、国民全体が社会全体のことを考える心の余裕が生まれる可能性が大だからであるのだ。
但し、これだけでは、社会全体のことを考える場合の社会とは自分が所属する国家に過ぎない。ところが、この社会をヨーロッパ全体に広げる環境が二つできあがりそうなのである。ユーロランド内のボーダレス化によるネットワーキングの対象が拡大する。これがひとつ。もうひとつはヨーロッパの政治を席巻しつつある、各国の中道左派政権が結託して行うであろう市民運動の支援である。
このようにしてできあがるであろう、ヨーロッパを横断する市民連合の形成が、ヨーロッパ市民の利益を長期にわたって守るための、政府ならではの積極的投資を誘導しない方がおかしいくらいである。国家財政も豊かになることだし、それに冷戦構造終結により噴出しつつある文明の対立もある。
ヨーロッパ市民の福祉向上にとって不可欠な産業構造の高度化を進めるためには、市民の教育水準を絶えず上げなければならないので、その面の投資がまず積極的に行われるであろう。それから、これからの新しい技術要素は宇宙や海洋開発から生まれるが、これには莫大な資金が必要。民間企業の投資対象ではない。そこで、次にこの面での投資も行われるであろう。
単独国家か、それともユーロランド国家であるかはともかくも、政府主導で教育投資や大型の技術開発が行われることは、ユーロランドの産業界にとって大変大きな意味を持つ。なぜなら、産業界の創造力と競争力が一段と強化されるからである。
ひるがえってわが国は財政の破綻の道を歩みつつあるので、このことを十分に織り込んだ企業経営を行わなくてはならないであろう。具体的には、次のようなことが必要になるのではなかろうか。
未来から眺めて、自社が守り強化する得意技術を発見あるいは確認して、この得意技術を梃子に使い、この得意技術の強化に結びつくことを可能ならしめる、欧米企業との積極果敢な提携を行う。
▲トップ
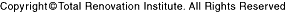
|
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)
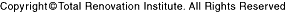
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)