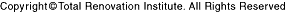【斬新な着眼】

 成長遺伝子をビジネス・パーソンに組み入れよう ― ホットな論議「小泉首相は抵抗勢力か?」から考える〈2002/3/2〉 成長遺伝子をビジネス・パーソンに組み入れよう ― ホットな論議「小泉首相は抵抗勢力か?」から考える〈2002/3/2〉
 日本人同士であっても"通訳"が必要な場合が多くなった 日本人同士であっても"通訳"が必要な場合が多くなった
それでは、小泉首相と田中前外相の溝は仕方がなかったのでしょうか。「否」です。「人間はその思いを適切に表現しきれるものではない。真意の洞察が必要である」という考え方に立った「概念拡大と論理化」手法を適応しさえすれば、溝は埋められたはずです。両氏共に〃通訳〃の才覚を持ったプレインに恵まれていなかった、と言わざるをえません。
このような"通訳"が必要なのは小泉首相と田中前外相に限ったことではありません。議論が噛み合っていないために会議を重ねても良い結果が生まれない、企業が数多く存在することが何よりの証拠です。
日本経済はほぼ一直線で成長し続ける時代が長いこと続きました。このような状態の下では思考力が鍛えられようがありませんでした。でも、「物質的に豊かになる」「終身雇用と年功序列を維持して組織の和を保つ」などの共通のスタンダードがありましたので、組織の安定を保つことができました。
そこへ持ってきての時代の様変わりです。「共通のスタンダードがなくなってしまった」「潜在していた人間の多様性が噴き出してしまった」「さりとて、思考力が鍛えられていない」となれば、毎日のように顔を合わせるような間柄であっても、お互いに理解しあうのが難しくなってしまったとしてもなんら不思議ではないのです。
ところで、田中外相の解任だけが小泉首相の人気を急落させたのでしょうか。「否」です。適切さを欠いた経済再生戦略が「資産デフレの進展⇒景気の悪化」に結びつき、構造改革批判を生んでしまったことも大きな原因になっていることを忘れてはなりません。
そこで、小泉首相の経済再生戦略の誤りを、前述の朝日新聞の社説問題についても触れつつ指摘させて頂きます。(「小泉改革」と「朝日新聞の見解」は同根なのです)
●『斬新な着眼』を無料でお届けする電子メールマガジンを発行しています。ぜひご登録下さい(無料)。
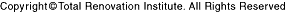
|
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)
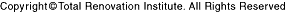
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)