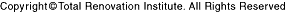![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif) |
新創業研究所 E-Mail: info@trijp.com TEL: 04-7138-5421(代表) 〒277-0886 柏市西柏台2-3-1 柏ハイライズ106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新創業研究所が掲載した数多くの有益コンテンツがGooleで第1位にランクされています |
| → トップページ |
【斬新な着眼】
![]() 練りに練った改革を大胆に行う
練りに練った改革を大胆に行う
過去のしがらみや固定観念から抜け出そうともがいている。これが日本の企業の一般的な実態です。この点、信長はラッキーでした。なぜなら、彼は尾張という国を父親から引継ぎ、本当の苦労を知らなかったからです。それでなければ、戦乱に巻き込まれて農民が苦労するような全国制覇の野望を掲げることができなかったことでしょう。
それでは、「オール・クリアー」とばかりにリセットボタンを押すごとくに改革を行えば良いのでしょうか?
「否」です。改革を進めるに際して注意しなければならないことは沢山ありますが、今日はひとつだけヒントを述べさせて頂きます。
ポーランドなどの旧共産圏諸国は冷戦終結後の改革がうまくいきました。ところが、東ドイツはそうではありません。この差はどこから生まれたのかを考える。これがヒントなのです。
東ドイツは西ドイツに占領されたがごとくに一方的に改革を押し付けられた。これが東ドイツの改革がうまくいっていない根源的な原因となっているのです。それではどうすべきだったのでしょうか?
東ドイツの人々が「心の底から改革をしたい」と思うようにして、体質に合った自前の改革案を練り上げた上で、実行すべきだったのです。
押し付けの改革ではうまくいかないのは企業の世界でも同様です。でも、自然に放置しているだけでは企業の改革はできません。だらかといって、企業独自に改革を進めようとしてもうまくいきません。なぜなら、過去のしがらみや固定観念から抜け出すことは至難の技だからです。
過去のしがらみや固定観念から抜け出せる。しかも、当事者が「心の底から改革をしたい」と思えるような改革の進め方の妙案があるのでしょうか? 実はあるのです。インサイダーとアウトサイダーの長所・短所を踏まえた方法を採用することです。 ⇒『改革を成功に導く方法』
| 2003年12月19日追記 こうすれば組織と個人の利害一致が可能になる |
| 〔信長流儀を現代経営に応用するに当って必要な五つの工夫〕 |
(工夫1) 「自分のやりたい仕事をやらせる ⇒ 創意工夫が生まれる ⇒ 知恵が生まれる」という図式を実現させる。
(但し、担当者レベルの知恵ですと、「もっと優れた知恵があるかもしれない。汎用性に欠けるかもしれない」という二つの問題が発生しかねません。ここに難問解決者役を兼ねた上司などの介入の必要性があるわけですが、部下との間に心理的な壁がありますと、この介入は巧くいきません)
(工夫2)上司と部下の心理的な壁を取り除く工夫をこらす。
入社式に顔を見せただけ、日本の大企業にはこのような社長は数多く存在しますが、製品のみで市場価値を創造する製造業ならいざ知らず、サービス業やサービスの付加が必要な製造業ではこのようなやり方は通用しません。
合理主義の国である米国にあっても、ゼネラル・エレクトロニクスのウェルチ元会長は幹部と頻繁にアルコール飲料を飲み交わすことにより臨機応変のリーダーシップを発揮しやすくしていたことを忘れてはならないのです。
(上司のリーダーシップが確立できたとしても、創意工夫の結果を記録に残せませんと、工夫2の効果は低くなります)
(工夫3) 必要に応じて後で修正可能なようにして、ネット上に担当者に業務日誌を発表させ、この業務日誌の集積結果を上司などが分析して、汎用性の高い知恵を開発する。
(激化する社内競争のことを考えますと、ライバルに塩を送ることに結びつく知恵の社内発表は形骸化する危険性が残ります)
(工夫4) 難問解決並びに知恵の補完を本人に相談した上で、迅速に行う。グループ単位の人事考課を行い、この人事考課の中に社内に発表した知恵をも十分に反映させる。
自己実現意欲の強い人材であれば、こういうことが適切に行われるのであれば、自分の開発した知恵を社内に喜んで発表することでしょう。
(自己実現意欲の強い人材が揃っているとは限らないので、工夫4があっても“敵に塩を送らない”人が出てきかねません)
(工夫5) 自己実現意欲が強い。しかも、協調性がある。── こういう人材を生み出すことに結びつくような個人ビジョンを工夫を凝らした開発がここでも必要になる。
「自己実現意欲の強い人物に協調性を期待するのはおとなしい羊に野生の虎的行動を期待するようなものである」という反論が出ることでしょう。この反論は認めるしかないのでしょうか? 「否」です。なぜなら、やり方次第では組織の利害と個人の利害を創造的に一致させることができるからです。
| 企業全体のパワーアップに結びつく、全社行事として行う幹部社員のビジョン開発 |
|
| 〔目次〕 | →次ページへ |
|
|
| 前のページへ | 目次 | トップページ |
|