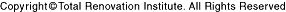製造業が低収益から抜け出す方法(その2) 〈2000/1/14〉 製造業が低収益から抜け出す方法(その2) 〈2000/1/14〉
4、事業展開シナリオを策定しよう
製造業がサービス事業を本格的に展開するためには、事業展開シナリオを予め描い
ておく必要があろう。なぜなら、次のことが指摘できるからだ。
◎波及性と成長性を確認してから投資を行う必要がある
顧客が自社製品を指名買いしてくれさえすれば、現在の事業は価格競争から抜け出
して、高収益路線を歩むことができる。但し、このような非価格競争力をつけるため
には、保証力やイメージ・パフォーマンス力などの強化が必要となる。
この保証力やイメージ・パフォーマンス力などの強化を行う際、対象となる製品の
ためだけであったら、投資はそれなりのものとなってしまう。ところが、強化される
保証力やイメージ・パフォーマンス力を利用して成長性豊かなサービス・ビジネス分
野に乗り出せたり、あるいはその他の現事業の強化に結びつくとしたらどうであろう
か。「投資のしがいがある」ということになり、思いきった手を打つことができよ
う。
商品である食品の長寿命化に迫られている企業があるとしよう。食品の長寿命化の
手段は一様ではなく、真空パックや赤外線を利用した陳列ケースの開発などがある。
選択肢の選択は思いつきで行うのではなく、「どの選択肢への投資が企業全体の波及
性と成長性に最も貢献できるか」を考え抜いた上で、選択肢の選定を行わなくてはな
らない。
波及性と成長性を確認してから投資を行う必要があるのは、現事業の強化の場合だ
けではない。新規事業開発の場合も同様だ。
納豆の製造販売を行っている企業があるとしよう。大豆をよく知っていることを利
用しての、納豆以外の大豆製品の開発。発酵技術を利用しての、バイオテクノロジー
分野への進出。この企業の新規事業開発の可能性はこの二つ以外にも様々あるはず。
言い換えれば、企業はその持てるポテンシャルの一部を使ってたまたま納豆の製造販
売を行っているに過ぎないのだ。
汎用性の高い経営資源を使った新規事業の選択肢が複数あるとすれば、自社にとっ
ての波及効果が高く、かつ成長性の高い選択肢を選定すべきであろう。
製造業がサービス・ビジネスに進出したいのであれば、顧客の交差比率を念頭に置
き、顧客の総資本利益率をよくするために行えるサービスをできるだけ数多く考え出
し、その中から自社にとって波及効果が高く、かつ成長性の高い選択肢を選定する。
こういう考え方で臨むべきであろう。
◎投資の波及性と成長性を確認するためには、事業展開シナリオが必要
現事業の強化にしろ、新規事業の開発にしろ、投資の選択肢は一様ではない。「こ
の投資こそがわが社にとって波及性と成長性が高い」という信念を持って選択肢の選
定を行うためには、経営ビジョンとその実現策、言い換えれば、事業展開シナリオを
策定しておく必要があるのだ。
このような事業展開シナリオがあれば、上記の食品の長寿命化を例にとると、合理
的な対策を採ることができるのだ。メカトロニクス分野に進出するのであれば赤外線
を利用した陳列ケースの開発を、包装資材分野に進出するのであれば真空パックの開
発を、それぞれ行うといった具合に。
それではどのようにして事業展開シナリオを策定すればよいであろうか。魅力ある
夢の事業をブレークスルー発想して設定することから始めなくてはならない。その上
で、この魅力ある夢の事業を成功裡に展開するのに必要な経営資源を抽出し、この経
営資源をアミーバ―的な事業展開を行いながら、言い換えれば、「儲かる布石」を打
ちながらとりこむ。この考え方を例示すると、下記の通り。
現事業を強化する(前述した保証力やブランド力の強化などが該当する)。新技術の
とりこみを目的とする、実績と信用のある販路を利用した新規事業の開発を行う(納
豆メーカーが現有の発酵技術にプラスアルファしてバイオ食品を開発するなどが該当
する)。優位性の高い製品や技術を梃子に用いて新市場を開拓する(通信機器メーカー
がオンラインの高速データ処理技術などを梃子に用いて既存の金融業者とタイアップ
して、インターネットを利用した株のブローカー業や金貸し業に乗り出すなどが該当
する)
現事業の強化、実績と信用のある販路を利用した新規事業の開発、並びに優位性の
高い製品や技術を梃子に用いた新市場の開拓は、見方を変えれば、魅力ある夢の事業
を実現するために必要な経営資源を取り込むことが目的。だから、「儲かる布石を打
ちながらとりこむ」と前述したわけだ。
なお、魅力ある夢の事業の実現を急がなくてはならない場合もあろう。その場合
は、アミーバ―的な事業展開ではなく、積極的なM&Aを行うことが必要になるのは
言うまでもない。
◎事業展開シナリオの策定はチャンスに強い企業体質をつくる
オイル・ショックや新しい法律の施行といったような「異変」の前には必ず「連続
的な変化」があるもの。漫然と企業経営を行っていると、異変に遭遇して慌てふため
く。ところが、「世の中はかくかくしかじかの理由でこうなるのではないか」といっ
たような問題意識をしっかりと持っていると、変化の連続の中に身を置くことができ
るが故に「異変待ち受けの企業経営」を行うことができるようになることが多い。
事業展開シナリオを策定するのは、このような「異変待ち受け経営」を行うことが
目的であって、計画的に企業経営を行うことに目的があるのではない。(本田技研は
「普通乗用車に進出する」という目標があったからこそ、徐々に深刻になっていく公
害問題が日本版マスキー法の施行に結びつくことを予知でき、先発企業に先駆けて低
公害車の開発に成功。なるが故に、大企業の牙城に食い込むことができたのだ)
→【次へ】
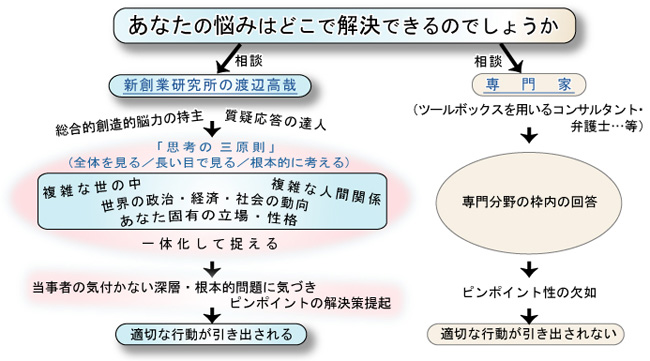
▲トップ
|
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)
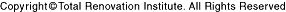
![[TRI] Total Renovation Institute](tri250x86.gif)