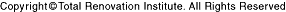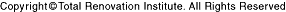3. マルチメディア・ビジネスという救世主
問 個性化ニーズ対応、地球に優しい環境開発、バイオテクノロジーを活用した健康開発・種子開発、マルチメディア、生産プロセス革命、この五つの他に、工業化型製品の用途開発、選択性と組合性の二つ、それから自動車産業の脱工業化関連が先進国産業界の活路であることはよく分かりました。
でも、マルチメディアのことがよく分からないのです。郵政省は「光ファイバーを用いた情報通信基盤を全国的に整備した場合、2010年には123兆円という巨大なマルチメディア市場が形成される」と予測していますが、漠としていて自分個人と会社にとってどういうことを意味するのかどうもはっきりしません。
マルチメディアとは一体何を意味するのか、マルメディアがどうしてそんなに成長性豊かであるかについての理論的説明をして頂けないでしょうか。個人と企業の立場に立って、好機と脅威を具体的に認識したいのです。
答 テレビは与えられた番組を受け身で楽しむだけ、電話は双方向通信が可能であるが、音声情報だけ、パソコンは情報操作ができるが、双方向通信はできない。このようにこれまでの情報メディアはどれをとっても機能的に大きな限界がありました。
ところが、音声・映像・文字・数値の情報の一体的処理・編集・圧縮を可能にするデジタル技術、膨大な情報を同時に送ることのできる光ファイバー、パソコンと通信の合体による双方向通信、この三つの出現によりこれまでのメディアの限界を打破し、これまでのメディアでは不可能だった機能実現を可能にしました。
同一画面で音声・映像・文字・数値の情報を扱えるだけではなく、双方向通信したり、ストックされた情報の切り貼りや好きな角度から競技を観戦したりできるようになったのです。この多機能メディアのことをマルチメディアと言っているのだと思います。でも、これだけでは理想とする情報活動の基盤形成が可能になっただけに過ぎません。
理想とする情報活動の基盤をできるだけ多くの人が活用するためには、世界中にネットワークを張り、必要な情報を検索し、自由自在な情報処理を行うことが可能とならなくてはなりませんが、この実現の鍵はインターネットの普及が握っています。
なぜなら、インターネットは、世界中の各種通信回線とつながっているだけではなく、インターネット上で必要なアプリケーション・ソフトウェアとコンテンツを選択し、必要に応じて組み合わせて使うことを可能にしてくれているからです。
インターネット経由で提供されるアプリケーション・ソフトウェアとコンテンツの種類が豊富になればなるほど、情報処理の自由自在さが増すわけですが、これを実現するためには、通信コストの引き下げ、電波を使った通信、一層のグローバリゼーションの三つにより、インターネット利用者の増加を図り、ソフト事業の意欲を一層刺激する必要があります。
問 インターネットの普及がアプリケーション・ソフトウェアとコンテンツの開発を促進し、これがまたマルチメディアの新製品開発を促進する。そして、マルチメディアの新製品がアプリケーション・ソフトウェアとコンテンツの新たな開発に結びつき、これがインターネット利用者の数を増やす・・・・・といったよう限りない循環が期待できるというわけですね。
答 そうなのです。マルチメディアの経済効果が大きいのは脱工業化の推進だけではなく、工業化型製品の延命も可能になるからなのです。マルチメディアの開発、インターネットの普及、インターネット経由で提供されるアプリケーション・ソフトウェアとコンテンツの開発、の三つが密接に絡み合っている図式をマルチメディア・ビジネスと言いたいのです。
問 地域電話、長距離通信、有線テレビの三業種の垣根の原則撤廃、テレビ・ラジオなどのメディア産業の資本規制の大幅緩和の二つを内容とする「通信改革法」が96年2月に米国で成立したことの意義はきわめて大きいですね。
通信会社とメディア会社の合併や激烈な価格競争が世界を巻き込む形で転換されていることや通信技術の革新を考えると、低価格の通信網が世界中に広がっていきますので、グローバリゼーションに加速がつき、マルチメディア・ビジネスは大発展間違いなしとなりますから。
でも、先進国がマルチメディア・ビジネスを真剣に推進することが前提となっていますが、この前提にちょっと疑問を感じているのです。なぜなら、米国経済が再生路線をしっかりと歩み始めたのは、自動車産業の復活に見られるような工業化型産業の拡大をしたからで、他の先進国も米国を真似るのではないかとふと思ったからです。
答 米国の株価の将来動向をお考え頂ければ、米国は一段と脱工業化を進めなければならないことをご理解頂けるものと思います。米国の株価を更に上昇させることは難しくなったとはいえ、暴落はあり得ない。この株価動向が大きな意味を持ってくるのです。
株式市場において経済的に余裕がない人の割合が高い場合、株価が天井に達すると、ちょっとした下げが暴落に結びつきやすいのですが、米国にはそのような条件があるとは思われないのです。
株主の大勢は資産家、最近株式市場に参加してきた人のほとんどは将来の所得増が期待できる若年層。だから、株の投げ売りに走りやすい人は少ないのです。
したがって、米国の株価は一段と上昇することも暴落することも考えにくいのです。これは二つのことを意味します。米国の消費意欲はそれほど衰えないであろう。これがひとつです。
しかし、低コストの資金調達が困難になるので、その分、米国内の設備投資は低迷し、余剰資金は高収益が期待できる新興工業国に向かい、工業製品の輸入が拡大するであろう。これがもうひとつの意味です。となれば、米国は脱工業化による輸出と雇用の拡大を図らなくてはなりません。他の先進国も似たようなことが言えるのではないでしょうか。
▲トップ